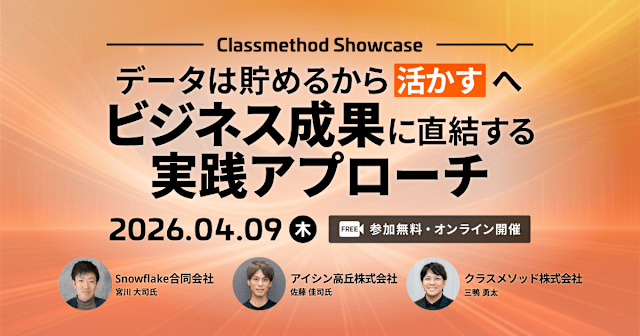【セッションレポート】 かんぽシステムソリューションズにおけるクラウド運用の新基準 ~クラウドCoEによる標準化とコスト最適化の挑戦~ (AP-24) #AWSSummit
はじめに
久しぶりの投稿ですが、AWS Summit Japan 2025 に参加しました。
「かんぽシステムソリューションズにおけるクラウド運用の新基準 ~クラウドCoEによる標準化とコスト最適化の挑戦~」 のセッションレポートです。
セッション概要
それぞれの組織の状況に応じた取り組みが必要な CCoE 構築と内製化。本セッションでは取り組みのポイントを整理したのちに、クラウドの標準化とコスト最適化に向けた、かんぽシステムソリューションズクラウド CoE の 2024 年度の活動についてご紹介します。
「標準ガイドの作成」、「コスト削減施策」、「内製での標準統制環境構築」、「対話型研修を通じた人材育成」など、内製化領域とパートナー支援領域を踏まえて行った取り組みを共有し、その中で見えた新たな課題も含めてご紹介頂きます。
浅野 佑真 氏
株式会社BeeX
事業開発部 副部長
堤 浩一 氏
かんぽシステムソリューションズ株式会社
常務執行役員
サマリ
本記事は、AWS Summit Tokyo 2025 にて開催されたパートナーセッション
「BeeX × かんぽシステムソリューションズ:クラウド活用を標準化とコスト最適化の両輪で推進」
の聴講レポートです。
本セッションでは、BeeXが支援する**かんぽシステムソリューションズ(以下、KSS)**におけるCCoEの立ち上げとクラウド標準化・最適化の取り組みが紹介されました。
KSSが持つレガシー資産や現場の課題に向き合いながら、若手メンバー主導で進めたCCoEの具体的な活動内容や工夫が多く語られており、クラウド活用の理想論ではなく、現実解としてのCCoEの形の1つが垣間見えるセッションでした。
クラウド人材の登用・ガイドライン整備・マルチクラウド選定など、現場に即したテーマが満載で、CCoEや運用部門に関わる方には非常に刺さる内容だったと思います。
内製化に向けた提言
セッション前半はBeeXによる内製化推進に関するナレッジ共有・提言が行われました。
以下のような観点が紹介され、単なる“技術内製化”ではなく、組織としての体制づくり・マインド醸成を含む包括的な内製化の重要性が強調されていました。
- クラウド人材のスキルレベル・役割の可視化
- "デジタル人材がいる"ではなく、どのような行動を取れているかを明確にする必要がある。
- CCoEによるクラウド推進基盤の整備
- 標準化とガイドラインの整備が“現場で使える”形になっているかが重要。
- プロダクトオーナーとクラウド技術者の連携
- ビジネス視点を持つPOと、実装を担うクラウド技術者の連携が成果に直結。
このフェーズで語られたのは、クラウド導入・利用における、「内製化=全部自社でやる」ではないという現実的なスタンスです。
内製化 or ベンダ活用という意思決定のレベルを上げる取り組みこそ重要というメッセージが印象的でした。
かんぽシステムソリューションズにおける取り組みと展望
ここからは実際に内製化・標準化を進めているKSSの事例紹介に入りました。登壇者はKSSの常務執行役員である堤 浩一 氏。基幹システムの開発や移行といった事業会社におけるIT専門のキャリアが印象に残りました。
若手主体で立ち上げたCCoEチーム
- CCoEは2024年に立ち上げ、8名体制でスタート。
- 全員が20代〜30代という構成で、若手中心の推進体制。
- 会場にはチーム全員が参加しており、「有事が起きたら強制送還します(笑)」という一言に、場内も和やかに。
- メンバーは積極的に意見を出してくれるカルチャーで、アクセル・ブレーキのバランスの取れた運営ができているとのこと。
ガバナンス運用
- 各部門のクラウド選定/クラウド開発・運用においていずれのシーンでもCCoEチームがレビューやサポートを実施。
- かなりユーザーに寄り添った支援体制を回しているとともに、工数もかかっていると推察され、クラウド活用に対する本気度を感じる内容。
フェーズに応じたガイドライン整備
- クラウドガバナンスに向けたガイドラインは、企画・調達・開発などのフェーズごとに粒度を調整。
- 仮想サーバーやコンテナといった対象ごとにもガイドを用意し、実際に使える形で整備されている。
- 特に印象的だったのは、クラウド選定における判断フローが明文化されている点。
- 「サポート体制がかんぽ業務に特化しているか」「ミッションクリティカル性」「ベンダーとの親和性」など、クラウドの強み・弱みを前提とした選定が行われていた。
- 実際に運用を回す以上、シンプルなフローにすることが重要と私も感じており、多くの事業会社の参考になる情報だったのではないかと思います。
現場主導の提案と教育体制
- AWS Control Tower導入は現場からの提案により実現。当初の計画にはなかったが、必要性と効果が認められ採用された。
- CCoEメンバーの募集は社内公募形式で、「上司に相談せずに応募してください」という大胆なルールで実施。
- 一時は「上司に無断で応募させるとはけしからん」と現場の反感も買ったそうですが、それでも“やる気を重視する”方針を貫いたとのこと。
- このやる気を重視する姿勢こそが、今のアクセル全開の体制の原動力となっていると感じました。
- オンプレ領域の担当とも連携し、教育にも注力。「教える側の負荷も加味した教育設計」という言葉が印象的でした。
おわりに
このセッションを通して、**「現場に根差したCCoEの運営とはどうあるべきか?」**を考えさせられる貴重な機会となりました。
クラウド推進というと、最新技術やAIなどに目が行きがちですが、
**本質的に大切なのは「人材」「共通言語」「使えるガイドライン」**の3つだと改めて感じさせられます。
とくに印象に残ったのは以下の点です:
- 若手主導でのCCoE立ち上げと現場主導の仕組みづくり
- 判断に迷わないガイドライン設計とクラウド選定基準の明確化
- 教育や育成への本気度。特に“反発があってもやり抜く”姿勢
CCoEという言葉が抽象化されがちな中で、**かんぽシステムソリューションズの取り組みはまさに“実行している組織の姿”**でした。
私自身もAWS運用を担う立場として、今後のCCoE支援や内製化提案の参考にしたいと思います。
セッション資料は以下からダウンロード可能です。
📄 参考資料:セッション資料(PDF)
今回のレポートは以上となります。どなたかのご参考になれば幸いです。