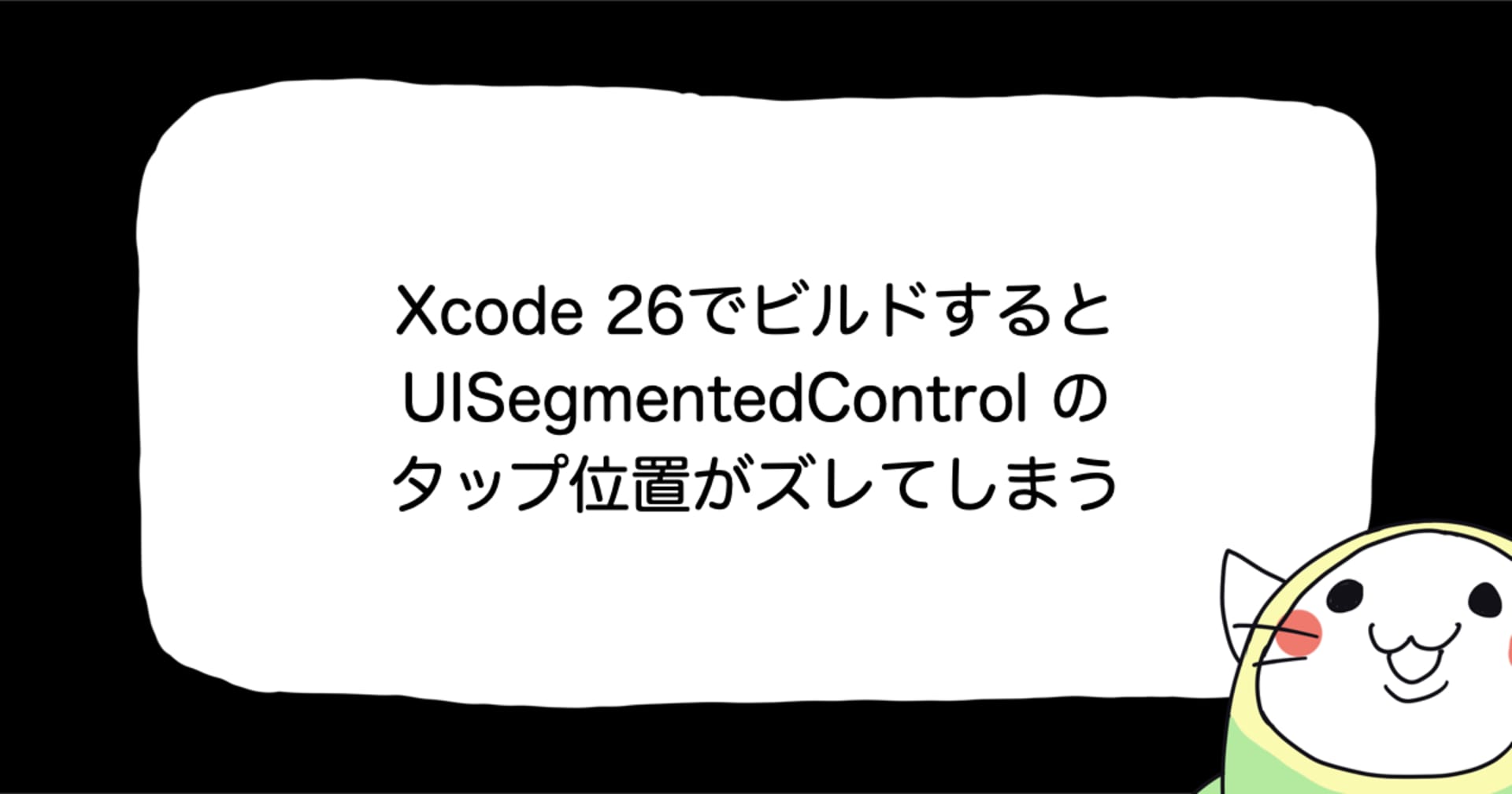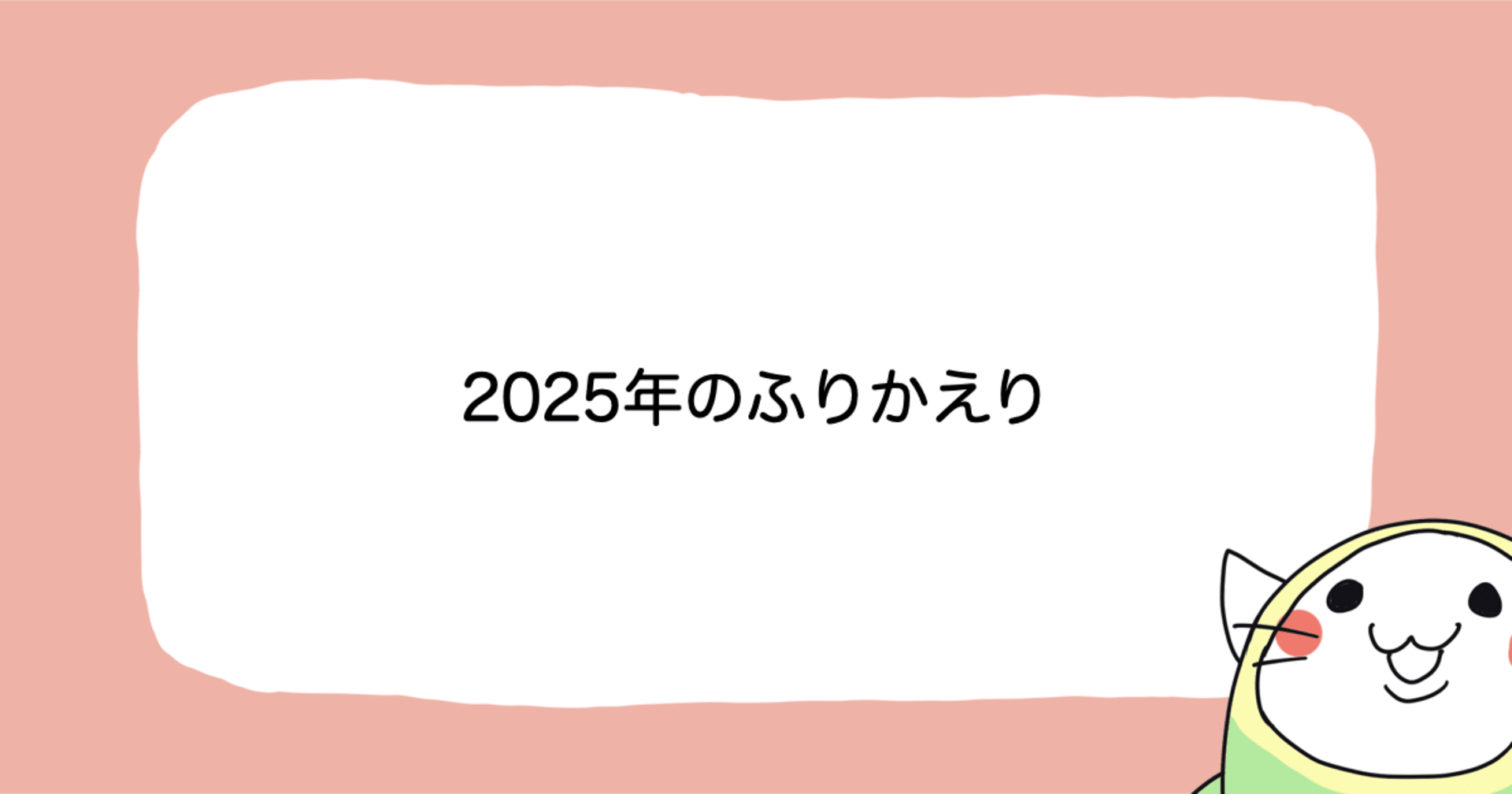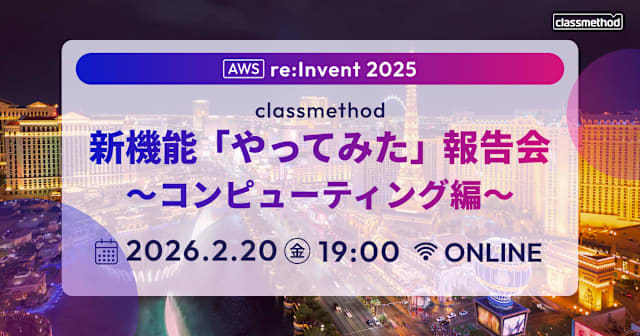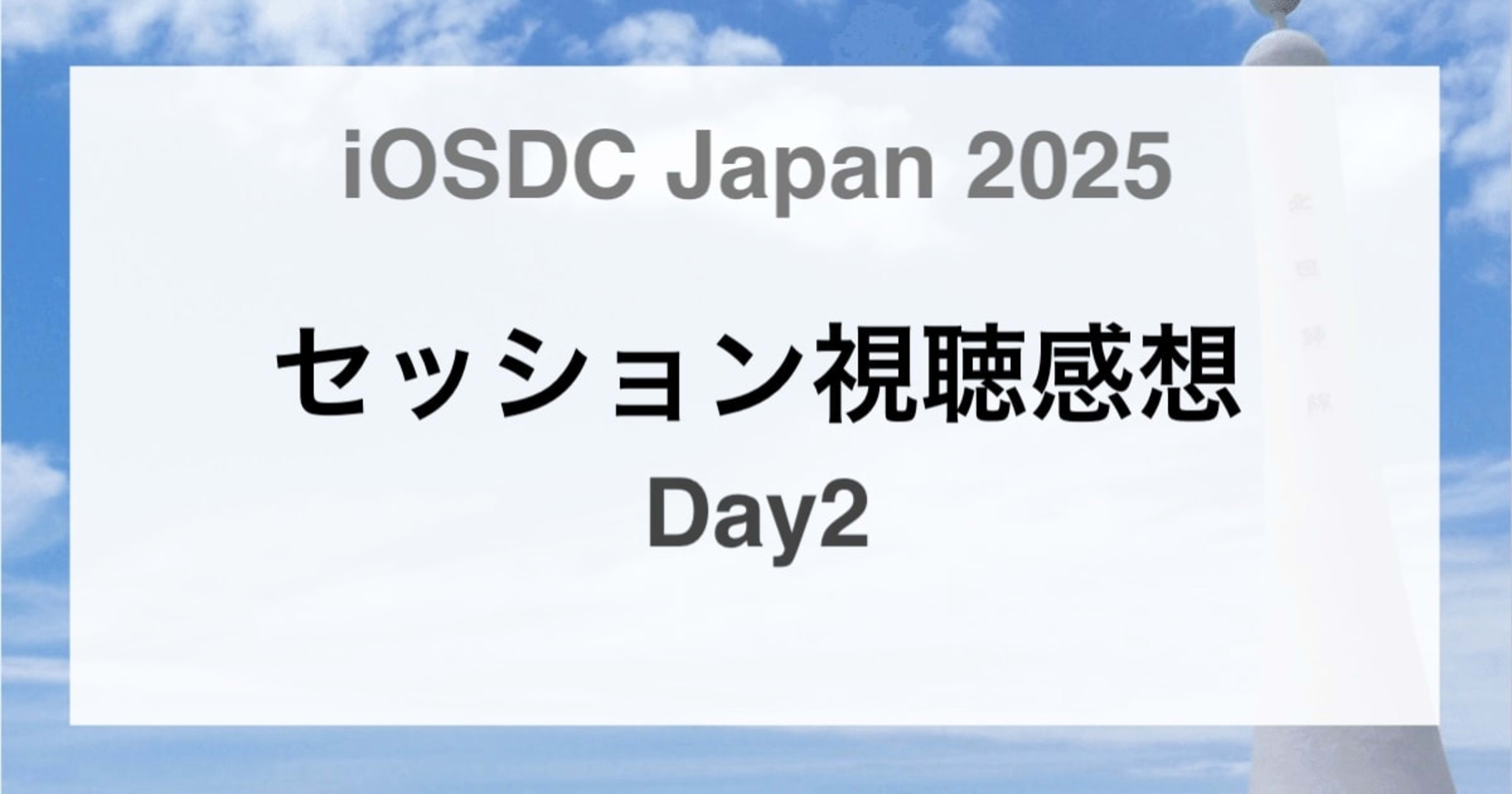
iOSDC Japan 2025 セッション視聴感想-Day2
はじめに
リテールアプリ共創部所属、iOSエンジニアのharukaです。
引き続き、会社のサポートのもと、iOSDC Japan 2025(9月19日〜21日開催)にオンライン参加した感想です。学んだ内容を記録するとともに、皆さんにもシェアできればと思います。
Day1の感想はこちらです。
iOSDC Japan とは?
iOSDC Japan 2025はiOS関連技術をコアのテーマとした、ソフトウェア技術者のためのカンファレンスです。会場は有明セントラルタワーホール&カンファレンスですが、トークセッションについてはオンライン配信も予定しています。
(iOSDC Japan 2025公式サイトから引用)
Track D-ゼロタップの世界へ - UWB × Nearby Interaction 実装ガイド
発表者:岡 優志 さん
紹介ページ:
UWB(Ultra Wide Band:超広帯域無線)技術について、実装経験がないため興味深く視聴しました。
セッション名の通り実装ガイドとして網羅的な内容で構成されており、スライドの公開を心待ちしています。
最後の実機デモが非常に効果的で、技術の可能性を視覚的に理解することができました。
直感的なタップレス操作が実現可能である一方、発表内容にもあるように、現段階では動作の安定性に課題があることが分かりました。機種依存やARKitとの併用など、プロダクション環境での採用には慎重な検討が必要と感じます。デバッグ工数の増加も想定されます。
技術的には魅力的ですが、現段階では安定性の向上を待って導入を検討するのが適切と考えます。
Track C-止められない医療アプリ、そっと Swift 6 へ
発表者:Shogo Yoshida さん
紹介ページ:
担当プロジェクトがまだ Swift 6 に対応していないため、将来的な対応時の参考として視聴しました。
SwiftUI への置き換えやマルチモジュール化など、実践的で参考になる内容でした。ただ、受託案件ではリファクタリングや技術刷新の機会が限られるため、すぐに適用するのは難しいというのが現実です。
@MainActorがPresentation層(ViewとViewModel)まで適用される点やSendableの付与など、自分の認識が正しいことを確認できました。
最後にSwift 6.2 のDefault Actor IsolationとApproachable Concurrencyを取り上げていただき、改めて確認する良い機会となりました。
個人的には、デフォルトで大部分のコードがメインスレッドで実行される仕様について、パフォーマンス面での懸念があります。理想的には画面描画に関連する処理のみメインスレッドで処理し、その他はバックグラウンドスレッドを活用したいところです。
一方で、UIの更新が意図せずバックグラウンドスレッドからアクセスされてクラッシュするトラブルを防げるメリットは大きいと感じます。
将来的にはチームで議論して方針を決定する必要があると感じました。
Track B-逆向きUIの世界〜iOSアプリのRTL言語対応〜
発表者:akatsuki174 さん
紹介ペーシ:
RTL(Right-to-Left:右から左に読む)言語対応について、非常に網羅的で充実した内容でした。
文字だけでなく、リストのボタンの位置やアイコンも反転される仕様について初めて知ることができました。
本格的なRTL言語対応を行う場合、アプリケーション全体を隅々まで確認する必要があり、工数が相当増加することが想定されます。
先日に引き続き、標準コンポーネントが多くの恩恵を自動的に提供してくれることを改めて実感しました。
標準コンポーネントを使用することで大部分の対応は自動化されますが、それでも対応しきれない部分があるため、カスタムUIではさらに工数が増加する可能性があります。
このセッションで学んだ標準コンポーネント活用の重要性は、設計段階から意識すべきポイントとして今後の参考になりました。
Track B-『ホットペッパービューティー』のiOSアプリをUIKitからSwiftUIへ段階的に移行するためにやったこと
発表者:Akihiro Kokubo さん
紹介ペーシ(スライドあり):
UIKitからSwiftUIへの移行とマルチモジュール化について、将来的な技術選択の参考として視聴しました。
体系的で図解も豊富な、非常に理解しやすいセッションでした。
UIコンポーネント単位から段階的に進めるアプローチは、影響範囲を限定でき、リスクを最小化できる優れた手法だと感じました。
UIコンポーネントをデザイナーと連携して整備するプロセスも印象深く、ガイドラインの重要性を認識しました。
画面遷移については引き続きUIKitベースを維持する判断も適切だと思います。移行時には全面的な変更ではなく、適切に範囲を定めることの重要性を学びました。
マルチモジュール化について、この二日間で頻繁に言及されており、SwiftUI移行やSwift6対応など、メンテナンス性向上には不可欠な前提条件という印象を受けました。
将来的な技術刷新においては、まずマルチモジュール化を検討してから、UIコンポーネントレベルでのSwiftUI導入を段階的に進めていく方針を検討したいと考えています。
終わりに
ライトニングトークも含めて、2日間を通じて技術的価値の高いセッションを多数視聴することができました。
特に大規模アプリケーションでの技術移行戦略や新技術の実用性について、実践的な知見を得ることができました。学んだ内容は今後の開発における技術選定や開発方針の検討において重要な参考情報となります。
引き続き、これらの技術動向をキャッチアップしていきたいと思います。