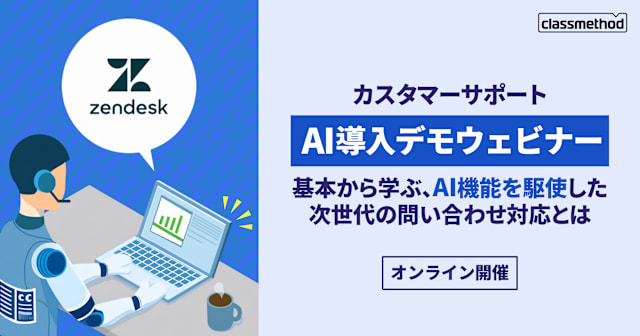「ここがアジャイルの世界か」 ~ 業務SEがアジャイラーになるまでの8か月 #scrumosaka
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
Scrum Fest Osakaとは?
2020年6月26(金)・27日(土)にScrum Fest Osakaがオンラインで開催されました。 Scrum Fest Osaka 2020@ONLINEは以下のようなイベントです。クラスメソッドではシルバースポンサーとして協賛を行いました。
Scrum Fest Osakaはスクラムの初心者からエキスパート、ユーザー企業から開発企業、立場の異なる様々な人々が集まる学びの場です。この2日間を通じ、参加社同士でスクラムやアジャイルプラクティスについての知識やパッションをシェアするだけでなく、ここで出会ったエキスパートに困りごとを相談することもできます。
「ここがアジャイルの世界か」 ~ 業務SEがアジャイラーになるまでの8か月
本記事は、セッション「「ここがアジャイルの世界か」 ~ 業務SEがアジャイラーになるまでの8か月」をレポートします。
スピーカー
株式会社永和システムマネジメント
Yukio Okajima
Yuichi Hashimoto
セッション概要
巨大ウォーターフォールプロジェクトの一員であった業務SEは、8か月後、重要なアジャイルプロジェクト(※)を任されるエンジニアになっていました。
「なぜ?」「どうやって?」。このセッションでは、チャレンジした本人(橋本)とそれを支える組織(岡島)それぞれの目線から、次の切り口で明らかにしていきます。
価値:変化を抱擁する世界へのチャレンジと、それを支援するアジャイル組織の在り方
原則:本気で取り組むための「ビジネスと学びの両立」「段階的動機付け」「組織能力化」
プラクティス:プログラミング未経験の業務SEが成長するために日々考え実行したこと
レポート
導入パート
7ヶ月で業務SE(ウォーターフォール/金融/何千人月/設計のみでプログラム経験なし)の橋本さんが
アジャイルを経験した記録
計画<3つのフェーズ>
◇スケジュール ・体験(1.5ヶ月 ・実習(2.5ヶ月 ・実践(3ヶ月 ◇最終目標 ・アジャイル ・モダンWeb JAVAで作成
体験のフォーメーション
◇知恵の師匠 →メンターのエンジニア ◇知識の先生 →座学中心 ◇相談の管理者 → 相談、評価先
■Gitの使い方などもここで会得
実習フェーズのフォーメーション
◇師匠 →一緒に仕事する ◇管理者 →相談、評価先
■実務に入る
■今までの業務と違って、スピードが違うと感じた
■コードレビューを受ける
■障害対応をする
実践のフォーメーション
◇開発メンバー(橋本さん(PO)/若手/20年選手) →みんなスクラム初めて ◇スクラムマスター →岡島さん ◇師匠 →見守り ◇伝説 →技術課題の相談役
■自ら体験だけではなく、若手に教える事で教育効果が期待できる
■フレームワーク調査
■デイリースクラムで困り事を共有
■課題が多くなり、チームワークが悪くなった
■お客様がスクラムを理解出来ていない
効果的だったプラクティス
◇モブプログラミング →コンフリクトが減った →課題解決に寄与 →レビューが同時にできる →伝説(上級者)とのセッション ◇振り返り →課題解決策が出た →スクラムマスターも参加
実践の厳しさ/難しさ
◇新しい学びが多い ◇成果が上がらなくても、顧客に転嫁出来ない ◇実務なのでチームバランスがいつでもいいとは限らない
■お客様のフィードバックにどこまで対応すればいいかわからない
→要望に答えるのが正義と考えてしまう
■カイゼンが出来ない
■計画通りに動けない
■チームとして機能してない
→無意識にチームを誘導(Yesとメンバーに言わせていた)
■頭の中と行動に大きなギャップ
→アジャイルのつもり
カイゼンが進むポイント/体験から得られたこと
■ヒントを周囲がくれる
→営業の人やアジャイルを知らない人からも実務的なアドバイスをもらえた
■実際にやってみる
→自信が湧く
■チームの大切さ
→雰囲気をよくする
→チームの成長
■お客様との関係性
→お客様に言われた事だけをやるではなく、自ら動く熱い気持ち
→お客様と共に創るという思い
現在の状況
■マインド
→アジャイルを実践
■対話、協調性、会話
→お客様とチームメンパーとも
■お客様
→「共に創る」、仲間として動く
■チームビルド
→チームの強みを活かす
→弱みをカイゼン
→メンバーとの信頼関係
アジャイル未経験者をいきなりプロジェクト投入すると
■敷居が高い
■成長できるかもしれないがチームのベロシティは下がるし、メンバーは苦い顔をしがち
■本人のプレッシャーが大きい
■本人の努力の結果が見えるようなやり方が良い
まとめ
■本質を学べる環境を準備し、技術ギャップの混乱を最小限に
■とにかく手を動かす
■フェーズ分けで成功体験を重ねる