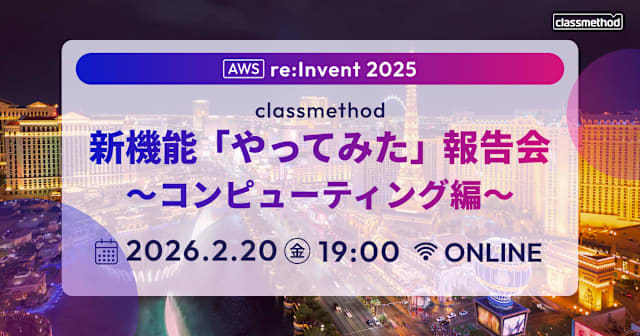7 ヶ月で 99 本の記事を書いて学んだ、技術ブログのライティングにおける 3 つのポイント
はじめに
クラスメソッド株式会社に合流してから 7 ヶ月が経ち、明日からは 8 ヶ月目に入ります。この期間でブログ記事を 99 本書き、次に書くのが記念すべき 100 本目となります。
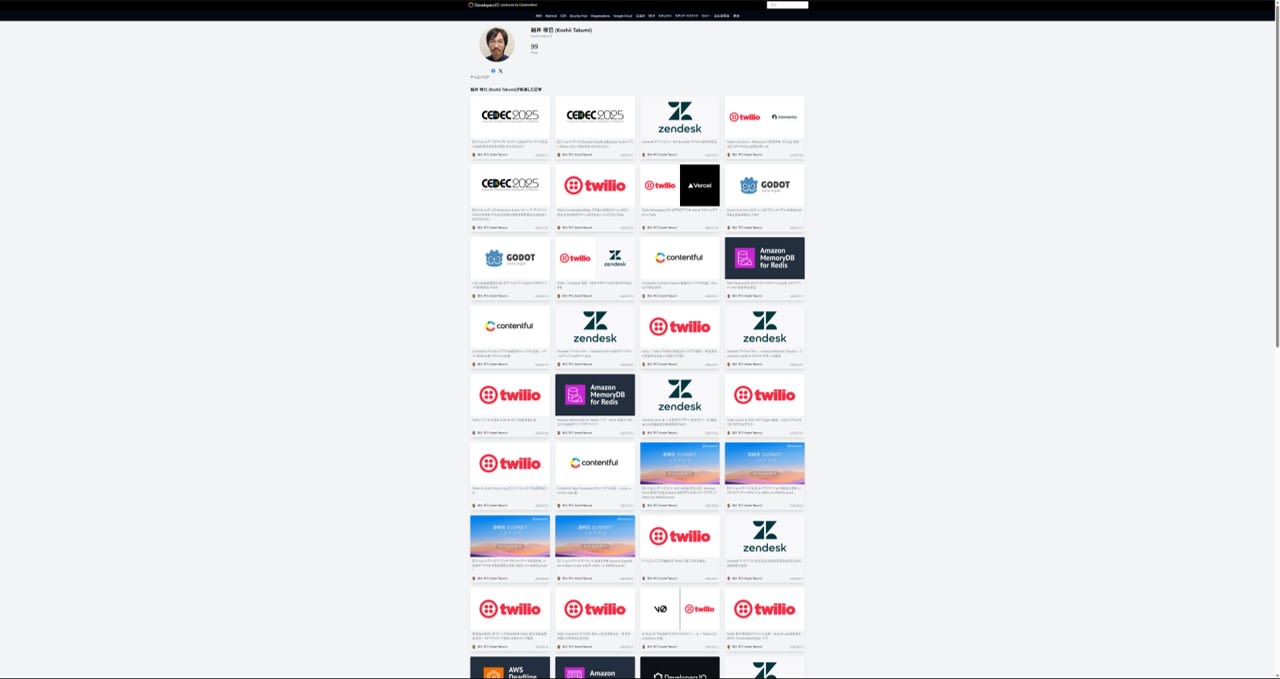
ブログを書く理由は人それぞれですが、私にとっては学習の定着と知識の整理、そして同じ課題に直面する誰かの助けになることが主な動機でした。組織にとっても、技術力のアピールやナレッジの蓄積といった価値があります。99 本の記事を書く中で、 SaaS の機能紹介記事が多くを占めました。特に反響が大きかったのは v0 に関する記事 で、トレンドに乗れたことがポイントでした。ゲームエンジニアの視点から Twilio の魅力について語った記事 も予想以上に読まれ、視点の独自性の重要さを実感しました。
この経験を通じて、記事を書く上で特に重要だと感じた 3 つのポイントが見えてきました。それは「抽象度をコントロールして書く」 「対象読者を明確にする」 「再現性を大切にする」という 3 点です。この記事ではこれら 3 つのポイントについて、7 ヶ月間の試行錯誤で得た生の経験を基に解説します。これから技術ブログを書きたいと考えている方にとって参考となれば幸いです。
対象読者
- 技術ブログを書き始めたいが、何から手をつけて良いか分からない方
- すでに技術記事を書いているが、より多くの人に読まれる記事を書きたい方
- 継続的に記事を書いているが、ライティングスキルを体系的に整理したい方
- 企業ブログでの執筆を任されたが、効果的な書き方を知りたい方
抽象度をコントロールして書く
技術記事において最も重要なスキルの一つが、抽象度のコントロールです。抽象度とは、情報の具体性と概念性のレベルを指します。読者が迷子にならないよう、適切な抽象度で情報を提示することが、理解しやすい記事を書く鍵となります。
冒頭での全体像提示
記事の冒頭では、必ず抽象度の高い話から始めます。「この記事を読むと何ができるようになるのか」を 10 秒で理解できるよう、概念的に記事の全体を説明します。
例えば、 サービスの新機能を紹介する記事 であれば、いきなり設定手順に入るのではなく、「この機能は何を解決するのか」 「従来の方法と比べてどう優れているのか」を先に説明します。可能な限り図や GIF アニメを活用し、視覚的に理解できるよう工夫します。(例: この記事 冒頭の GIF アニメ等)
見出し設計と構成の工夫
見出しだけを読んでも記事の流れが分かる構成を心がけます。見出しは記事の骨格であり、読者が内容を予測できる道しるべの役割を果たします。
重要なのは、構成をテンプレートに従って設計することです。序論・本論・結論のような基本的な構成や、技術記事であれば「概要 → 前提条件 → 手順 → まとめ」といった定型的な流れに沿うことで、読者の認知負荷を下げることができます。読者は慣れ親しんだ構成であれば、内容に集中でき、迷うことなく記事を読み進められます。
テンプレートに従うことは創造性を制限するように感じるかもしれませんが、実際には読者にとって親切な配慮です。予測可能な構成は理解を助け、情報の吸収効率を高めます。
理由の併記とモチベーション管理
具体的な手順に突入する前に、「なぜこの手順が必要なのか」の理由を必ず併記します。読者のモチベーションを維持するためです。
生成 AI や最新のアップデート情報をまとめた記事では、この原則がより重要になります。トレンド記事は読まれやすい反面、読者の期待値も高いため、冒頭で「この記事で何が分かるのか」を明確に示すことで、最後まで読んでもらえる確率が高まります。トレンド記事は書くのが速ければ速いほど良いという特性があるため、抽象度設計を事前にテンプレ化しておくことで執筆スピードの向上にもつながります。
対象読者を明確にする
技術記事が読まれるかどうかは、対象読者の設定にかかっています。誰に向けて書いているのかが曖昧だと、内容も曖昧になり、結果として誰にも刺さらない記事になってしまいます。
技術レベル別のアプローチ
まず、読者の技術レベルを明確に設定します。技術に慣れている人向けなのか、全く分からない人が読んでも理解できる記事なのかを決めることで、使用する専門用語のレベルや説明の詳しさが決まります。
初心者向けの記事では、専門用語を使う際に必ず説明を併記し、前提知識を仮定しません。一方、上級者向けの記事では、基本的な概念の説明は省略し、より高度な内容に焦点を当てます。読者に寄り添い、読者と共に理解の進行度のベースラインを一緒に底上げする気持ちで書くことが重要です。
検索キーワード戦略
読者が検索で辿り着きやすいキーワードを意識することも重要です。 SaaS を紹介するとき、サービス名だけでなく、その SaaS が解決する課題に関連するキーワードも考慮します。
例えば、 SMS 送信サービスを紹介する記事 では、「SMS」 「Python」 「自動送信」 「通知」といった関連キーワードでも検索される可能性があります。サービス名を知らない潜在的なユーザーも、これらのキーワードから記事に辿り着くことができます。そういった層も考慮したワーディング設計によって、より多くの読者にリーチできます。
視点の独自性を活かす
ゲームエンジニアの視点から Twilio の魅力について語った記事 が予想以上に読まれたのは、独自の視点が価値を生んだ例です。同じ技術でも、異なる業界や職種の視点から語ることで、新たな読者層を開拓できます。
自分の専門分野や経験を活かした独自の切り口を見つけることで、競合記事との差別化を図れます。技術的な内容は同じでも、語る人の背景や視点が異なれば、全く違う価値を提供できるのです。
トレンド記事での読者ニーズ
生成 AI や最新のアップデート情報をまとめた記事は読まれやすい傾向にあります。これらのトレンド記事では、読者のニーズが明確で緊急性が高いため、対象読者の設定がより重要になります。
トレンド記事の読者は、最新情報をいち早く知りたい人、実際に試してみたい人、ビジネスへの影響を知りたい人など、動機が多様です。記事の冒頭で「どの読者層に向けた記事なのか」を明確にすることで、読者は自分にとって有益な記事かどうかを素早く判断できます。
再現性を大切にする
技術記事の価値は、読者が実際に同じ結果を得られるかどうかにかかっています。再現性とは、「誰が、いつ、どこで読んでも同じ動作を再現できる」ことを意味します。これは読者にとっても、また、未来の自分にとっても重要な要素です。
環境情報の明記
記事で紹介する内容を実際に試した環境を必ず記載します。OS のバージョン、使用したソフトウェアのバージョン、前提となる設定など、再現に必要な情報を漏れなく書きます。
例えば、API バージョン: v2、検証日時: 2025年7月 といった具体的な情報を記載することで、読者は自分の環境との違いを把握でき、問題が発生した際の原因特定にも役立ちます。 (例: この記事 の 「検証環境」セクション 等)
できない場合の対処法
すべての環境で完璧に動作することは現実的ではありません。重要なのは、できない場合にその原因がはっきり分かることです。よくあるトラブルとその対策方法を事前に調査し、記事に含めることで、読者の問題解決を支援できます。(例: この記事 の この手順を忘れると Function からの Asset 内容参照に失敗するので注意してください。 の記載等) 特定の環境でのみ動作する場合は、その制限を明確に記載します。「この方法は Windows 環境では動作しません」といった制限事項を隠さずに書くことで、読者の時間を無駄にすることを防げます。
複数の手順を含む記事では、どの段階で動作確認を行うべきかも明記します。例えば、「ここまでの設定で一度動作テストを実行してください」 「この段階で単体テストを通しておくことで、後の手順でエラーが発生した際の切り分けが容易になります」といった中間確認ポイントを設ける (例: この記事 の 「ローカルでの動作確認」セクション 等) ことで、読者が問題を早期発見できるよう配慮します。
コードとスクリーンショットの効果的活用
実際のコードやスクリーンショットは、再現性を高める重要な要素です。コードブロックには適切なコメントを付け、何をしているのかを明確にします。スクリーンショットでは、重要な部分を赤枠で囲むなどハイライトし、読者が見るべきポイントを明確に示します。
特に SaaS の設定記事では、UI の変更が頻繁に発生するため、記事執筆時のスクリーンショットを記録しておくことで、更新があった際差分を調査するための資料としても役立てることができます。
まとめ
7 ヶ月で 99 本の記事を書く中で学んだ 3 つのポイントを振り返ります。
- 抽象度をコントロールして書く
冒頭での全体像提示、テンプレートに従った構成設計、理由の併記による読者のモチベーション管理が重要であることを説明しました。また、抽象度設計の事前テンプレ化が執筆スピードの向上につながります。 - 対象読者を明確にする
技術レベル別のアプローチ、検索キーワード戦略、独自の視点の活用について解説しました。読者に寄り添い、共に理解度を底上げする気持ちで書くことが、多くの人に読まれる記事につながります。 - 再現性を大切にする
環境情報の明記、トラブル対処法の記載、中間確認ポイントの設置、効果的なコードとスクリーンショットの活用を取り上げました。「誰が、いつ、どこで読んでも同じ動作を再現できる。もしくは、できないなら理由が分かる。」記事を目指すことが重要です。
これらのポイントは、継続的な執筆を通じて身についたものです。完璧を目指すよりも、まずは書き始めることが大切だと思います。一本一本の記事執筆を通して、読者に寄り添う気持ちを忘れず改善を重ねていけば、必ず読まれる記事が書けるようになると考えます。
技術ブログは、自分の学習を深めるだけでなく、同じ課題に直面する誰かの助けになる価値ある活動です。自分が困っているということは、世界の誰かも困っているはずです。その困りごとを解決した経験を記事として残すことで、未来の誰かの時間を節約し、課題解決の手助けができます。
この記事が、これから技術ブログを書き始める方の参考になれば幸いです。