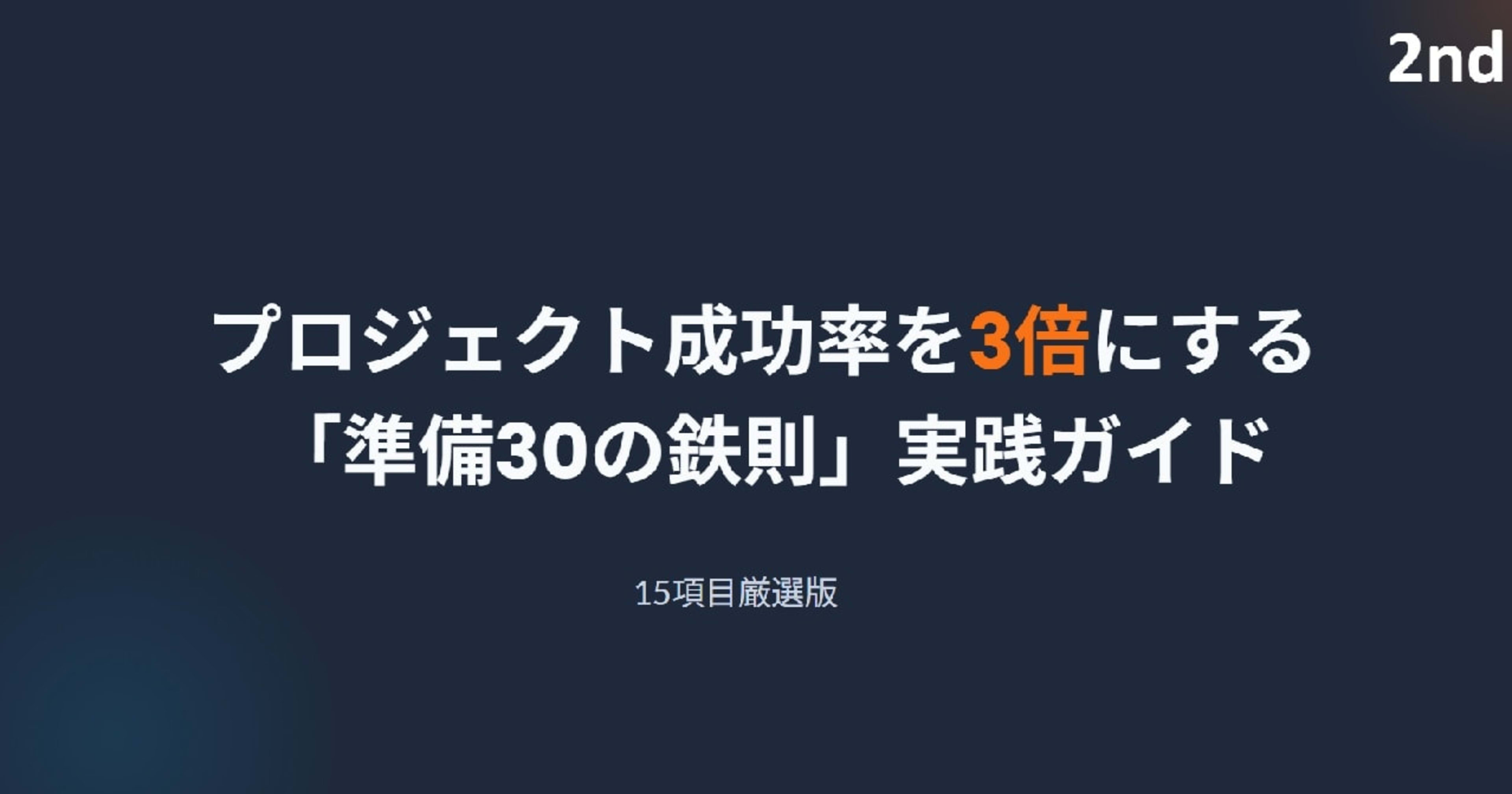
プロジェクト成功率を3倍に引き上げるテク30 ~2nd
どうも、たてやんです。
プロジェクト成功率3倍テクシリーズ、第2弾です。
前回、「運用の4か条」をお伝えしました。
目標、期限、責任者、管理。
この4つを決めるだけで、プロジェクトの成功率は劇的に上がります。
でも、これだけでは足りません。「決めたことが、伝わらない」これが次の壁です。
あなたの組織でも、こんな経験ありませんか?
「キックオフで説明したのに、誰も覚えてない」
「週次MTGで決めたはずなのに、実行されてない」
「同じ質問が何度も来る」
これ、全部コミュニケーション設計の失敗です。
今回は、「決めたことを、確実に伝え、実行してもらう」ためのコミュニケーション設計3項目をお伝えします。
早くも読み物化に苦戦しているので、連載ラストのまとめ資料にご期待頂いてもOKですw
鉄則5: 導入目的を明確にする
なぜ必要か:「何のためにやるのか」が曖昧だと、誰も本気にならない
悪い例:
「新しいツールを導入します」
「業務効率化のため、システムを刷新します」
「DX推進のため、AIを活用します」
→ 何も伝わりません。たぶんメンバーはこう思います。
「で、俺は何すればいいの?」
「なんでこのタイミング?」
「今のやり方じゃダメなの?」
良い例:
【プロジェクト目的】
なぜ: 顧客対応に時間がかかりすぎて、営業活動ができていない
現状: 1件あたり平均30分 → 1日8件対応で6時間消費
問題: 新規開拓の時間がない → 売上が伸びない
↓↓↓
【目指す姿】
対応時間を15分に短縮 → 1日16件対応可能
空いた3時間を新規開拓に → 月10件の新規商談創出
↓↓↓
【メンバーへの影響】
✓ 残業が減る(現状月20時間 → 10時間へ)
✓ 新規案件が増える → インセンティブ増
✓ スキルアップ(AIツール活用経験)
→ 「なぜ」「何が変わるか」「自分にどんなメリットがあるか」が明確
チェックリスト
- □ 「なぜ今やるのか」が説明できる
- □ 「現状の問題」が数値で示されている
- □ 「目指す姿」が具体的に描かれている
- □ 「メンバーへのメリット」が明示されている
- □ 経営層の本気度が伝わっている
- □ A4用紙1枚にまとまっている
鉄則6: 運用期間を設定する
なぜ必要か:「いつまで」が決まってないと、永遠に終わらない
前回、プロジェクト全体の期限(鉄則2)を説明しました。
今回は、運用フェーズごとの期間設計です。
悪い例:
「とりあえず始めて、様子を見ながら」
「軌道に乗るまで続ける」
「うまくいったら本格導入」
→ いつまで? 何をもって「軌道に乗った」と判断?
良い例
【運用期間設定】
Phase 1: 準備期間(2週間)
- Week 1: キックオフ、マニュアル作成
- Week 2: トレーニング、テスト運用
Phase 2: 初動期間(4週間)
- Week 3-6: 本格運用開始
- 毎週金曜: 進捗報告
- 問題発生時: 即座にサポート介入
Phase 3: 定着期間(6週間)
- Week 7-12: 自走化
- 隔週金曜: 進捗確認
- 好事例の横展開
Phase 4: 評価期間(1週間)
- Week 13: 最終評価
- 成果測定、課題抽出
- 次フェーズの計画策定
→ いつ、何をするかが明確
ポイント1: 初動3ヶ月集中投下
ポイント2: 週次単位で期限を切る
ポイント3: 「終わり」を明確にする
殆どの人は短距離走者で、その後、いつの間にかタスクが空中分解します。
そして、できる人はごく一部で、できる人は端から自分ルールを持っていたり、言わなくてもやってます。
過去の統計データでは3カ月目以降継続率が面白いほど下がり始めましたw
なので、短く週単位で切り、「いつまでにどのフェーズ」を明確にしましょう。
チェックリスト
- □ プロジェクト全体が3ヶ月以内
- □ 週次のマイルストーンが設定されている
- □ 各週の達成基準が明確
- □ 最終評価日が決まっている
- □ Phase 1終了後、Phase 2の計画がある
- □ 全スケジュールが可視化されている(Gantt等)
鉄則7: チーム別の責任者を決める
なぜ必要か:全体の責任者がいても、現場が動かない
前回(鉄則3)、プロジェクト全体の責任者を決めました。
でも、それだけでは足りません。各チーム・各拠点・各部門にも責任者が必要です。
悪い例:
【プロジェクト体制】
プロジェクト責任者: 部長
メンバー: 営業部20名、サポート部15名、開発部10名
→ 誰が何をやるの?
各部門のメンバーの心の声:
「部長が責任者なら、俺は関係ない」
「何かあったら部長が対応するんでしょ」
「他の人がやってくれるだろう」
良い例
【プロジェクト体制】
- 全体責任者: 鈴木部長
- 営業部リーダー: 田中課長
- 東日本チーム責任者: 佐藤主任(10名)
- 西日本チーム責任者: 伊藤主任(10名)
- サポート部リーダー: 山田課長
- 1次対応責任者: 高橋係長(8名)
- 2次対応責任者: 中村係長(7名)
- 開発部リーダー: 渡辺課長
- フロント責任者: 小林エンジニア(5名)
- バックエンド責任者: 加藤エンジニア(5名)
各責任者の役割:
- 週次進捗報告(毎週金曜15:00)
- メンバーの質問対応(24時間以内)
- 問題発生時の即時エスカレーション
→ 誰が何を担当するか明確
ポイント1: 「現場に近い人」を責任者に
ポイント2: 責任範囲を明確に
ポイント3: 責任者を「支援」する
笑えない笑い話ですが、「みんなでやろう!」と言ったら誰もやりません。
「●●さんの目標は××ね!」と名指しで指名するとやります。
その効果は指名なし⇔指名ありで2.93倍の効果の開きがありました。。。。
チェックリスト
- □ 各チーム・部門に責任者が任命されている
- □ 責任者の役割が文書化されている
- □ 責任範囲(メンバー数、目標値)が明確
- □ 権限(予算、人事)が委譲されている
- □ 報告ルール(頻度、フォーマット)が決まっている
- □ 責任者へのサポート体制がある
- □ 責任者向けのマニュアルが用意されている
まとめ
今回のポイント
- Whyを伝える、メリットを伝える。
- 人は忘れる。短距離走指定で。長くて3カ月。週次目標も設定
- 「みんなで」は他人事。タスクはbynameで。
今日からできること
- 週次マイルストーンをカレンダーに入れる
- 各チームの責任者を指名する
- 責任者との週次MTGをスケジュールする
聞くと「そりゃそうだろ」と思う事、意外に手が回ってない事多いです。
それだけなのにプロジェクトの成否は意外とそこに左右されたりします。
せっかくやっているんなら、少しの工数を惜しまず、必ず成功させましょう。
次回は第3回!お楽しみに!
連載スケジュール(再掲)
- 第1回: 運用の4か条 ✓
- 第2回: コミュニケーション設計(前編) ← 今回
- 第3回: コミュニケーション設計(後編)
- 第4回: モチベーション設計
- 第5回: ツール・マテリアル(前編)
- 第6回: ツール・マテリアル(後編)
- 第7回: 実働段階 + 総括






