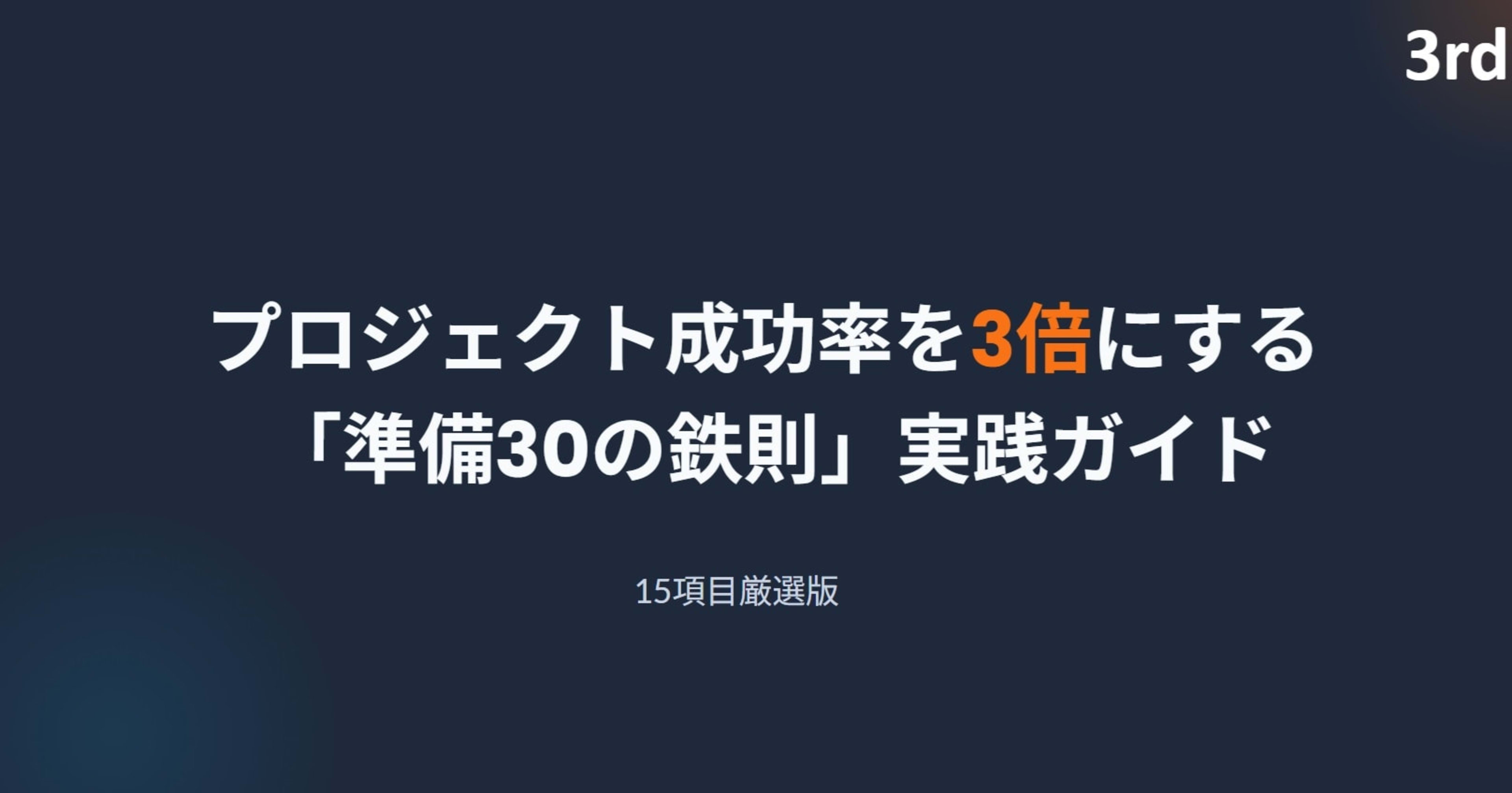
プロジェクト成功率を3倍に引き上げるテク30 ~3rd
どうも、たてやんです。
プロジェクト成功率3倍テクシリーズ、第3弾です。
前回はコミュニケーション設計の前編として、「目的」「期間」「責任者」の3つをお伝えしました。
それでも人はまだ動きません。面白いぐらいに。
今回は、決めたことを「実行」に移し、プロジェクトを「推進」させるためのコミュニケーション設計(後編)、2つの鉄則をお伝えします。
ではどうぞ。
鉄則8: タスクを明確にする
なぜ必要か:「何をすればいいか」が分からないと、人は動けないから。
悪い例:
「佐藤さん、例の件よろしく!」
「みんなで協力して、資料作っちゃおう!」
「手が空いた人で、バグ修正お願い」
→ 100%動きません。たぶんメンバーはこう思います。
「例の件って、どれ?」
「『みんなで』って、誰がやるの? 俺じゃないよな…」
「『手が空いた人』なんて、うちのチームに存在しないんだが?」
良い例:
タスクは「5W1H」を意識しつつ、超絶シンプルに1日のタスクを言い換えましょう。
- 「1日●件、××の顧客に△△して!」
→ いつまでに、何を、どのレベルまでやればいいか、一目瞭然。
ポイント1: 動詞で指示する
「顧客対応」ではなく「メールを送る」「情報連携する」など、具体的に行動できるレベルまで分解しましょう。
ポイント2: 完了条件を決める
担当者が複数いるタスクは、誰も責任を取りません。必ず一人を指名しましょう。
チェックリスト
- □ 1名1名のタスクは明確化?
- □ 期限は「日付+時間」で設定されているか?
- □ 「何をすれば終わりか」という完了条件は明確か?
- □ なぜこのタスクが必要か、背景も伝えているか?
- □ タスク管理ツール(Asana, Trello等)で全員が見える状態か?
鉄則9: 報告ルールを徹底する
なぜ必要か:「報告がない=PJT順調」ではないから。
プロジェクトで一番怖いのは「静寂」です。問題は、報告されない限り存在しないのと同じ。そして気づいた時には手遅れになります。
悪い例:
「何かあったら言ってね」
「進捗どう?」「順調です!」
(月末になって)「すみません、間に合いません…」
→ これが一番最悪のパターン。マネージャーは何もコントロールできません。
良い例:
報告は「仕組み」で吸い上げるものです。フォーマットと時間を固定しましょう。
- 【週次報告ルール】
- 報告タイミング: 毎週金曜 16:00まで
- 報告場所: Slackの「#proj-report」チャンネル
- 報告フォーマット(テンプレート):
- 今週やったこと(Fact):
- 〇〇画面の設計完了
- △△のバグを3件修正
- 課題・懸念点(Problem):
- ××の仕様で不明点があり、作業が止まっている(担当:Aさん)
- 来週やること(Next Action):
- ××の仕様をAさんに確認
- □□画面の設計に着手
- 今週やったこと(Fact):
→ たった3項目。書くのに5分もかかりません。でも、これだけでプロジェクトの状態が手に取るように分かります。
もっと簡単な報告で言うなら「対応案件数を正の字で書いて、共有シートに数字だけ記入!」とかでもいいです。
ポイント1: フォーマットを統一する
自由記述の報告は、読むのに時間がかかり、重要な情報が埋もれます。
ポイント2: 悪い報告ほど早く上げる文化を作る
「問題を見つけた人=偉い」という雰囲気を作りましょう。問題を隠すのが一番の悪です。
ポイント3: 報告に必ず目を通し、リアクションする
報告しても無反応だと、誰も報告しなくなります。スタンプ1つでもいいので、必ず反応しましょう。
人間、めんどくさい事は続きません。自分だけしかやってない事もなかなか継続できません。
聞いてもらえる、報告が反映されてることで安心が生まれます。
チェックリスト
- □ 報告のテンプレートは決まっているか?
- □ 報告の期限(曜日・時間)は決まっているか?
- □ 報告の場所(ツール・チャンネル)は決まっているか?
- □ 「悪いニュース」を歓迎する雰囲気があるか?
- □ 緊急時のエスカレーションルールは決まっているか?
まとめ
今回のポイント
- タスクは「5W1H」で明確に。担当者は必ず一人。
- 報告は「仕組み」で吸い上げ、フォーマットと時間を固定する。
- 「静寂」は危険信号。悪い報告ほど価値がある。
今日からできること
- □ チームのタスクを1つ選び、「5W1H」で書き直してみる
- □ 3項目だけのシンプルな週次(あるいは日次)報告テンプレートを作り、チームに共有する
一見、マイクロマネジメントで面倒に見えるかもですが、これは管理ではなく「連携」です。
阿吽の呼吸なんて幻想。言葉と仕組みで連携して初めて、チームは本当の力を発揮します。
神は細部に宿る、ではないですが細かい点を継続できてこそ大きな成果が得られます。
◆次回予告
第4回: モチベーション設計
仕組みだけでは、人は疲弊します。メンバーが「やりたい!」と自走する仕掛け作りについて解説します。
◆連載スケジュール(再掲)
- 第1回: 運用の4か条 ✓
- 第2回: コミュニケーション設計(前編) ✓
- 第3回: コミュニケーション設計(後編) ← 今回
- 第4回: モチベーション設計
- 第5回: ツール・マテリアル(前編)
- 第6回: ツール・マテリアル(後編)






