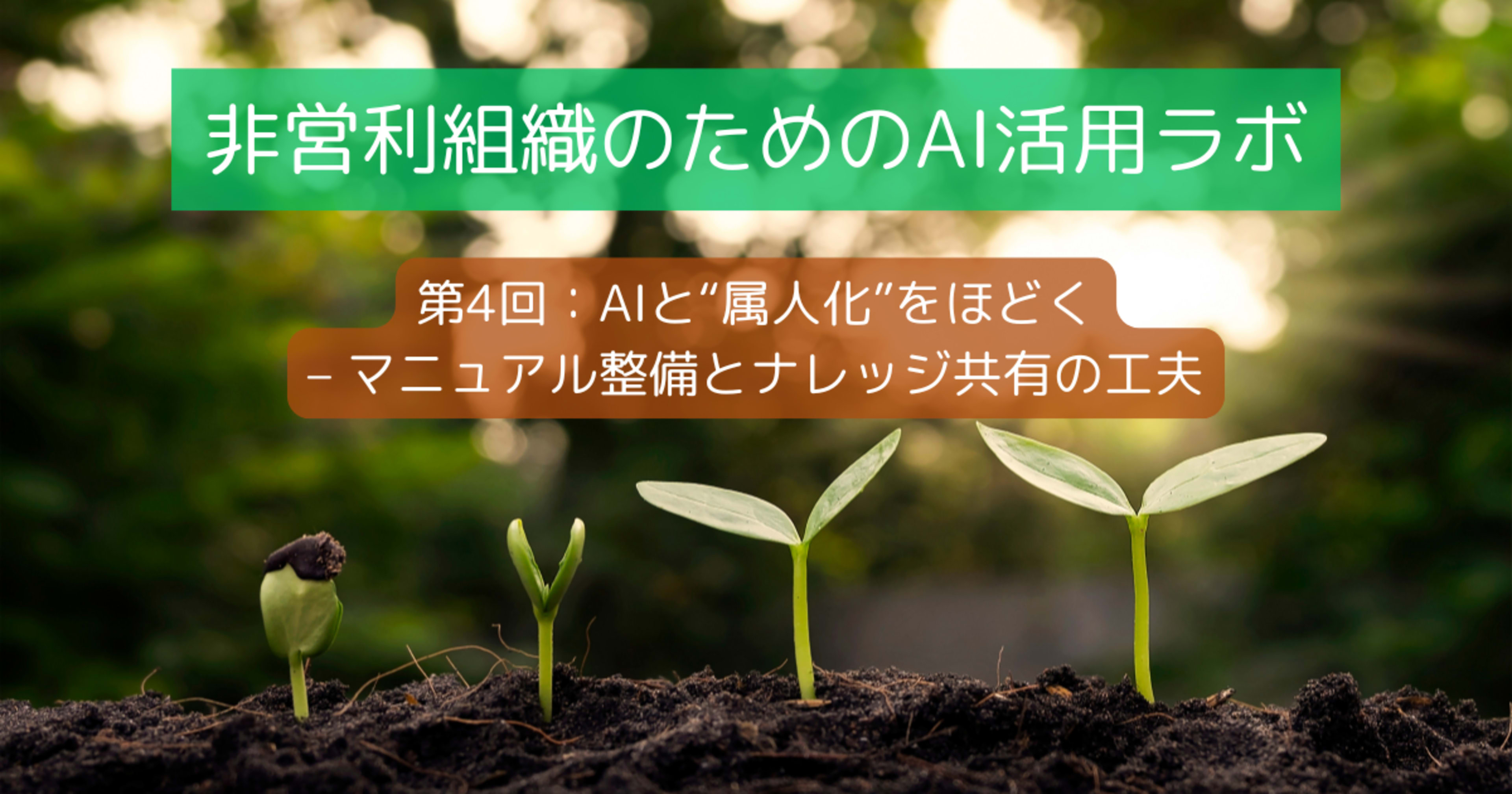
非営利組織のためのAI活用ラボ - 第4回:AIと“属人化”をほどく – マニュアル整備とナレッジ共有の工夫
はじめに:「属人化」は現実。でも、不安定さは減らしたい
非営利組織では、業務が一人の担当者に依存する“属人化”はごく自然な現象です。
少人数・低コストで運営されている以上、「○○さんにしかできない仕事」が生まれるのは当然。しかしそれが引き継ぎや継続性の妨げになってしまうことも多く、組織の成長や持続可能性にとっては大きなリスクになり得ます。
そこで今回は、属人化を完全に否定するのではなく、「安心して頼れる状態」をつくるために生成AIをどう活用できるかをテーマにお話しします。
属人化を“言語化”でほぐす – AIが活躍する場面
属人化の根本的な課題は、「暗黙知のままになっていることが多い」 という点です。
例えば、「○○さんがいたらすぐにできるけど、手順を誰も知らない」といった状態は、その知識が言語化・構造化されていないことが原因です。
ここで生成AIが役に立ちます。
ChatGPTやClaudeに対して、
- 「この作業ってどう進めていたんだっけ?」
- 「Slackにあるやりとりからマニュアルを作って」
- 「この手順を初めての人でも分かるように書き直して」
といったプロンプトを投げることで、暗黙知を明文化するプロセスをサポートしてくれます。
Obsidian + NotebookLM:会話からナレッジベースを育てる
筆者は、以下のような構成でナレッジを蓄積・活用しています。
Obsidian:知識の蓄積と構造化
- ローカル環境で動作し、Markdownで記述可能
- ノート同士をリンクでつなぎ、マインドマップ的に整理
- Obsidianで記録したノートは、GitHubのリポジトリに自動的に同期・保存することで、外部連携や履歴管理も容易に
NotebookLM:自然言語で知識を引き出す
- GitHubリポジトリ内のObsidianノートを元に、NotebookLMに読み込ませる
- AIが「中の人のように」質問に答えてくれる
- 例:「○○事業の助成金申請の手順って?」「過去にやった広報の内容は?」など
このようにして、知識の蓄積・共有・検索が循環する仕組みを構築できます。
まずは“やりとり”を記録するところから
いきなり立派なマニュアルを作ろうとすると大変です。
まずはSlackのやりとりや議事録といった、すでにある言語情報を記録し、それをAIで整形することから始めましょう。
例
- Slackの会話:「どうやって申請したっけ?」→「前回は○○で…」
- そのやりとりをObsidianに記録(Markdownで書き留める)
- GitHubリポジトリに自動同期
- NotebookLMに連携して、自然言語で再活用できるようにする
このように、“会話”からマニュアルは生まれます。
まとめ:「頼れる人」を、安心して頼れる仕組みに
属人化をゼロにすることが目的ではありません。
人が人に頼ることは、組織にとってむしろ健全です。
しかし、“○○さんがいないと分からない”ではなく、
“○○さんの知識がここにある”という状態にしておくだけで、組織の不安定さは大きく減らせます。
生成AIとObsidian、GitHub、NotebookLMなどのツールをうまく活用することで、
非営利組織でも無理なく、属人化を“知識の形で引き継ぐ”ことが可能になります。
次回予告:AIは“IT人材の代わり”になれるのか?
第5回では、非営利組織で特に不足しがちなIT人材の代替や補完について取り上げます。
「この作業、できればエンジニアに相談したいけど、うちにはいない…」
そんな状況で、生成AIはどこまで頼りになるのか?
AIをIT人材の“並走者”として使う現実的な方法を探っていきます。










