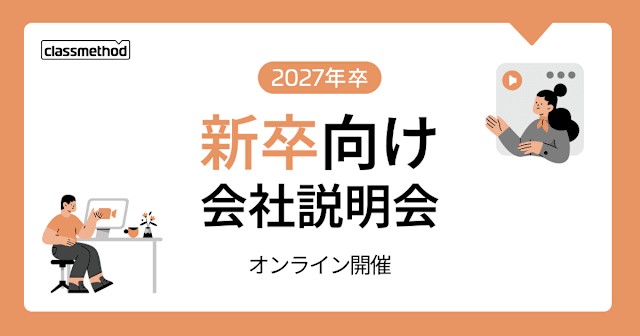![[レポート]AI時代にデータエンジニア/アナリストが生き残るためにすべきことは? #pNdatasummit #DataEngineeringStudy](https://devio2024-media.developers.io/image/upload/f_auto,q_auto,w_3840/v1764119951/user-gen-eyecatch/j4cafuyrgahloylmfskk.jpg)
[レポート]AI時代にデータエンジニア/アナリストが生き残るためにすべきことは? #pNdatasummit #DataEngineeringStudy
2025.11.26
さがらです。
2025年11月26日に、primeNumber社が主催する「primeNumber DATA SUMMIT 2025」が開催されました。
本記事はセッション「AI時代にデータエンジニア・アナリストが生き残るためにすべきことは?」のレポートブログとなります。
登壇者
- 松井 太郎 氏
- CCCMKホールディングス株式会社 テクノロジー戦略本部 本部長
- 大木 基至 氏
- Ubie株式会社 アナリティクスエンジニア
- 阿部 直之 氏
- 株式会社リクルート データ推進室データテクノロジーユニット Vice President
- 宮﨑 一輝 氏
- stable株式会社 代表取締役
自己紹介
- 松井氏
- ここ10年くらいはデータエンジニア、Data Superheroも担っている
- 大木氏
- 新卒からずっとデータ関係、基盤開発からデータサイエンティストを担当し、2021年にUbieに入社。現在は経営企画にも携わっている
- 阿部氏
- リクルートでは各事業会社に分かれているが、事業を横断した取り組みを行っている。業務プロセスの改善やDXなど、幅広く担当している
- 宮崎氏
- データエンジニア系の支援会社の代表。クライアントはベンチャーやスタートアップの企業が多い
Q1:AIが進化してきた結果、現在の仕事がどう変化したか?(直近1年くらいで)
- 松井氏
- 自分の領域が広がった。エンジニアリングがとてもやりやすくなり、効率も上がったと思う
- 変わらなかった点で言うと、人間とのコミュニケーションの重要性が高まっている。課題は何で、自分たちは何をすべきか、を問われているのは変わらない
- 大木氏
- アウトプットの生産量が大きく変わった。データ基盤の整備をするスピードが大きく向上し、プルリクエスト数も増えた
- 会社の中では、経営企画にも携わるようになって領域が広がった。元々データに基づいた経営の意思決定を支援していたが、より経営企画に関わるようになった
- 変わらなかった仕事としては、データ整備の仕事自体は変わらなかった。より具体的には、自分以外のメンバーがデータ整備をしていく「民主化」が進んだ。メタデータの整備、Notionのドキュメント整備などを自然とデータエンジニア以外が関心を持つようになった
- 阿部氏
- インプットとアウトプットのスピードが上がった。具体的には業務プロセスを理解するために図書館で本を借りることを行っていたが、AIに聞くことでスピードアップした
- 一方で変わらなかったこととして、課題を整理して紐づけるような業務。課題を整理してからの取り組みスピードは上がっている
Q2:「賞味期限の短いスキル」と「長く価値を発揮し続けるスキル」は何か
- 松井氏
- 「学ぶスキル」をAIを用いて磨いていくことが大事と考える
- データベースのチューニングなど10年やっていたが、これはAIや製品によって最適化されていくとも思う
- 抽象化されたものがAIに取って代わるかどうかを考えながら、どういうスキルを身につけていくのかを考えるのが良いと思う
- スキルをいかに速く学んで核を掴んで、次の学びのサイクルに活かしていくことが大事だと思う
- 今の自分のスキルを後輩に引き継ぐときに、何を優先するか。自分のスキルを棚卸しして、今後の技術動向も考えて、優先順位を決めていくのが良いと思う
- 大木氏
- この時代に生きていくのは大変だな…というのは正直な所
- 元々SQLを書くのが大好きで社内でも一番書いているが、これがAIに代替されていくのは悲しい
- 一方で、AIが出した結果を最後仕上げて入れるところは人間の仕事である
- 今の世の中にどういう技術があって、今の自社には何が合うのか、抽象から具体に落とし込んでいくようなスキルが必要だと思う
- AIによってPDCAのサイクルがとても高速化している。このサイクルを回していくことも大事と思う
- 言語化しづらいスキルをドキュメント化して引き継いでいくことも重要だと思う
- 阿部氏
- 賞味期限が短いとはどういうことか考えると、外部要因的な影響によって使われなくなる技術が生まれたり、新しい技術が汎用化していくスピードが以前よりも上がっていくことだと思う
- ただ、技術の変化もいきなりばつんと切り替わることはなくて、ちょっとした変化を追っていければ、スキルとしていきなり陳腐化することはないと思う
- 「How」は世の中の流れによって変わってしまうため、価値が下がりやすい印象がある。すぐに違う「How」を追従できるようなスキルがあればよいのでは。具体的には、あるBIツールの使い方ではなく、BI全体、データマネジメント全体、などより抽象度高いスキルがあれば長く価値を発揮し続けると思う。スキルの抽象化と具体化の往復が重要だと思う
- 長く続くスキルを身につけるためには、その各論を抑えるのが大事だと思う
若手に対して、具体ではなく抽象方面のスキルを上げるにはどうするか?
- 阿部氏
- 言われたことをやるだけでなく、やったことで何が起きたか、どう繋がっているか、ということを意識しながら業務をすることが大事だと思う
Q3:AIでより早く価値を発揮できるようになったら何をしたいか
- 松井氏
- AIで効率化する方面よりも、品質を上げていくのが大事だと思う。プルリクエストがたくさん上がっても、レビュアーが辛くなるだけ
- アーキテクチャ選定や会社の歴史など、ドキュメントを残して、情報の断絶を起こさないこと。自分自身がいっぱいアウトプットすることで組織自体の力を上げていくイメージ
- 仮に自分がいなくなっても、誰でも意思決定や業務をできるようにしたい(松井ボットも作ったが、まだ評判は良くないらしい…)
- 大木氏
- 会社の中でボトルネックになっているとこを倒しにいくことをしたい
- レビューがボトルネックになったら、レビューボットを開発する。レビューボットを開発したら人間の意思決定がボトルネックになるため、こうなると組織マネジメントなどの話になっていく
- もう一つ違う観点で言うと、n=1のユーザーのリアルな声を取りに行くこともやりたい。AIは平均的な回答を得られると思うが、本日のようなイベントなどにも行くことで、AIでは得られない回答を得ていきたい
- 阿部氏
- 新しいことに踏み込むことが圧倒的に楽になっている
- できることが増えていくことで、その内容がシナジーを生みだすタイミングがあると思う。そういうチャレンジをしていきたい
最後に
- 松井氏
- 最近、エンジニアリングという言葉が凄い良いなと感じている
- データエンジニアというとデータで何かしら改善するというイメージだが、AIによって領域がどんどん広がっていくと、業務プロセスや事業そのものを改善・エンジニアリングしていくことになっていくと思う
- データエンジニアが生き残るかというと、できることが広がっていくためデータエンジニアという狭い領域の職種はなくなっていくが、広い意味でのエンジニアは今後もなくならない
- 大木氏
- 「明日から自分でコードを書かない」のように取り決めて、自分の日々の業務の中で何をAIに置き換えていくか、業務の棚卸しをするのがよいと思う
- 阿部氏
- 「技術を使って課題を解決する」ということは今後も変わらない。事業をちゃんと見ながら、今までと変わらず取り組んでいき、AIも取り入れることが大事と考える
質疑応答(Ask the Speakerセッションにて)
Q. ある程度スキルを身に着けたエンジニアはAIの出力をレビューする能力が備わっていますが、育成の観点だと書く力が育っていないとレビューするのは難しいかなと思いますが、どう臨めばよいでしょうか?
- 松井氏
- 自分も書けない言語があるため、AIにコードを出力してもらった後、またAIにレビューをしてもらい「何がだめなのか」を指摘してもらうことで、学びに活かしている
- 大木氏
- 最終的にその方が作ったものをシニアの方にレビューしてもらうプロセスは外せないと思う
- SQLを書くにしても、コードが汚くてもサブクエリが整っていても、結果としては同じとなる。「なぜこのクエリはだめなのか」をちゃんとレビューをしていくプロセスが大事
- 阿部氏
- 育成の対象をよりシャープにしたほうがよいと思っている
- コードを書く力を高める、プロダクトとしての質を高める、など、何のスキルをつけるかという目標設定をよりシャープにすべきだと思う
- 宮崎氏
- 基本的には書く能力が一定ないと評価はできないと思う
- 今の学生を見ていると、コードは書けないけどAIでなんとかなっているという方もいる印象がある。本番環境にプロダクトとして出すためにはコードを理解しておかないといけないため、書く力が必要
Q. AIを活用した学びは今後さらに増えていくと思いますが、AIを使った学習での工夫もしくは注意していることはありますか?
- 松井氏
- 勉強の仕方というよりは、自分の考えや仮説をAIにぶつけて、指摘をもらいながらブラッシュアップしていくのが良いと思う
- AIは「能力拡張」と考えて使っていくのがよいと思う
- 阿部氏
- AIのいいところは、「何を聞いても恥ずかしくない」こと。上司や同僚に聞くと「そんなこともわからないの」となる強さがあるが、AIの場合はない
- そのうえで、自分の仮説をAIに与えながらブラッシュアップしていくことが重要
- また、AIが引用した一次ソースを見に行くことも大事だと思う
- どんどん試していくことが重要、絶対にAIは怒らない(一方で批判的に回答して、というと凄い辛辣な回答が来る場合もあります)
Q. なんか速度感が変わっているだけでいままでとそんなに変わっているのだろうか?大きな変化はまだ先かなとも思っていたり
- 松井氏
- 逆だと思っていて、回転数がこれまでと全く違う。AIを使いこなす人と使いこなさない人で、差はどんどん広がると思う
- AIを使いこなすというよりは「言語化能力」が大事だと思う。自分がやりたいことはこれというコンテキストを言語化してAIに与えて、足りない点をAIに聞いていくことが重要
- 大木氏
- ボトルネックが移り変わっているだけで変わっていないように見えるかもしれないが、ある時ボトルネックが劇的に改善される瞬間がある
- 阿部氏
- AIが加速しているのは点の部分。組織含めて全体の流れをどう変えていくかまで俯瞰して取り組むのが大事
- 宮崎氏
- 変わっていないところで言うと、メタデータやコンテキスト、データモデリングが重要というのは全く変わっていない
- 一方で、メタデータを整備することの意義、などは明らかに変わった。AIが出る前は「めんどくさいけどやっておくか」みたいなものだと思ったが、「AIで使うからメタデータを入れてね」という意義になった
Q. 抽象化の学習の仕方でおすすめはありますか?
- 松井氏
- 抽象化の学習の仕方はないと思っている。何か1つをちゃんと学ぶことで、抽象化する基準ができるため、次の学習が効率化していく(ベテランエンジニアが別の言語でもすぐに使える例を交えながら)
- 抽象化というのは特別高度なことではない、今行っていることをちゃんと身に付けることが重要だと思う
- 大木氏
- 本質は「余白を作ること」だと思っている。業務をしていると、その業務に一直線になってしまう
- 例えばチームの中でまとまった時間を設けて、抽象化するための考える時間を作るアプローチも重要だと思う
- 自分でプロンプトを作るのではなく、AIにプロンプトを作ってもらうことも大事だと思う
- 阿部氏
- 今やっていることの先に何があるのか、目的を意識すること
- より具体の話をすると、Webアプリケーションのフレームワークを複数学んで、それぞれにどういうメリット・デメリットがあるか言語化する、のように近しいものを検証して比較していくことで、抽象化のスキルが上がっていくと思う
- 宮崎氏
- 抽象化って具体的なものを多面的に見に行くことだと思う
- 例として、一個のタスクを行う時には、「このタスクってどう進めるの?」「このタスクってやる意味あるの?」「代替案はないの?」など色々な観点でAIと壁打ちすることが重要だと思う
- AIに問う力を鍛えるには、AIにとにかく聞くことが大事
所感
本セッションを通じて強く感じたのは、AI時代における「エンジニアリングの本質回帰」です。登壇者の皆様が共通して仰っていたのは、AIはあくまで「How(手段)」の高速化や効率化を担うものであり、人間が担うべきは「Why(目的)」や「What(課題設定・抽象化)」であるという点でした。
コードを書くスピードが劇的に上がり、技術の陳腐化も速い現代において、特定のツールや言語に固執するのではなく、物事を抽象化して捉える力、そしてそれを他者(AI含む)に伝える言語化能力こそが、「生き残る」ための必須スキルなのだと再認識しました。
「AIに代替されることを恐れるのではなく、AIを使ってどう自分の価値や組織の品質を高めるか」というポジティブなマインドセットに切り替えて、日々の業務に取り組みたいですね!