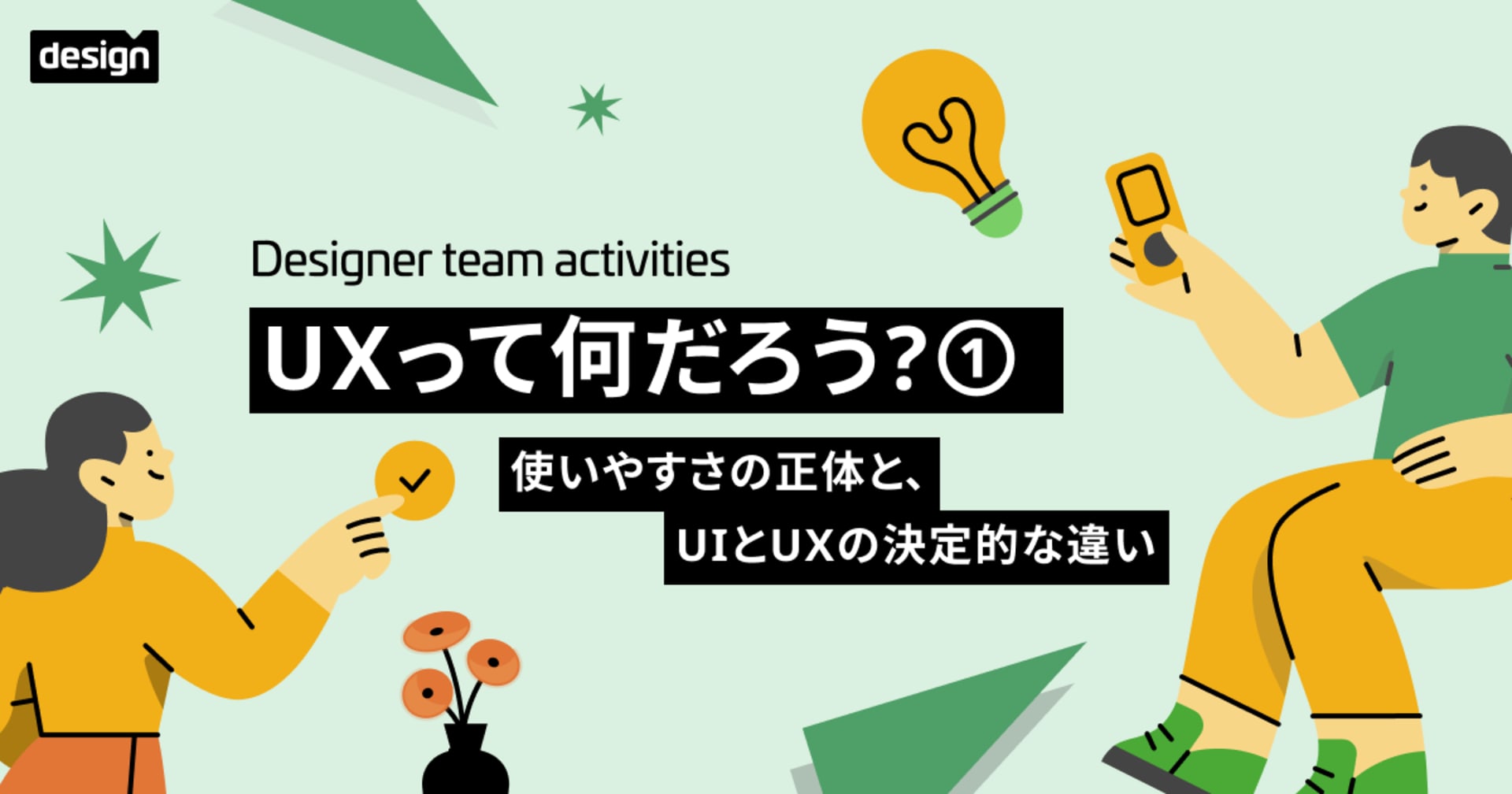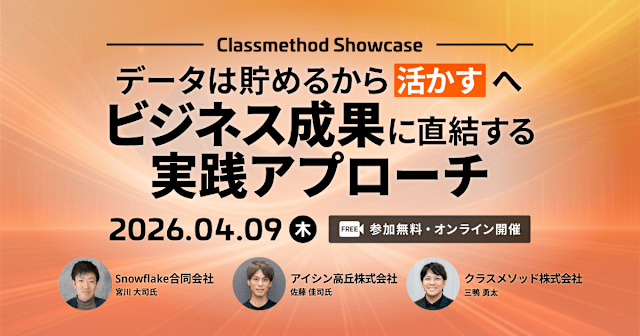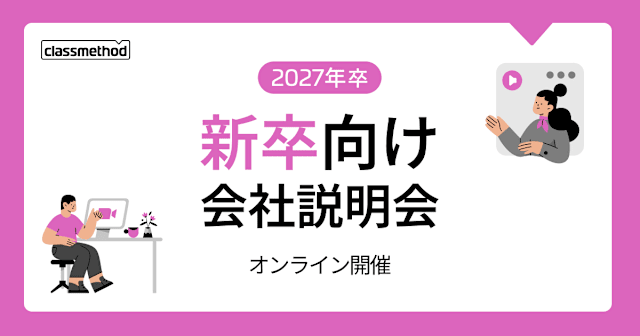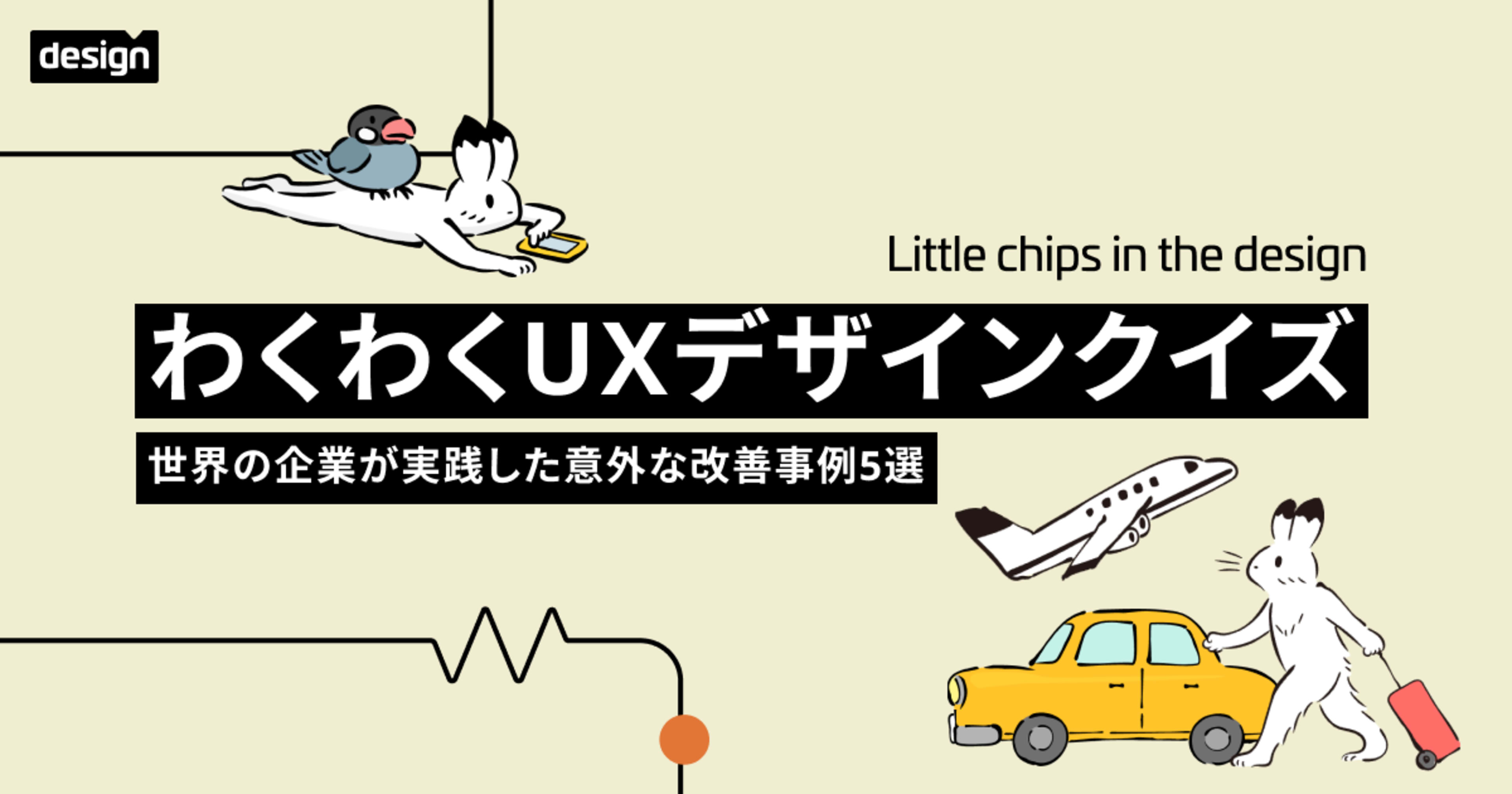
わくわくUXデザインクイズ〜世界の企業が実践した意外な改善事例5選〜
はじめに
「ユーザー体験(UX)デザイン」と聞いて、何を思い浮かべますか?
使いやすいボタン、綺麗な画面、スムーズな操作………どれも正解ですが、UXデザインはとても幅広いものです。そこで、今回は、世界の有名企業が実際に行ったUX改善事例を、クイズ形式で紹介します。
全5問。ぜひ、UXデザインの考え方に触れてみてください。
(このクイズは製造ビジネス・テクノロジー部でのLT会で実施された内容であるため、製造現場での応用ポイントも記載されています)
第1問

A:荷物処理の進捗をリアルタイムで表示し、 「あと◯分」と分かるようにした
B:待合所に大型スクリーンを設置し、地元の観光情報や娯楽コンテンツを流した
C:到着ゲートから荷物受取所までの通路を延長し、空港内を歩く時間を増やした
D:荷物が出てくる順番を予測表示し、「あなたの荷物は◯番目」と表示した
回答と解説
正解
C:到着ゲートから荷物受取所までの通路を延長し、空港内を歩く時間を増やした
解説
到着ゲートを遠くに変更し、荷物受取所まで歩く時間を約8分に延ばしました。
待つ時間(7分)を歩く時間(約6分またはそれ以上)に置き換えることで、歩いている間に荷物が到着し、受取所での待ち時間がゼロになりました。実際の時間はほぼ同じ時間。
学び
人間は「何もせず待つ」ことに強いストレスを感じます。
同じ時間でも、「何かをしている」と感じると、時間が早く感じられます。
「実際の時間 ≠ 体感時間」
UXデザインでは、「どう感じるか」が重要です。
製造現場への応用
機械の処理待ち時間中、ただ待たせるのではなく「次の準備作業をしてもらう」などのアクションをフローに取り入れることにより同じ時間でも、ストレスが減り、生産性も上がります。
参考資料
第2問

A:サーバー負荷を減らすため
B:ユーザーの健康への配慮
C:インフルエンサーの影響力を下げるため
D:広告効果を高めるため
回答と解説
正解
B:ユーザーの健康への配慮
解説
Instagramは「いいね」の数を他人から見えなくしました。「人々が『いいね』の数ではなく、コンテンツそのものに集中できるように」。
インフルエンサーからの反発、滞在時間減少の可能性、広告効果低下の懸念、といった短期的リスクが懸念されましたが、それでも実施しました。
その後、ユーザーの意見が二極化。現在は「見る/見ない」を自分で選択できるUIになっています。
学び
エンゲージメント < ユーザーの幸福度
短期的な損失より、長期的な信頼を優先する。また一つの正解はない。だから「選択権を与える」という解決策もある。
製造現場への応用
作業実績の「見える化」も同じです。
❌ 「あなたは平均より遅い」 → 他人との比較、プレッシャー
⭕ 「昨日より◯分速くなりました」 → 自分との比較、モチベーション向上
他人と比較させない設計が、長期的なモチベーションを生みます。
参考資料
第3問

A:ボタンの配置が悪かった(トヨタはもっと押しやすい場所に設置)
B:報奨金制度がなかった(トヨタは押すとボーナスが出る)
C:押した人を褒める文化がなかった(トヨタは問題発見を評価する)
D:作業員への教育が不足していた(トヨタはもっと研修をしている)
回答と解説
正解
C:押した人を褒める文化がなかった(トヨタは問題発見を評価する)
解説
A工場は、トヨタのアンドンシステムを真似しました。緊急停止ボタンを設置し、マニュアルも整備し、説明会も実施。でも、ほとんど使われませんでした。ここでできていなかったこととして「文化」が考えられます。
トヨタでは、
- ボタンを押すこと = 問題の発見
- ラインを止めること = 勇気ある行動
- 問題を報告すること = 高く評価される
として、作業員は安心して報告できる文化があります。
学び
良いUIを作るだけでは不十分です。
「使いやすい」だけでなく、「使う勇気が出る」環境が必要です。
システムデザイン × 文化デザイン = UX
製造現場への応用
- エラー報告ボタン
- 改善提案フォーム
- ヘルプ機能
使われない理由は、UIじゃなくて文化かもしれません。
❌ 「報告したら怒られる」
⭕ 「報告した人を評価する」
仕組みと文化、両方が必要です。
参考資料
第4問

A:会員の月額料金を3ヶ月間半額にします
B:医療従事者に6ヶ月無料提供します
C:学生向けプランを1年間無料にします
D:1年以上視聴していない方の契約を、自動的にキャンセルします
回答と解説
正解
D:1年以上視聴していない方の契約を、自動的にキャンセルします
解説
COVID-19パンデミックのさなか、Netflixは「自分から収益を減らす」選択をしました。
対象は全体の0.5%未満(数十万人)。「1年以上視聴していない方に、自動解約を通知する」
普通の企業なら、黙って課金し続けます。でもNetflixは、わざわざ「使ってないですよね?」と連絡しました。この施策により短期的には収益減。でも長期的には、ユーザーの信頼を獲得しました。
同時期、Netflixの有料会員数は過去最高の1,577万人増加し、累計1億8,300万人になりました。
学び
UXデザインは「使いやすさ」だけじゃなく「誠実さ」「信頼」もユーザー体験の一部です。「短期的な損失 < 長期的な信頼」0.5%を切り捨てることで、残り99.5%の信頼を得た。これはダークパターン(わざと解約しにくくする)の真逆です。
製造現場への応用
目先の効率より、長期的な使いやすさを考える。
❌ 「とりあえず動けばいい」で作る
⭕ 「5年後も使いやすい」を考えて作る
❌ エラーを隠して見なかったことに
⭕ エラーを報告しやすい仕組み
誠実な設計が、長期的な信頼を生みます。
参考資料
第5問

A:デザイナーチームが3案に絞り、役員会議で投票に持ち込んだ
B:主要ユーザー1万人にアンケートを実施し、最多得票の色を採用
C:競合5社(Yahoo, Microsoft, Amazon等)の色を分析し、最適解を導出した
D:複数パターンでA/Bテストを実施し、クリック率が最も高い色を採用した
回答と解説
正解
D:複数パターンでA/Bテストを実施し、クリック率が最も高い色を採用した
解説
Googleは徹底的にデータ主義を貫きました。41種類の微妙に異なる青を用意し、数百万人のユーザーでA/Bテストを実施。最もクリック率が高い青を発見しました。
しかし、代償もありました。この出来事がきっかけで、デザインディレクターのDouglas Bowmanが退職。彼の退職ブログでは「2つの青のどちらが良いか決められず、41色でテストする。デザイナーの専門性や直感が尊重されない環境だった」とあったそうです。データで最適解は見つかったものの、優秀なデザイナーを失ってしまいました。
学び
データは重要。でもデータだけでは不十分。Googleはこの反省を活かし、現在は「データ × デザイン」の両立を重視しています。
データ(客観的な検証)× デザイン(専門的な直感)= 良いUX
製造現場への応用
❌ 「データで決めろ」と言われ、現場の経験が無視される
❌ 「効率だけ」を追求し、作業者の意見を聞かない
❌ 数字は良くなったけど、ベテランが辞めていく
⭕ データで検証する
⭕ でも現場の「勘」も尊重する
⭕ 両方のバランスが最高の結果を生む
現場への丁寧なヒアリングを大切にしながら、データとの掛け合わせが良い製品を生む、といえるかもしれません。
参考資料
おわりに
以上有名な5つの事例を紹介しました。
どの事例にも共通していたのは、「ユーザーの視点に立って考える」ことでした。
(UXとは、その製品・サービス・仕組みに関わる全ての人(=従業員)の体験(EX)も含みます)。
- 実際の時間ではなく、どう感じるか。(空港の体感時間)
- 機能の有無だけでなく、使いやすいか、使えるか。(トヨタの文化)
- 短期的な利益ではなく、信頼されるか。(Netflixの誠実さ)
- データだけでなく、専門的な経験や直感が尊重されるか。(Googleの従業員体験)
ユーザーの視点に立って、体験を設計することが、サービスの価値を体現すると考えます。
「ここ、使いにくいな」と感じたときには、ぜひお近くのデザイナーに声をかけてください。一緒に、より良い体験を作りましょう。