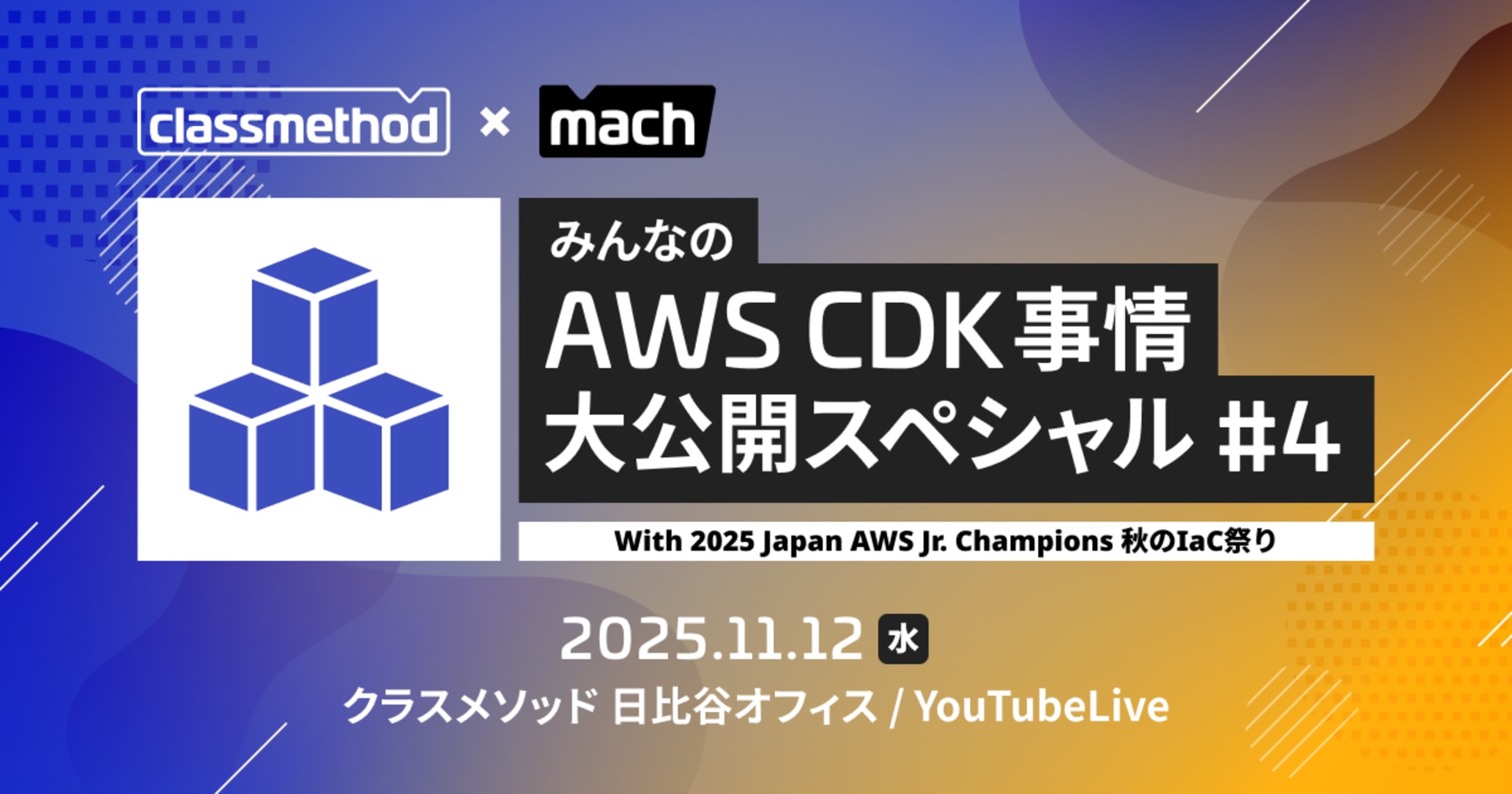![[レポート]高可用性/セキュリティを実現する、金融機関/FintechにおけるAWS活用の実際と構成パターン #AWSSummit](https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2016/06/aws-summit-tokyo-2016.png)
[レポート]高可用性/セキュリティを実現する、金融機関/FintechにおけるAWS活用の実際と構成パターン #AWSSummit
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
こんにちは、城内です。
今回は、 AWS Summit Tokyo 2016の6/2(木) P3C1620セッションのレポートです。
セッション情報
- セッション名:高可用性 / セキュリティを実現する、金融機関 / Fintech における AWS 活用の実際と構成パターン
- ホストスピーカー:瀧澤 与一氏(アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 技術本部 エンタープライズソリューション部 部長/シニアソリューションアーキテクト)
- ゲストスピーカー:藤井 達人氏(株式会社三菱東京UFJ銀行 デジタルイノベーション推進部 シニアアナリスト)
- ゲストスピーカー:宮本 昌明氏(株式会社ジャパンネット銀行 IT本部 開発二部 副部長/基盤開発第一グループ長)
- ゲストスピーカー:加藤 智氏(クォンツ・リサーチ株式会社 アプリケーション開発部 上級アプリケーションエンジニア )
セッション内容
概要
グローバルでの金融機関におけるAWSの利用が広がっている。
グローバルの事例
- Capital One
- NASDAQ ...など
国内の事例
- ソニー銀行
- すでにAWSを利用している
- 今後も順次システムを移行していくことが決定していり
イノベージョン
- 加速する機能拡張・改善のスピード
- セキュリティに対するサービスも増えている
- AWSの拠点が広がっている(AZ:33、リージョン:12、エッジロケーション:54)
- サービスの数も70以上
AWSを利用することで以下のようなメリットを得られる。
- AWSを利用すると自組織のDCを拡張できる
- 閉域網を構成することも可能
- リソースの増減に対して柔軟性がある
高可用性
障害発生時の対応・体制
- お客様の運用管理システム
- Service Health Dashboard
- AWSサポート、SA
AutoScaling、自動化
- 性能不足による障害に自動で対応できる
AWSを利用したシステムの特徴
- Design for Failure
- 伸縮自在性を実装
- 疎結合なシステムを実現可能
顧客事例
Quants Research
リアルタイム時価情報サービスプラットフォーム
- 自社でファシリティを持っていない
- FISCに準拠するパブリッククラウドとしてAWSを選択
- リアルタイム性と高可用性を実現
- 完全二重化構成(DX、VPCのMulti-AZ)
- トラフィック量が変動する(9時~10時)
- AutoScalingで対応、必要な時間帯のみ必要なリソースを確保
QRサーチコンシェルジュ
- Elastic Beanstalkを利用
セキュリティ
FISCの安全対策基準(2015年6月リリース)、システム監査指針(2016年5月リリース)にクラウドに関する項目が追加された。
クラウド利用に関する有識者検討会にAWSも参加。
事業者の選定
- 外部の監査人の審査
- 取得した認定の公開
データの所在
- Tokyoリージョン
データの暗号化
- クラウドHSM、KMSなど
- データの所有権はお客様、AWSはデータには触れない
立ち入り監査
- AWSにおけるデータセンターの場所は公開していないが、第三者監査にて代替可能
責任共有モデルにて、責任範囲を明確化している(サーバにログインすることはない)。
顧客事例
ジャパンネット銀行
OAシステムをAWSに全面移行
- 基幹システムはオンプレ
- DXとVPNを利用
- Multi-AZを利用
- システムのクリティカル度によってアクティブ/アクティブか、アクティブ/スタンバイを使い分け
- Panzura(キャッシュ製品)+S3で、EC2+EBSのNFSを代用
- 通常のNFSだとCIFSの通信が多く、レスポンスが悪かった
FISCの第8版でAWSを評価した結果、適合していると判断。
クラウド化の流れはとまらない
基幹系もクラウドへの移行を検討している。
FinTech
顧客事例
三菱東京UFJ銀行
2つの大きな波
- モバイルの普及
- 新規参入の増加
競争のスピードが上がってきているため、自社だけで対応するには難しい。
FinTechとは
- キーテクノロジー
- ビッグデータ、AI、IoTなど
- スタートアップ企業
- 既存銀行ではカバーできていない顧客の不満を解消するようなサービスを展開
ビッグデータとAIはキラーコンテンツ
- オンプレで大量のデータを保持するのには限界がある
- AIはクラウドのAPI公開という形式が増えている
感想
FinTechというキーワードは聞いたことあるくらいのレベルの私でしたので、金融業界のITに対する意識の高さにはとても驚きました。
新しいテクノロジーを使用して、どんどん新しいサービスを生み出そうとしているんだなと感じました。
安定志向の堅いイメージだった金融系のイメージが、ガラリと変わったセッションでした。