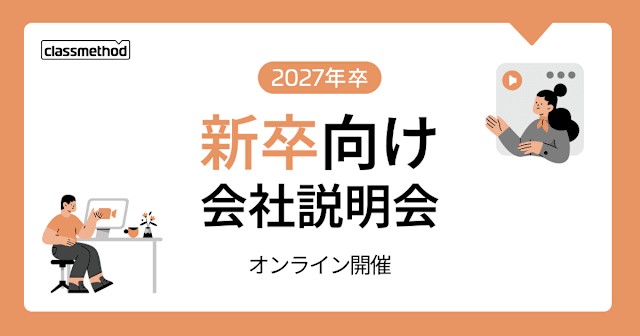組織の活力を生み出す感謝のアプローチ
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
こんばんは。僕です。
はじめに
職場でのさりげない「ありがとう」に、どんな可能性があるでしょうか。何気ない一言の積み重ねが、チームの結束を強くしたり、仕事への手応えを感じるきっかけになったりすることは多々あります。
感謝のやり取りがうまく機能している職場では、次のようなことが起こりやすくなります。
- 人間関係が円滑になる お互いの存在や貢献を「そんなの当たり前」と思わなくなる
- 前向きな気持ちが生まれる 自分の働きが誰かの役に立っていると実感できる
- 良い習慣が根付く 周囲の行動に目を向け、それを尊重する風土ができる
特別なイベントを設けたり、新しい制度を導入したりしなくても、日常の中で自然と生まれる言葉によって、仕事のしやすさが作られていくということです。本記事では、感謝がどのように組織の活力につながるのかを考えてみます。
信頼関係を深めるやり取り
どんなにスキルの高い人が集まっても、チームとしての信頼関係がなければ、うまく連携するのは難しくなります。信頼を築くには、相手の言動を認めることが大切ですが、業務に追われるとそれを見落としてしまうこともあります。
日々のやり取りの中で、相手の働きに「気づいたこと」を伝えるだけで、お互いの距離感は変わります。
- 「〇〇さんがいてくれると、安心して進められますね」
- 「いつもさりげなくフォローしてくれてるの、ありがたいです」
こうした言葉があると、自分の行動が認められていることが伝わり、信頼が積み重なっていきます。「相手を評価しなければ」と意識するよりも、「何か受け取ったことがあったら、そのまま言葉にする」くらいの感覚で、自然に伝えるのがちょうどいいバランスかもしれません。
自信につながる言葉
何か新しいことに挑戦するとき、周囲の反応があるかどうかで、その後の行動が大きく変わることがあります。特に、手応えがつかめないまま仕事を進めているときに、小さなフィードバックがあると、次の一歩を踏み出しやすくなります。
- 「〇〇さんの視点、すごく助かります。やっぱりいいところに気づきますね」
- 「さっきの〇〇、すごく良かったです。次もお願いしたいくらいです」
意識してポジティブな言葉をかけるというよりも、良いと感じたことをそのまま伝えるだけでも十分です。それが続くことで、チーム内で自然と「誰かの働きを見て、言葉にする」という流れが生まれ、自発的な行動につながりやすくなります。
自覚を促し、行動を引き出す
自分の何気ない行動が、実は組織の成長やチームの雰囲気づくりにとって重要なものだった――そんな経験は意外と多いものです。ところが、本人にその自覚がないと、意識的に続けることなく、偶然の出来事として流れてしまいがちです。
例えば、普段から自然と周囲をサポートする人や、知識を惜しみなく共有する人がいるとします。その人自身は「自分が特別なことをしているわけではない」と思っているかもしれません。ですが、周囲の人々がそれを認識し、適切に言葉で伝えることで、本人の意識が変化することがあります。
- 「〇〇さんがいつもやってくれてること、けっこうみんな助かってるみたいですよ」
- 「今のすごくよかったです。自然にやってたんですか?」
こうしたやり取りがあると、「そんなに役に立てているなら、今後もやってみよう」と、ポジティブな気持ちにつながります。言葉をかける側も、「続けてくれたら嬉しい」ではなく、「すでに価値を生んでいる」と伝えることで、より自然な形で相手の行動を尊重する雰囲気を作れます。
特に、リーダーだけでなく、メンバー同士でもこうした声が交わされると、組織の雰囲気が前向きなものになりやすくなります。
おわりに
感謝を伝えることは、誰かを評価したり、褒めたりすることとは少し違います。ふとした瞬間に「この人の働きがありがたい」と思ったら、そのままそれを伝えるだけです。そうしたやり取りが積み重なることで、周りの雰囲気は少しずつ変わっていきます。
職場でのコミュニケーションは、何かを「こうしよう」と決めるよりも、まず自然に交わされるものから広がることが多いものです。感謝のやり取りも、意識して取り組むというより、「伝えやすくなる」環境を作ることで、無理なく根付いていくのではないでしょうか。