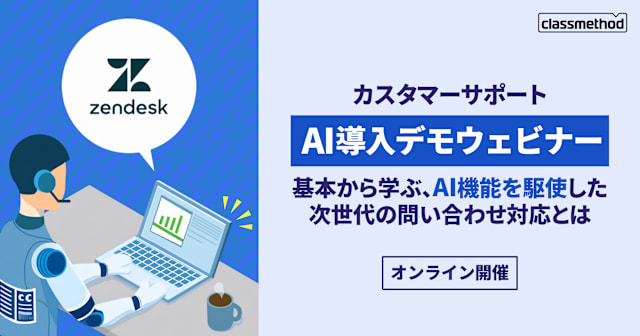聞く?調べる?迷わない情報収集の3つの判断基準
こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
仕事を進めるにあたって、様々な情報が必要になります。自分がもともと持っている情報だけで完結するとは限りません。そのため、仕事において必要な情報を調べることや人から聞くことが必要になります。
この記事では、調べる情報と聞く情報についてまとめます。
調べる情報と聞く情報
情報を自分で調べるか、人から聞くかの判断は、大きく3つに分けられます。
- 自分で調べるのが好ましい
- 自分で調べることもできるが聞くと効率がいい
- 聞かないと分からないため、聞くことが必須
1. 自分で調べるのが好ましい
自分で調べるのが好ましい情報には、公開情報やマニュアル、過去の資料、社内ナレッジベースなどがあります。
調べれは発見可能で、調べるコストも小さい場合は自分で調べるのが最適です。
- 例1 : 社内システムの使い方
- 例2 : 業界・技術用語
- 例3 : 過去に実施された施策の記録
2. 自分で調べることもできるが聞くと効率がいい
自分で調べることもできるが聞くと効率がいい情報は、調べれば分かるが、情報が点在していたり、量が多かったりして、調べるのに時間がかかるようなものです。また、調べるためにも前提知識や理解が必要になる情報も同様です。
推奨の書籍やページを教えてもらったり、調べるための要点を事前に教えてもらうなどすると、調査や理解に必要な時間を大きく短縮できます。
- 例1 : 社内のある業務プロセスの全体像
- 例2 : 特定プロジェクトの背景と関係者
- 例3 : 自分にとって未経験の領域の全体像を理解するための調査
ただし、人に頼る場合は相手の時間も必要になるため、相手の負荷を減らせるように最低限は自分で調べておいたり、不明点を整理して伝えられるようにするなどの配慮を合わせてする必要があります。
3. 聞かないと分からないため、聞くことが必須
聞かないと分からないため、聞くことが必須の情報は、ドキュメント化されていない情報や文脈の依存性が強く、状況ごとに判断が異なるような情報です。
- 例1 : 今の部門の優先事項や判断基準
- 例2 : 関係者の温度感や今後の見通し
- 例3 : 明文化されていない慣習やカルチャー
判断は人によって異なる
情報を調べるか、人に聞くかを判断する場合、同じ情報でも人によって適した判断は異なります。判断はその人の知識・経験・所属・アクセス可能な情報源・関係性などに大きく左右されます。
分類が人によって異なる理由には、以下の5つがあります。
- 知識や経験の差
- 情報へのアクセス環境の違い
- 心理的安全性の違い
- リテラシーの違い
- 抽象度の高い情報の理解度の違い
1. 知識や経験の差
ベテランは「当然知っている」情報でも、新人にとっては全くの未知の場合があります。
2. 情報へのアクセス環境の違い
所属チームやロールによって、ナレッジベースやSlackチャンネルにアクセスできるかが異なります。
3. 心理的安全性の違い
聞きやすい関係性がある人は「聞けば早い」と思えるが、そうでない人には聞くこと自体がハードルになります。
4. リテラシーの違い
同じ社内Wikiを見ても、必要な情報に適切にたどり着ける人と、そうでない人がいます。
5. 抽象度の高い情報の理解度の違い
戦略や方針など一定の抽象度が高く、解釈の余地がある情報は調べれば適切に理解できる人もいれば、解釈が適切か確認するために質問をすることが必要な人もいます。一般的に戦略や方針については、担当する業務のレイヤーが高いほど理解しやすく、一般のメンバーになるほど補足が必要になります。
聞かないと分からない情報を調べればわかる情報にする
聞かないと分からない情報の一部は、文書化することで調べれば分かる情報にすることができます。
文書化すれば、その情報を扱う人は以降、人に聞かずとも調べるだけで情報を得られるため、調べる本人にとっての負荷が減りますし、質問によって時間を割かなければならない人も減り全体の効率化につながります。
聞く相手を選ぶ
- 自分で調べるのが好ましい
- 自分で調べることもできるが聞くと効率がいい
- 聞かないと分からないため、聞くことが必須
の3つの判断は、自分だけでは完結しません。
自分から見たら 3 の『聞くことが必須』の情報だったとしても、相手から見たら『自分で調べて当たり前』の情報に見えた場合、「それくらい自分で調べなさい」と叱られてしまうかもしれません。この場合、「確かにその情報は聞かないと分からないね」と理解し、丁寧に教えてくれる人を見つけるのがよいでしょう。技術的な知識の豊富さとスキルの高さと、誰が何を知っていてどの情報量を伝えるのが適切かを見極めるソフトスキルは一致するとは限りません。そのため、たとえば『スキルレベルが高いかソフトスキルのレベルが低い人』と『スキルレベルはほどほどだが理解は適切で、ソフトスキルのレベルが高い人』がいた場合、後者に確認するのがよりよい選択になります。こういった人の見極めや、快く応じてもらえるための関係構築も大切になります。