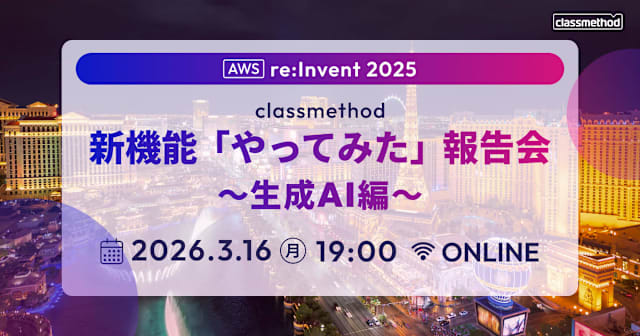【書評】「できるリーダーは、「これ」しかやらない 聞き方・話し方編」
こんにちは、こーへいです。
今回は人をテーマにした本を読んだので書評として気づき執筆させていただければと思います。
現状について
基本的に私は特定の部下は持っておらず、仕事によって他のエンジニアや営業と一緒に仕事をしたりすることが多いです。
(数ヶ月前に具体的な働き方を動画にて紹介させていただきましたので併せてこちらも見ていただけると嬉しいです)
そのため明示的にリーダーとして任命されることはないのですが、仕事によってはリーダー的な振る舞いが必要となる場面がございます。
そういった状況の中で、傾聴力をもっと鍛えることでより円滑に仕事が進むだろうなと思う場面が増えてきた。というのが本を読み、記事執筆のきっかけです。
各章概要
はじめに
本の入りです。ここでは対話の重要性が語られており、職場の問題のほとんどは対話不足によるものと指摘し、また対話は聞くことが肝要であることを述べています。聞くために重要となる質問力についても言及しています。
第1章 強いリーダーから「聞いてくれるリーダー」へ 理想の上司像は大きく変わった
まずはここ10年程でリーダーに期待される役割が「引っ張っていく強いリーダー」から「話をよく聞いてくれるリーダー」に変化しているということを述べています。ここは体感でも感じるところなんじゃないかなと思います。
とはいえ、ただただ優しさを見せるのでは「ぬるい職場」として離職の可能性が高まることにも触れられ、現代での人をまとめることの難しさ、そして解決策として対話力が重要であることが記載されています。
ちなみに理想のリーダー像の変化の背景の1つに、社会の発展により仕事の多様化・高度化が進んだことで部下の仕事をリーダーが経験していないということも増えた結果。というのがあるそうで新たな気づきでした。
第2章 誰からでも30分間「話を聞き続ける」テクニック
ここでは話を聞くことの重要性と、聞きたいことを引き出すためのテクニックが散りばめられています。
特に自分に刺さったのは「的当て質問」であり、何かを聞きたいときに推測で「これが原因?」と先回りしてしまうことに身に覚えがあったので意識しようとなりました。。。
また「情報は低い方に流れる」と記載があり良い表現だなぁと感じました。人からの情報には教えてくださいの姿勢は忘れないようにしたいですね。
第3章 対話をスムーズに進める「魔法の声がけ術」
この章についても個別の場面ごとのテクニックが散りばめられています。
特に「ツリークエスチョン」と言う、話したいこと(悩み)が曖昧な場合にとりあえず書き出してみて論点を絞って詳細を知ると言う手法は改めてその重要性を気づきました。
自分も何から解決したらいいのか分からなくなった場合は、絵を描くようにしていたのでこの辺りは自然と出来ていたんだなと自信に繋がりました。お客様の課題を明確化する際も意識していきたいです。
第4章 「やる気のない部下」をストレッチする質問
この章では特に、組織の目標が大きく変化した際にギャップを感じてしまうメンバーへの対応についての記載が印象深いです。
ここでもやはり個別に聞くことの重要性が訴えられてました。組織といっても構成要素は人なのでこの辺りは一朝一夕ではなく長期的にメンバーがギャップを徐々に埋められるように働きかけることが大切なのでしょう。
第5章 「要領の悪い部下」に聞く質問
読んでて「要領の悪い自分」に聞く質問にタイトルが置き換えられていました…
バッファを明示的に設ける、うまくいかなかった時のリスクマネジメントを考えるについては「はい…」と言うお気持ちしかないです。
第6章 部下の悩みの9割は「聞く」だけで解決する
極端に言えばアドバイスはリスクの高い解決方法だと受け取りました。やはりここでも聞くことで本人に解決策を気づいてもらうための会話が必要であることが記載されています。
そして話を聞いた最後には本人にきちんと存在自体に感謝を伝えることの重要性が記載されています。感謝しよう!
第7章 1on1を「最高の気づきの場」にするテクニック
自分はマネージャーに1on1して頂いてる立場なのですが、人と会話すると言う意味だと誰に対してもそれは1on1になり得るとは思ってます。
特に体調に関する記載は興味があり、人の体調変化は基本的に見えにくいものだと認識しています。
心身の不調を事前にキャッチすることで対策が可能ですが、ここでは手法として「10点満点中何点ですか?」と聞くことで詳しい話ができると記載していました。個人的にはそれも大事と思いますが、人に興味を持ち観察するのが一番だとは思います。
第8章 上手なダメ出しで納得してもらう「フィードバック」の技術
フィードバックの章です。ここは特に近年では難しい技術なのかなと感じていますが、言う必要のあることは言わなければならないでしょう。
要約すると「感謝の気持ちは忘れず」「正しい順序で」「でも事実を曲げずに伝える」なのかなと思います。言いたいことではなく、言う必要のあることを愛情もって伝えることが重要なのではないでしょうか。
感想
この本では立場上はリーダーや上司から部下への目線で記載されていますが、結局は人間関係ですので自分を含めた周りの人間関係全てに応用の効く話だと思います。
テクニックも大切だと思いつつ、やはり根底にあるのは相手のことを考え続けることが大切でそれが愛情なのかなと思っており、それは忘れずに実行していきたいなと思います。
また組織やチームにおいてリーダーやマネージャーは人を管理する役割を求められますが、メンバー目線からでも人を見て働きかけることが可能であり、上からではなく横からも支えられるような集団にできたら理想だなと感じます。