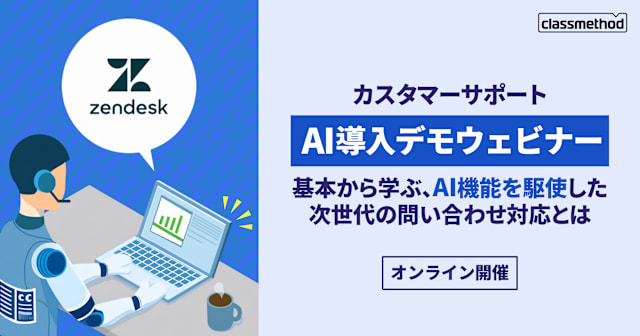行動変容には段階がある。どこで躓いているのか判別してから対策をすること
こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
仕事で従来のやり方が通用しなくなり、変化が求められることがあります。転職、人事異動、役割の変更、組織変更、市場の変化など、環境の変化が大きいほど自身の変化も必要になります。
一方、変化の道のりは困難です。変化が必ず成功するとは限りませんし、失敗した場合、行き詰まる要因は一箇所とは限りません。
この記事では、変化のプロセスを捉えるための行動変容ステージモデルを紹介します。
行動変容ステージモデル
変化を段階的に捉える考えとして、行動変容ステージモデルがあります。
| ステージ | 内容 |
|---|---|
| 無関心期 | 変化の必要性を感じておらず、行動を変える意志がない状態 |
| 関心期 | 変化の必要性を認識し始めるが、まだ行動には移していない状態 |
| 準備期 | 具体的に変化のための行動を始める準備をしている状態 |
| 実行期 | 新しい行動を実際に始めている状態 |
| 維持期 | 新しい行動が定着し、継続できている状態 |
行動変容ステージモデルの例
計画重視の企業文化の会社から実行重視の会社に転職した場合における変容のステージモデルに沿ってまとめると以下のようになります。
1. 無関心期
状態
前職の進め方が正しいと信じていて、新しい職場のやり方に違和感を覚えるが、合わせようという意識はまだ薄い。
例
「この会社は行き当たりばったりだな…。もっとちゃんと事前に考えてからやればいいのに」と内心で批判している。
2. 関心期
状態
周囲のスピード感や継続的改善の成果を目にし、「このやり方にも意味があるのかも」と考え始めるが、まだ行動を変えるには至っていない。
例
「確かに手を動かしてから考えることで、早く学習できているようだ。でも、自分には合わない気もするな…。」
3. 準備期
状態
新しいやり方を試してみようという気持ちが芽生え、具体的な取り組み方を観察・計画し始める。
例
「まずは小さいタスクから"とりあえずやってみる"を意識してみようかな。考えすぎず、一歩踏み出してみよう」
4. 実行期
状態
実際にまず着手し、試行錯誤しながら進めるやり方を実践している段階。違和感はあるものの、行動を変え始めている。
例
「まだ不安もあるけど、先にプロトタイプを出してみたらフィードバックがすぐにもらえて助かった。これはこれでアリかも」
5. 維持期
状態
新しい進め方に慣れ、意識せずとも自然に“まずやってみる”スタイルが身についてきている。
例
「最近は考えすぎる前に動けるようになったし、その後の継続的な改善にも慣れてきた」
行動変容ステージモデルのステージごとの難易度
長いキャリアで見てきた様々な職場の出来事をふりかえると、行動変容ステージモデルの各ステップは序盤ほど難易度が高いと感じています。
自分自身がこれまで基本としてきた考え方や行動が、今の状況ではうまく機能しておらず、失敗の原因になっていると認めるのは簡単ではありません。あくまで一時的な失敗だと捉えたり、失敗の要因は自分にはないと捉えることで目を背けることも珍しくありません。
また、仕事におけるすべての業務が定量的に成否を把握できるわけではないため、自分の言動が失敗だったかどうかも判断しにくく、「自分は失敗していない。うまくできている」と自分を納得させやすい背景でもあります。
このように、自分ひとりで自分の行動に関する課題を発見し、本当に取り組むべきものとして認識するのは難しいため、第三者の力を借りることができると理想的です。「この人が言うのなら妥当な指摘なのだろう」と思えるような信頼のある人からフィードバックをもらうことで、課題に目を向け、改善に取り組む段階に進みやすくなります。
相手が変化に四苦八苦するような重要な課題ほど、フィードバックする第三者も伝えるのに勇気がいります。「相手の心が折れてしまったらどうしよう」「相手に嫌われたらどうしよう」「相手に攻撃されたらどうしよう」など不安がよぎります。そういった不安がよぎらないくらいの信頼関係が必要になります。普段からフィードバックを受け入れる姿勢を示しておくことが、自己変容を早める土壌になります。
自分で変化のきっかけを掴むための一つのヒント
第三者の力を借りるのが変化の鍵ではありますが、物事を俯瞰して捉え、適切なフィードバックができて、なおかつ勇気を持ってそれを伝えてくれる人はどこにでもいるわけではありません。相手の成功や成長には興味がなく、自分の不満や怒りを伝えたり、自分の好みの進め方に従わせたいという目的でフィードバックをする人もいます。
それを踏まえると、自力でも変化できると安心です。
自分で変化のきっかけを得たい場合の考え方として、2つの鍵があります。
- 成功とこだわりの判断
- 客観視
1. 成功とこだわりの判断
1つ目の鍵は、『成功したいのか』それとも『失敗してもいいので自分の考えを曲げたくないのか』を判断することです。
自分のこだわりを押し通した結果としてうまくいかない状況が続いていて、それでも成功したいなら他のアプローチが必要なはずです。
この際にありがちなのは失敗の責任を他者や環境に求めることですが、本当に他者や環境が悪かったとしても自分ではどうにもできないことがほとんどです。周囲が変化するのを待っていてもいつ変わるかわからないため、自分の行動を変えて周囲に影響を与えるほうが能動的に変化を起こしやすくなります。
2. 客観視
2つ目の鍵は、『同じ状況でうまくやっている人はどのように振る舞っているのか』を知ることです。
大抵の場合、人によって苦労する状況でも成功につなげる事ができる人もいます。周囲にうまくやっている人がいるのなら、彼らは環境に即した行動ができているはずです。また、彼らも最初からうまくやっていたわけではなく、変化した結果としてうまくいくようになっているはずです。全くミスがなく、どの環境でも常に正解だけを選べるような人はいません。変化の大きさや速度に差はあれど、うまくやっている人は失敗から学び、変化を繰り返しているはずです。
うまくやっている人たちの言動を観察し、その判断基準を学び、自分と比較してみることで変化の必要性や変化の方法が見えてくるかもしれません。また、観察してもわからない場合は相手に聞いてみるのが一番です。仕事の具体的な場面で、相手が何を考え、どのように判断しているのかを直接尋ねてみることが有効です。