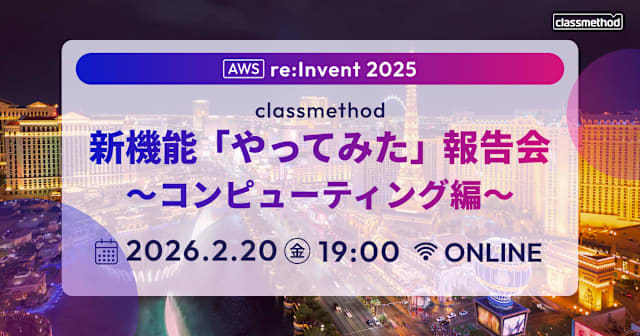AWS Certified AI Practitioner – Foundational 認定取得に向けて「Generative AI Essentials on AWS」を受講しました
こんにちは、Haradaです。
今回は、AWS Certified AI Practitioner – Foundational 認定資格の取得を目指し、
公式トレーニング「Generative AI Essentials on AWS」を受講しました。
本記事では、受講内容や学びのポイントを簡潔にご紹介します。
その1.トレーニング概要
■ トレーニングの構成
この講座は、以下の7つのモジュールで構成されています。
- 生成AIの紹介
生成AIの概要や仕組み、基盤技術を学びます。 - 生成AIのユースケースを探る
生成AIがどのような場面で有効かを理解し、適切なユースケースを見極めます。 - プロンプトエンジニアリングの要点
効果的なプロンプトの設計手法や応用テクニックを学びます。 - 責任あるAIの原則と考慮事項
AIの倫理、バイアス、透明性など社会的責任の観点を理解します。 - セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンス
生成AI特有のリスクや脅威に対するセキュリティ対策を学習します。 - 生成AIプロジェクトの実装
ユースケース定義からFM(基盤モデル)選定、デプロイまでの流れを学びます。 - 生成AIソリューションの開発
実際のビジネスドキュメントを通じてソリューション開発のプロセスを体験します。
■ ハンズオンの実践モジュール
モジュール 3・4・7 では、Amazon Bedrock 環境でのラボ演習が用意されており、
生成AIを「実際に手を動かして」学べる構成でした。
体験型の学習によって、知識が定着し、現場での活用イメージもつかみやすくなりました。
■ この講座がおすすめな人
この講座は、以下のような「生成AIに関心のあるビギナー層」に特におすすめです。
- 生成AIに関心のある方
- AWS Certified AI Practitioner – Foundational の受験を検討している方
その2.各モジュールの学びと感想(ダイジェスト)
■ モジュール1:生成AIの紹介
学べること:
- 生成AIの定義と、ディープラーニングとの関係
- テキスト、音声、画像、コードなど、生成対象ごとの特徴
- 基盤モデルやLLMの基本動作と推論の仕組み
- 生成AIのリスク(ハルシネーション、バイアス、知財、倫理)
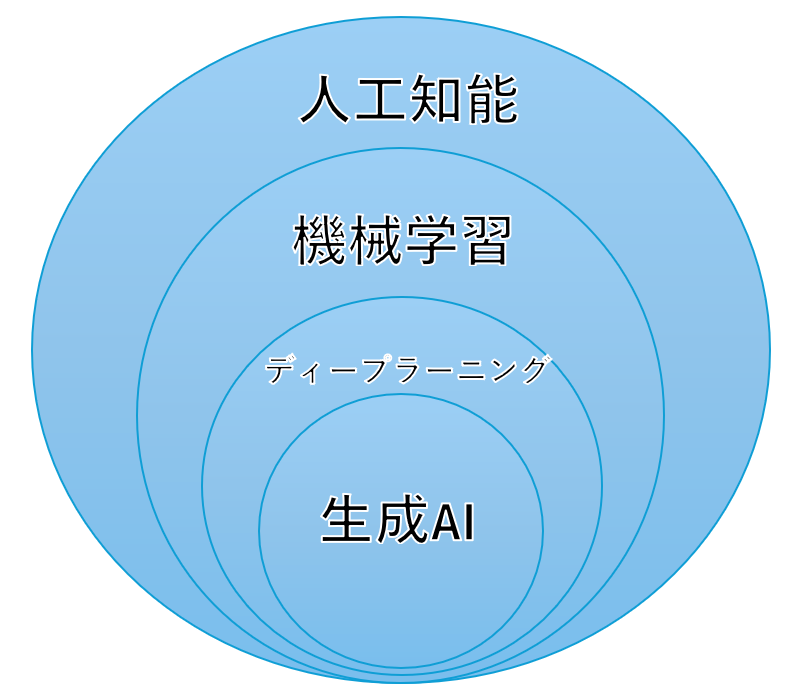
感想:
生成AIが「確率」で成り立っていることを体系的に理解できた。ベース技術を知ると応用の見え方が変わる。
■ モジュール2:ユースケースを探る
学べること:
- 生成AIが向いているタスクと、MLとの使い分け
- 導入判断に必要な観点(コスト、データ品質、法的制約など)
- AIを使わない選択肢の妥当性(if/then条件など)
感想:
生成AIは万能ではないことを痛感。ビジネス価値とリスクを天秤にかける視点が重要だと再認識。
■ モジュール3:プロンプトエンジニアリングの要点
学べること:
- プロンプト設計の原則と高度な応用(RAG、CoT、ToT)
- 出力制御のための各種パラメータ(Temperature, Top-K/P)
- Amazon Bedrockによるプロンプト最適化の実践
感想:
少しの工夫で出力品質が激変するのが面白い。壁打ちや発想補助など用途に応じた使い分けが可能。
■ モジュール4:責任あるAIの原則と考慮事項
学べること:
- 公平性・説明可能性・制御性など、AI倫理の8要素
- SageMaker Clarify / Autopilotの役割と使い所
- Amazon Bedrock Guardrailsによる制御の仕組み
感想:
「便利なAI」だけでなく「信頼されるAI」を設計する視点が得られた。Guardrailsは実用度が高い。
■ モジュール5:セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンス
学べること:
- 生成AI特有の攻撃(プロンプトインジェクション等)の理解
- Guardrailsやアクセス制御による防御方法
- 従来の情報セキュリティとの共通点と違い
感想:
従来のITセキュリティとは異なる新たな脅威に対応する必要性を学べた。
■ モジュール6:生成AIプロジェクトの実装
学べること:
- プロジェクトライフサイクル全体像(定義~評価~デプロイ)
- FM選定と、ファインチューニング vs ナレッジ拡張の違い
- コスト・精度のバランスを考えた設計の視点
感想:
開発プロセスの全体を俯瞰できるようになり、実務への応用がイメージできた。
■ モジュール7:生成AIソリューションの開発
学べること:
- KPI設定による成果の定量化
- 生成AI活用の効果測定の考え方
感想:
単なる導入で終わらず、価値を「測れる」ことが重要だと実感。KPI設計は特に今後役立つ。
その3.受講を終えて
私はこのトレーニングを 2025年2月末 に受講し、4月上旬に AWS AIF 認定資格を取得しました。
特に印象に残っているのは、テキストでは理解しづらい「Top-K値」や「温度パラメータ」などを、
ハンズオンを通して体感的に学べたことです。
非エンジニアの私にとっては、自学だけでは得がたい「感覚的理解」や「出力の傾向を読む力」を養う貴重な経験となりました。