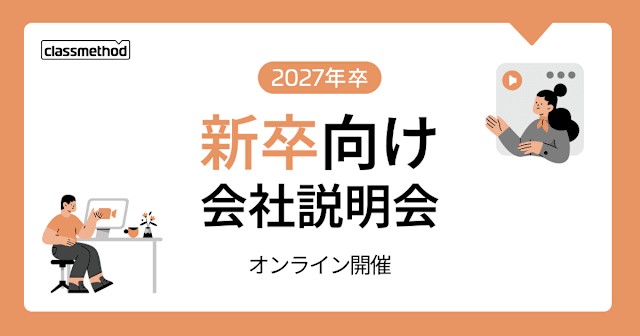![[登壇レポート]激動の2025年、Modern Data Stackの最新技術動向 #data_summit_findy](https://devio2024-media.developers.io/image/upload/f_auto,q_auto,w_3840/v1762414053/user-gen-eyecatch/ic01zjsr4ufp6zk5e01o.png)
[登壇レポート]激動の2025年、Modern Data Stackの最新技術動向 #data_summit_findy
さがらです。
Findy社の主催で、2025年11月6日にData Engineering Summitが開催されました。
このイベントにて、大変ありがたいことにSpecial Speaker枠として招待頂いたため、「激動の2025年、Modern Data Stackの最新技術動向」というタイトルで登壇してきました。
その登壇資料や質疑応答について、本記事でまとめます。
登壇資料
こちらは資料をダウンロード頂くと、各機能のドキュメントなどへリンク可能です。
質疑応答
※実際の質問の文章そのままではなく、私の記憶を元に頂いた質問の内容を書いておりますのでご了承ください。
Q:SnowflakeとDatabricksにベンダーロックインしないためにはどういうことができますか?
なかなか回答が難しい質問ですが、Icebergなどのオープンテーブルフォーマットを取り入れることで、データ自体はユーザー管理のS3に保持がされるため移行もしやすく、別のクエリエンジンからも柔軟にクエリができる、ということでベンダーロックインを多少避けることはできると考えております。
Q:Icebergがレイクハウスフォーマットの筆頭となるのでしょうか?
ここ1~2年の動きを見ていると、AWS、Google Cloud、Snowflake、Databricks、いずれもIcebergに最も力を入れている印象があるため、今はIcebergが筆頭という印象があります。
一方で、DuckLakeのように新しいレイクハウスフォーマットも出てきていますので、Icebergを見つつ、類似技術の動向はウォッチすることをおすすめします。
Q:Omniはなぜそこまで伸びているのでしょうか?
これまでのセルフサービス型BIとSemantic Layer型BIの良いところ取りをしているのが、Omniだと感じています。
セルフサービス型BIの特徴として、データソースに繋いですぐに分析できるところが強みだと思いますが、各計算フィールドなどの定義がワークブックで閉じてしまいガバナンスを保つことの難しさが悩ましいです。
一方でSemantic Layer型BIの特徴として、事前にコードを書いてディメンションやメジャーの定義を行うことで全員が同じ定義の元で分析ができる強みですが、事前にコードを書くということで分析のスピードが落ちてしまうことが悩ましいです。
Omniのアプローチは、「セルフサービス型BIのようにすぐにデータに繋いでGUIベースの操作で計算フィールドや結合定義が行った上で、定義した指標がSemantic Layerのコードに裏側で変換される」という、従来のBIの良いところ取りをしたアプローチです。このアプローチがユーザーから評価を受けていると考えています。
Omniのこの良さを知って頂く上では、以下のブログが参考になると思いますので、ぜひご覧ください。
Q:Semantic Layerでは何がおすすめでしょうか?
最近触った技術の中で言うと、Omniはやはりお勧めですね。先の質問の回答の通り従来のBIの良いところ取りをしたアプローチであることに加え、豊富なAI用のコンテキスト設定機能もありますし、Omni内でも多くの生成AIを用いた機能があるため、Semantic Layerを定義しつつ、生成AIと組み合わせる良さをすぐに感じて頂けると思います。
一方でOmniも有償のBIツールですので、まず気軽に試したいという観点でいうと、SnowflakeのSemantic View、DatabricksのUnity Catalogのmetric viewなどは、Semantic Layerを試す第一歩としておすすめです。
登壇を終えて
改めて、セッションをご視聴頂いた皆様ありがとうございました!
今回の登壇内容をまとめてみて、やはりSnowflakeとDatabricksは強いという印象を受けたのと、LLMの台頭に伴う各機能の発表が多くあったのを実感しました。
一方で、SnowflakeやDatabricksの1プラットフォームとして強くなっているこの状況や各企業の買収や統合もあって、Modern Data Stackというワードもトレンドの節目を迎えている印象も受けましたね…ちょっと寂しいですがw
ただ、今後も新しい機能が各製品からリリースされていくということは間違いないので、私は引き続き各製品の最新動向を追って、ブログや登壇を通して情報発信は続けていければと思います!