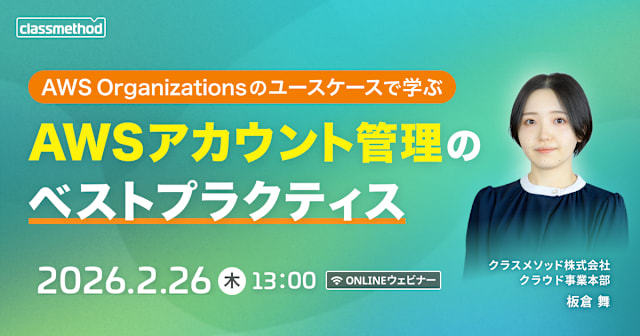問題の明確化 – 感情のみの共有
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
仕事において、大小さまざまな問題が存在します。誰かが問題について話すとき、すぐに解決に向けて取り組むことができるとは限りません。問題を解決していく前に、問題の明確化が必要なケースがあります。
感情のみの共有
例えば、「このチームで仕事をすることがストレスで辛いです」という情報があった場合、大まかにチームに関わる何かが問題であることは伝わりますが、それ以外はストレスがあることと辛いという感情のみが分かる状態です。
「感情のみの共有」を整理する
共通の対応
情報を引き出す際には事実を引き出すことが重要です。When、Where、Who、What、Howなどの質問によって事実を問うのが有効です。逆に「なぜ」「どうして」などの質問は事実ではなく、解釈を引き出しやすくなります。解釈は事実と一致しているとは限らないため問題の本質からそれてしまう可能性があります。
感情の扱いに注意する
これ以降の部分に関しては「共通の対応」にまとめた内容で問題の詳細を確認していくことになります。
まとめ
感情の情報だけでは問題がなにか分からないため困惑したり、自分自身も感情に流されやすくなりがちです。一方で、感情の裏にはその原因となる事象があるはずです。相手に寄り添い、共感し、詳細を整理し、問題の解消の材料を整理していくことになるでしょう。なお、その感情の矛先が自分だった場合、相手の心情を考えると自分が詳細を引き出すのは難しいかもしれません。その場合は、第三者の協力が必要になるでしょう。