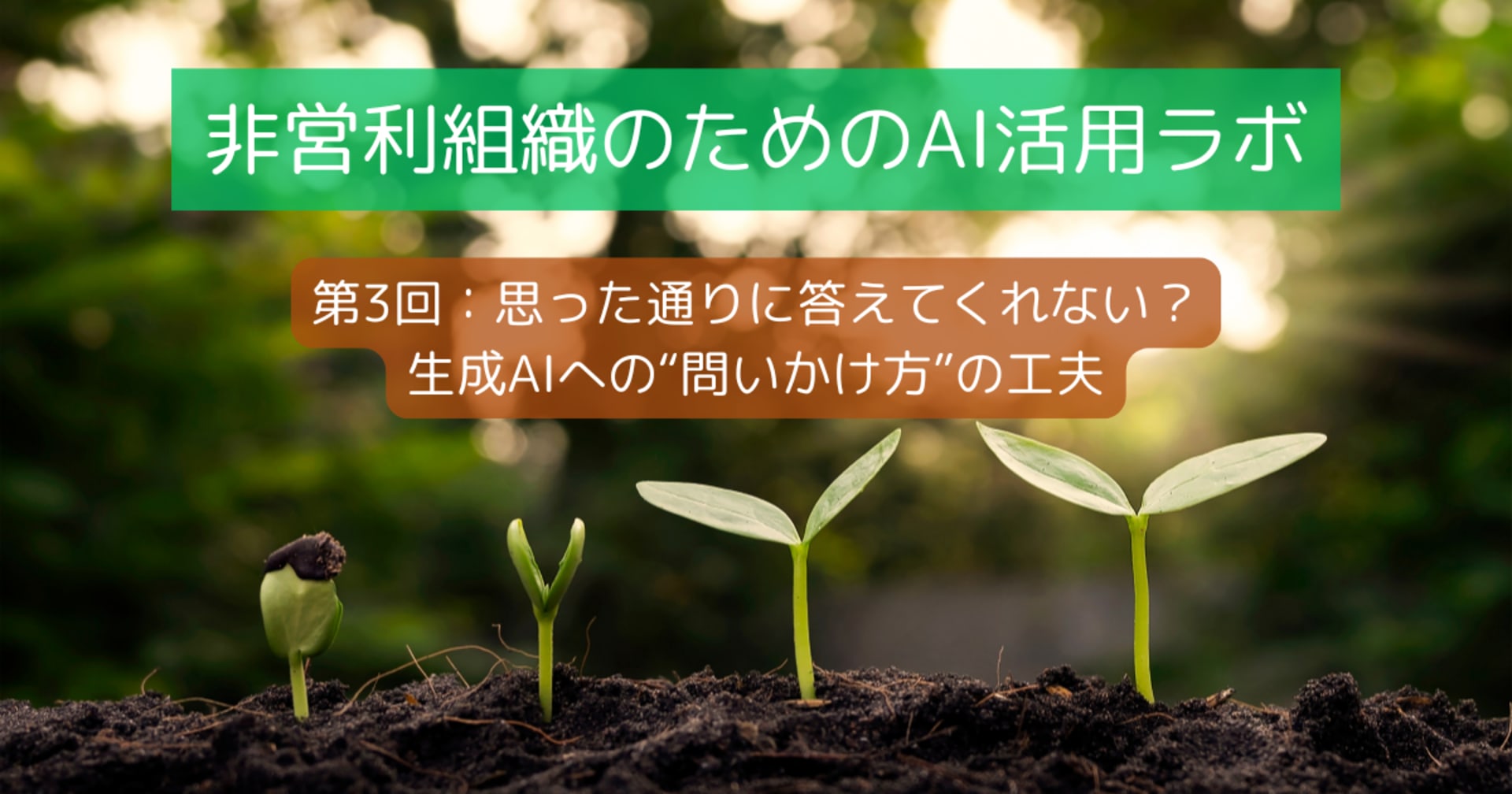最小から最大プロンプトで段階的に解決する
こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
今回は Gemini で最小から最大プロンプトを利用して、複雑なタスクを段階的に扱う方法を試してみます。
最小から最大プロンプトとは
最小から最大プロンプト ( Least to Most Prompting ) とは、複雑なタスクを最小のステップから最大のゴールに向かって、段階的に中間ステップに分解し、一つずつ解かせる手法です。
プロンプトの実施は一気に指示することもあれば、段階的に指示することもあります。
思考の連鎖プロンプトとの違い
以前、以下の記事で 思考の連鎖プロンプト ( Chain-of-Thought Prompting ) を紹介しました。
AI壁打ちシリーズ : 思考の流れを推測する | DevelopersIO
最小から最大プロンプトと思考の連鎖プロンプトは段階的という意味では似ていますが、最小から最大プロンプトでは、ユーザーが段階を明示するのに対して、思考の連鎖プロンプトは結果の出力の過程としてAIが判断した段階を明示してもらうという点が異なります。
最小から最大プロンプトの例
段階的に実施する例
入力
私は『業界トップクラスのノイズキャンセリング性能』と『丸一日持つバッテリー寿命』を売りにした新しいワイヤレスイヤホンのレビュー記事を作成したいです。
読者に響く記事にするために、まずはこのタスクを解決するために必要な論理的な中間ステップを箇条書きで洗い出してください。
出力
「承知いたしました。読者に響く記事を作成するために、以下の3つの中間ステップが必要です。
1. 記事の核となる特長の決定(二つの強みのうち、どちらをメインに据えるか)。
2. 決定した特長に基づいたキャッチーな記事タイトルの候補を複数作成。
3. 最も良いタイトルと特長を結びつける、読者の興味を引く導入文の作成。」
入力
ステップ1を進めます。この二つの強み(『業界トップクラスのノイズキャンセリング性能』と『丸一日持つバッテリー寿命』)のうち、記事の核とする特長を一つ選び、その選択理由を簡潔に述べてください。
出力
記事の核とすべき特長は、『業界トップクラスのノイズキャンセリング性能』です。
理由: ノイズキャンセリングはユーザー体験に直結し、「業界トップクラス」という表現が競合優位性を最も強く示唆するため、記事をクリックさせる強力な動機になります。
入力
ありがとうございます。ステップ2に進みます。先ほどの回答で選ばれた特長 『業界トップクラスのノイズキャンセリング性能』 に焦点を当て、読者の期待感を高めるような記事タイトルを3つ提案してください。
出力
承知いたしました。特長を強調したタイトルを3つ提案します。
1. 【静寂を支配】業界トップクラスのノイズキャンセリングを体験!新ワイヤレスイヤホン徹底レビュー
2. 世界が消える。ノイキャン性能の限界を超えたイヤホンがもたらす極上の集中体験
3. もはや魔法!静寂を手に入れたいあなたへ贈る、最強ワイヤレスイヤホン
入力
最終ステップに進みます。
ステップ3で提案されたタイトル候補の中から最も優れていると思うタイトル(例:No.1)を選び、そのタイトルと特長(ノイキャン性能)を効果的に使った**導入文(50〜80文字程度)**を、すぐに記事に使える形で作成してください。
出力
最終結果を出力します。
最も優れているタイトルはNo.1の**『【静寂を支配】業界トップクラスのノイズキャンセリングを体験!新ワイヤレスイヤホン徹底レビュー』**を選びます。
導入文:
『【静寂を支配】業界トップクラスのノイズキャンセリングを体験!』 騒音から解放され、自分だけの世界に没入したいと願うあなたへ。ついに、その願いを叶えるワイヤレスイヤホンが登場しました。
一気に実施する例
先ほどと同じ内容を1つのプロンプトで指示するケースです。
入力
あなたは、新しいワイヤレスイヤホンのレビュー記事を作成する編集者です。このイヤホンには**『業界トップクラスのノイズキャンセリング性能』と『丸一日持つバッテリー寿命』**という2つの強みがあります。
以下の手順をステップバイステップで実行してください。
1. まず、このレビュー記事の核とする最も魅力的な特長を一つ選び、その理由を簡潔に述べてください。
2. 次に、選んだ特長に焦点を当てたキャッチーな記事タイトルの候補を3つ提案してください。
3. 最後に、提案したタイトルの中から最も優れていると思うものを一つ選び、そのタイトルと特長を効果的に使った**導入文(50〜80文字程度)**を、記事にすぐに使える形で作成してください。
回答は、これらのステップを全て実行した結果として、最終的なタイトルと導入文を含めて出力してください。
出力
承知いたしました。ご依頼のタスクをステップバイステップで実行します。
ステップ1:記事の核となる特長の決定
最も読者の関心を引き、記事の核とすべき特長は、**『業界トップクラスのノイズキャンセリング性能』**です。
理由: ノイズキャンセリング性能はユーザー体験に直結する機能であり、「業界トップクラス」という訴求力が、記事をクリックさせる最も強い動機になります。
ステップ2:キャッチーな記事タイトルの候補作成
選んだ特長に基づき、以下の3つのタイトルを提案します。
【静寂を支配】業界トップクラスのノイズキャンセリングを体験!新ワイヤレスイヤホン徹底レビュー
世界が消える。ノイキャン性能の限界を超えたイヤホンがもたらす極上の集中体験
もはや魔法!静寂を手に入れたいあなたへ贈る、最強ワイヤレスイヤホン
ステップ3:最終的なタイトルと導入文の作成
上記の候補から、最も具体的でインパクトのあるNo.1のタイトルを採用します。
最終タイトル:
【静寂を支配】業界トップクラスのノイズキャンセリングを体験!新ワイヤレスイヤホン徹底レビュー
導入文:
『【静寂を支配】業界トップクラスのノイズキャンセリングを体験!』 騒音から解放され、自分だけの世界に没入したいと願うあなたへ。ついに、その願いを叶えるワイヤレスイヤホンが登場しました。
人事領域における活用例
マネージャーがメンバーに向けてフィードバック内容を検討する例です。やりとりの内容はすべて架空のものです。
入力
メンバーに向けて納得感の高い評価フィードバック文書を作成したいです。
単なる評価ではなく、本人の成長を促すための文書にするために必要な中間ステップを箇条書きで洗い出してください。
各ステップは1つずつ段階的に掘り下げていきたいのはまずは最小限の見出しだけ教えてください。
各ステップは1つずつ段階的に掘り下げていきたいのはまずは最小限の見出しだけ教えてください。
という部分ですが、最小限の出力を促さないと各ステップに対してかなり詳細な出力がされてしまうことになります。
出力
メンバーの成長を促すための、納得感の高いフィードバック文書作成のステップですね。
単なる評価に留まらず、次のアクションにつながる文書にするための重要な中間ステップを、まずは最小限の見出しとして洗い出します。
### 成長を促すフィードバック文書作成のステップ(見出し)
* **目的とゴールの明確化**
* **情報とデータの収集**
* **分析とパターンの特定**
* **「未来志向」での構成案作成**
* **草稿作成と調整**
---
まずはこれら5つの見出しから、段階的に掘り下げていきましょう。
入力
目的とゴールの明確化について、まずは評価制度およびメンバーの育成支援を踏まえて、評価フィードバックの一般的な目的とゴールを教えてください。
差分があれば私から補足します。
出力
最初のステップである**「目的とゴールの明確化」**について、「評価制度」と「メンバーの育成支援」の2つの観点から、フィードバックの一般的な目的とゴールを整理します。
---
## 目的とゴールの明確化
フィードバック文書の作成にあたり、一般的な目的とゴールは以下の通りです。
これらは、単なる過去の評価の伝達ではなく、「未来の成長」を促すための土台となります。
### 1. 評価制度の観点からの目的とゴール
| 種別 | 目的(Why) | ゴール(What) |
| :--- | :--- | :--- |
| **評価の適正化** | 評価の背景、根拠、そして判断基準を明確に伝え、評価の透明性と公平性を担保する。 | メンバーが**自身の評価結果に納得**し、評価プロセス全体への**信頼**を維持・向上させる。 |
| **意思決定の根拠** | 給与、賞与、昇進・昇格といった人事上の意思決定の根拠を、メンバーと組織全体に対して文書として示す。 | 人事上の**決定事項への理解**を得て、組織的な**整合性**を保つ。 |
| **目標設定** | 前期間の成果と行動を総括し、次期間の**目標設定**や期待される**役割・行動基準**の明確化に繋げる。 | 次期間の**目標設定が具体的**になり、メンバーが**取るべき行動**の方向性が定まる。 |
### 2. メンバーの育成支援の観点からの目的とゴール
| 種別 | 目的(Why) | ゴール(What) |
| :--- | :--- | :--- |
| **行動変容の促進** | 成果に繋がった**強み**と、改善が必要な**課題(成長機会)**を具体的に伝え、**行動の振り返り**を促す。 | メンバー自身が、次に**どのような行動**を取り、**何を学習**すべきかについての**気づき**を得て、**成長意欲**を高める。 |
| **期待値の調整** | 組織や上司が、現在のメンバーの能力や役割に対して**何を期待しているのか**を明確に伝え、**認識のズレを解消**する。 | メンバーと上司の間で、**期待される成果や行動**に関する**共通理解**(アラインメント)を構築する。 |
| **キャリア支援** | 現在の役割におけるフィードバックを通じて、メンバーの**中長期的なキャリアパス**や**能力開発**の方向性を共に考えるきっかけとする。 | メンバーが**自身の強みと弱み**を活かし、組織内での**継続的な貢献**と**自己実現**を図るための**具体的なアクションプラン**を持つ。 |
これらの目的とゴールは、フィードバックが単なる「通知」ではなく、**「対話のための資料」**であり、**「成長のための羅針盤」**としての役割を果たすことを示しています。
---
あたなの会社やチームにおけるフィードバックの目的について、上記で特に強調したい点や、追加で補足すべき差分はございますか?
入力
ありません。次に進みましょう。
次は、情報とデータの収集です。
メンバーは、ジュニアのグレードから一人前のグレードに上がる直前です。
今年度は、一通りの業務を自分一人で担当できるようになっています。自己評価だけではなく、周囲の同僚からも同様の意見を聞いています。
また、マインドとしても指示待ちではなく、自ら考え、率先して動くことができています。
これらは、一人前のグレードの評価基準に即しています。
出力
次のステップは、納得感の高いフィードバック文書の土台となる**「情報とデータの収集」**です。
対象のメンバーは、**ジュニアから一人前への移行直前**という非常に重要なフェーズにいますね。一通りの業務を一人で担当でき、指示待ちではなく自発的に動けているという情報は、フィードバックを組み立てる上で強力な裏付けとなります。
この段階で、評価の納得感と成長促進のために、特に何を、どのような観点から収集・整理すべきかをまとめます。
---
## 情報とデータの収集
このフェーズでは、**「評価基準を満たしている証拠」**と**「次の成長ステップを見つけるためのヒント」**の2つに焦点を当てて情報を収集・整理します。
### 1. 評価基準への適合性を裏付ける定量・定性データ(過去の達成度)
一人前のグレードへの昇格を裏付けるために、**客観的な事実**を集めます。
* **目標達成に関する定量データ:**
* 担当した主要業務の**達成率**や**結果**(例:リード数、エラー率、処理時間など)。
* 業務遂行における**効率性やスピード**の変化を示すデータ。
* **行動・プロセスに関する定性データ:**
* **「一人で担当できた」**ことを示す具体的な事例(例:自力で解決した課題、他者のサポートなしで完了させたプロジェクト)。
* **「自ら考え、率先して動いた」**ことを示す具体的な行動(例:提案した改善策、主導して行った連携、事前にリスクを察知し対処した事例)。
* **自己評価、同僚からの意見**を裏付ける具体的なコメントやエピソード。
### 2. 「一人前」から「次なるステージ」へ進むためのデータ(未来の成長機会)
この情報は、**「強み」**を次のレベルに引き上げるために、あるいは**「潜在的な課題」**を成長機会に変えるために不可欠です。
* **「一人でできる」の質に関する情報:**
* **判断の「深さ」**に関するエピソード(例:*なぜ*その方法を選んだのか、複数の選択肢から*どう*比較検討したのか)。
* **影響の「範囲」**に関する情報(例:自身の業務外に、チームや部署に良い影響を与えたか。他のメンバーをサポートしたか)。
* **マインドセットの「持続性」に関する情報:**
* **困難な状況**や**予期せぬトラブル**に直面した際の対応(例:プレッシャー下でも自発性が維持されたか、失敗から何を学んだか)。
* **他者への影響力**に関する情報(例:チーム内での知識共有の頻度、後輩やジュニアメンバーへの教え方)。
* **育成者自身の気づき:**
* メンバーの**能力が「期待値を超えた」**と感じた具体的な瞬間と、その理由。
* フィードバックや指示が**「不要」**になったと感じた業務の具体的な内容。
---
この収集・整理のリストで、特に意識して情報を集めたい点や、既に手元にある情報に照らして追加すべき観点はありますか?
入力
チームの課題管理ツールのログや、コメントのやりとりがあるので後でそこを確認しておきます。
次は『分析とパターンの特定』なのですが、あなたが提案してくれたこの内容についてもう少し補足してください
出力
収集した情報を単なる事実の羅列で終わらせず、納得感と成長に繋げるための核心的なステップ、**「分析とパターンの特定」**について掘り下げて解説します。
---
## 分析とパターンの特定
このステップの目的は、収集した**客観的なデータやエピソード**の中に隠れている**メンバーの「核となる能力」や「行動の傾向」**を見つけ出すことです。
フィードバックの価値は、「○○ができました」という事実の伝達ではなく、「○○という行動を**継続的**に行った結果、**こう**なりました。これはあなたの**こういう**強み(あるいは傾向)によるものです」と**抽象化して伝える**ことで生まれます。
### 1. 「昇格の根拠」となるパターン(一人前グレードへの適合)の特定
これは、メンバーが一人前グレードの基準を満たしたことを、**複数の事実で裏付ける**作業です。
| 分析観点 | 掘り下げる質問 | 特定すべきパターン(例) |
| :--- | :--- | :--- |
| **業務遂行能力の安定性** | 一人で担当できた業務は、難易度や種類が異なる場合でも**安定して**結果を出しているか? | 特定の業務だけでなく、**標準的な業務プロセス全般**において**一貫して品質を保てる**能力がある。 |
| **自発性の傾向と質** | 「自ら考え、動いた」行動は、**問題を解決するため**だったか? それとも**効率を上げるため**だったか? | **「問題を未然に防ぐ」**ことに関心が強く、常に**先を見越して**行動できる**リスク管理能力**が高い。 |
| **同僚の意見の共通点** | 同僚からの評価(「一人でできる」)の裏には、具体的に**どのスキル**や**どの姿勢**が評価されているのか? | **コミュニケーションコストが低い**(質問が的確、報連相が最小限で済む)ため、周囲から**安心して業務を任せられる**と認識されている。 |
### 2. 「次の成長機会」となる能力のパターン(未来志向のヒント)の特定
これは、次のグレード(例:中堅、チームリーダー候補)へ進むために必要な、**メンバー自身が気づいていない「伸びしろ」**を見つけることです。
| 分析観点 | 掘り下げる質問 | 特定すべき成長パターン(例) |
| :--- | :--- | :--- |
| **「なぜ」の探求(意思決定の深さ)** | 成功例や失敗例における**判断の根拠**は、組織の全体目標や戦略とどれだけ結びついているか? | 「正しい手順」を選べているが、「**なぜ**その手順が組織にとって最適か」という**目的意識がまだ弱い**。 |
| **「影響の範囲」のパターン** | 自身の業務の範囲を超えて、**他者の行動を変えたり**、**チームの標準を変えたり**した事例はあるか? | **個人プレーの完結度**は高いが、**周囲を巻き込む力**や、自身の知識を**形式知化して共有する仕組み**を作る経験が不足している。 |
| **エネルギー源の特定(モチベーション)** | メンバーは**どんな時に**最もイキイキと成果を出しているか?(例:難しい技術課題、新しい顧客との対話、改善提案など) | **ルーティンよりも挑戦**に意欲を見せるタイプであり、今後は**複雑なプロジェクト**や**専門性の深化**が成長を促す可能性がある。 |
この「分析とパターンの特定」を行うことで、フィードバックは**「あなたはその能力を活かして、次の課題に取り組める」**というメッセージに変わり、メンバーの納得感と、行動への意欲を大きく高めることができます。
この分析プロセスについて、特に重点を置きたい点やご質問はございますか?
入力
まとめてもらった観点について、どの側面からも昇格に十分な材料があります。内容は後でまとめます。
また、未来に向けた課題については、主体性はあるものの課題の重要性、優先度の見極めがまだ苦手そうなので、その点は今後強化していきたいところです。
次に進みましょう。
あなたが提案した『「未来志向」での構成案作成』ですが、どのような意図の内容ですか?
出力
メンバーが昇格基準をクリアしていること、そして次の成長機会として**「課題の重要性、優先度の見極め」**が明確になったことは非常に重要です。
それでは、次のステップである**「『未来志向』での構成案作成」**について、その意図と具体的な構成要素を説明します。
---
## 「未来志向」での構成案作成の意図
このステップの意図は、フィードバック文書の**メッセージの重心**を「過去の評価」から**「未来の成長」**へ意図的にシフトさせることにあります。
メンバーは昇格に必要な成果と主体性を達成しています。そのため、文書の主要な目的は「あなたは一人前になった」という**承認**と、「次に進むために、この能力を**どう伸ばすべきか**」という**指針**の提示に変わります。
単なる評価報告書ではなく、メンバーの**次のキャリアに向けた「招待状」**として文書を構成することが狙いです。
### 意図を達成するための具体的な構成要素
「未来志向」の文書は、過去(フィードバック)から未来(フィードフォワード)へ、メンバーの**主体性**を促しながら展開します。
#### 1. 冒頭:過去の承認と未来への期待(ポジティブな着地)
文書の最初の部分で、メンバーの**努力と昇格の達成を強力に承認**します。
* **構成の意図:** メンバーの心理的安全性を高め、フィードバック全体を前向きに受け入れる土台を作る。
* **具体例:**
* **事実の承認:** 「今期、あなたは一人前のグレードに求められる全ての基準、特に『一通りの業務完遂』と『自発的な行動』を**見事に達成しました**。」
* **未来への橋渡し:** 「この成果はあなたの大きな財産であり、次のステップである『より大きな影響力を発揮する』役割に進むための確固たる基盤となります。」
#### 2. 中盤:強みの本質化と昇格の根拠(パターンを未来に繋げる)
分析で見つけ出した**核となる強み(パターン)**を明確に伝え、それが昇格の決定的な根拠であることを示します。
* **構成の意図:** 評価結果の**納得感**を高め、メンバーが**「何を継続すべきか」**を理解させる。
* **具体例:**
* 単なる「仕事が速い」ではなく、「あなたの**『先を見越して手順を設計する能力』**こそが、同僚から『安心して任せられる』という評価に繋がっています。」といった形で、**能力の本質**を記述します。
#### 3. 終盤:「成長機会」の定義と「行動変容」の提案(フィードフォワード)
あなたが特定された「課題の重要性、優先度の見極め」を、**ネガティブな指摘**ではなく**「次のステージへのチケット」**として提示します。
* **構成の意図:** 過去の行動を責めるのではなく、**未来の行動**と**具体的なサポート**に焦点を当てる。
* **具体例:**
* **成長機会の定義:** 「これまでは『やるべきこと』を完遂してきましたが、次のステップでは『**最もインパクトの大きな課題**』を選び出す能力が求められます。これが、あなたがより大きな価値を生み出すための**成長機会**です。」
* **行動の提案(フィードフォワード):**
* 「来期は、業務に取り掛かる前に、**『このタスクの完了が、チームの目標達成にどう貢献するか』を言語化**してから着手するプロセスを試してみましょう。」
* 「来週の1on1では、あなたが検討した**課題の優先度マップ**を一緒に見直しましょう。」
---
このように「未来志向」で構成することで、文書は「昇格しました」という**過去の通知**で終わらず、「あなたはもっと成長できる、そのために**組織としてこうサポートする**」という**未来へのコミットメント**を示すものになります。
この構成案について、特に深掘りしたい点はありますか?もしなければ、最終ステップの「草稿作成と調整」に進みます。
入力
未来志向のフィードバックは、いわゆるフィードフォワードというやつですね。
意図がわかりました。詳細は後ほど入力しておきます。草稿作成と調整をしましょう。
なお、私が暫定にした部分はあとで入力が必要な部分として目印を残してください。それを踏まえて、フィードバック文書の草案を作成してください。
出力
あなたのおっしゃる通り、未来志向のフィードバックとは、まさに**「フィードフォワード」**の考え方を文書に落とし込むことです。過去の事実を未来の成長につなげるという視点で、この最終ステップを進めます。
---
## 草稿作成と調整
最終ステップである**「草稿作成と調整」**では、これまでのステップで整理・分析した内容を、メンバーの心に響き、行動を促す文書として具体化します。
ここでは、フィードフォワードの構成に沿った文書の**草案**と、文書の**効果を最大化するための調整の観点**を提示します。
### フィードバック文書 草案(未来志向型)
以下に、昇格直前のメンバーに向けたフィードバック文書の骨子と、あなたが後ほど入力すべき**【暫定目印】**を残した草案を示します。
#### 1. 冒頭:達成の承認と未来への期待(ポジティブな着地)
| 見出し | 記述内容(草案) |
| :--- | :--- |
| **評価期間の総括と承認** | **【メンバー名】**さん、今期は本当にお疲れ様でした。あなたはジュニアグレードの役割を完全に卒業し、この度、**一人前のグレードへの昇格**が決定しました。これは、評価期間を通じてあなたが示した**【暫定目印:最も顕著な成果(例:困難なプロジェクトの完遂、特定の指標の劇的な改善)】**という具体的な成果と、その達成を支えた揺るぎない**主体的な姿勢**によるものです。 |
| **感謝と期待** | **【暫定目印:具体的な感謝の言葉(例:チームへの貢献、周囲への影響など)】**。あなたの安定した業務遂行能力は、チームにとって不可欠です。次期は、この新しいグレードで、さらなる成長と活躍を期待しています。 |
#### 2. 中盤:強みの本質化と昇格の根拠
| 見出し | 記述内容(草案) |
| :--- | :--- |
| **強み(核となる能力)** | あなたの最大の強みは、**「【暫定目印:分析した核となる能力のパターン(例:先読み能力、構造化力)】」**です。一通りの業務を**一人で完遂**できたのは、単に手順を覚えたからではなく、この**【パターン】**によって**判断と行動の質**が高まっていたからです。同僚からの「安心して任せられる」という評価は、この能力がチームの信頼に繋がっている何よりの証拠です。 |
| **一人前のグレード適合性** | 上記の能力により、あなたは一人前のグレードに求められる**「自ら考え、率先して動く」**という基準を完全に満たしました。今後は、この強みを活かし、より**複雑な課題**や**広範な影響**を持つ業務に挑戦してもらいます。 |
#### 3. 終盤:「成長機会」の定義と「行動変容」の提案
| 見出し | 記述内容(草案) |
| :--- | :--- |
| **次なる成長の焦点** | 次期、あなたがさらに大きな影響力を発揮し、中堅グレードへとステップアップするために焦点を当てるべき成長機会は、**「課題の重要性・優先度の見極め」**です。あなたは**主体性**を持って多くの課題に取り組みますが、今後は「**【暫定目印:最もインパクトの大きな課題の定義(例:組織の目標達成に直結する課題)】**」に時間とエネルギーを集中させる**判断力**を磨いていきましょう。 |
| **具体的な行動(フィードフォワード)** | そのために、以下を次期の行動として特に意識してください。 **1. 計画的な意思決定:** 業務着手前に、「この課題の解決が、**チームの目標**に**【数値で表せる貢献】**をどれだけもたらすか」を言語化し、上司と共有する。 **2. 優先度マップの作成:** 毎週、目の前にある全ての課題を「重要度」と「緊急度」で分類し、**重要だが緊急ではない課題**(=成長に繋がる課題)に意識的に時間を使う。 |
| **組織のサポートと対話** | 私はあなたの成長を全面的にサポートします。特に来月からは**【暫定目印:具体的なサポートプラン(例:意思決定に焦点を当てた1on1、優先度決定に関するトレーニングなど)】**を定期的に実施します。この文書は対話の出発点です。**【日付】**の面談で、この内容について詳しく話し合いましょう。 |
---
### 文書調整の観点
草稿を最終文書に仕上げる際に、以下の点を意識して調整すると、納得感がさらに高まります。
1. **具体性と事実の連結:**
* **「褒める言葉」**には必ず、収集した**具体的なエピソード**や**データ**を付記する(例:主体性があった $\to$ Aプロジェクトにおいて、期限前に自らマニュアルを作成し、チームのエラー率を〇〇%削減した)。
2. **トーンと一貫性:**
* 全体を通じて、**「期待と信頼」**を示すトーンを保つ。ネガティブな言葉は避け、「課題」を**「成長機会」**や**「次のステージに必要となるスキル」**と言い換える。
3. **アクションの明確さ(S.M.A.R.T.の要素):**
* フィードフォワード部分(行動の提案)が、測定可能で(**M**easurable)、実行可能である(**A**chievable)かを確認する。行動が曖昧だと、フィードバックの効果が薄れてしまいます。
この草案の**【暫定目印】**部分について、補足すべき情報があれば次にお聞かせください。
最小から最大プロンプトのユースケース
今回紹介した以外に、以下のようなユースケースがあるでしょう。
大きめの取り組みの進行計画
- 目的の整理
- ゴールの設定
- ロードマップの作成
- マイルストーンの設定
- 初期の行動計画の作成
フィードバック内容の整理
- SBI法の S で Situation = 状況を整理する
- SBI法の B で Behavior = 行動を整理する
- SBI法の I で Impact = 影響を整理する
- フィードバック全体を確認し、微調整する
SBI法は、Situation/Behavior/Impactの頭文字をとったものです。
これらの要素について、
- Situation - フィードバック対象の状況を伝えること
- Behavior - フィードバック対象の振る舞いを伝えること
- Impact - フィードバック対象の振る舞いがもたらした影響を伝えること
という感じでフィードバックを伝える手法です。
PREP法で説明資料を作成する
- 結論 ( Point ) をまとめる
- 理由 ( Reason ) をまとめる
- 具体例 ( Example ) をまとめる
- 結論 ( Point ) を繰り返し、全体を仕上げる
PREP法は、結論から先に伝え、理由、具体例と続け、最後に再度結論を繰り返すことで、相手に分かりやすく、説得力のある説明をするためのロジック構成フレームワークです。
ブログ記事を執筆する
- テーマを決定する
- アウトラインを決定する
- 各見出しの詳細を作成する
- 全体を推敲する
- 校正・校閲をする