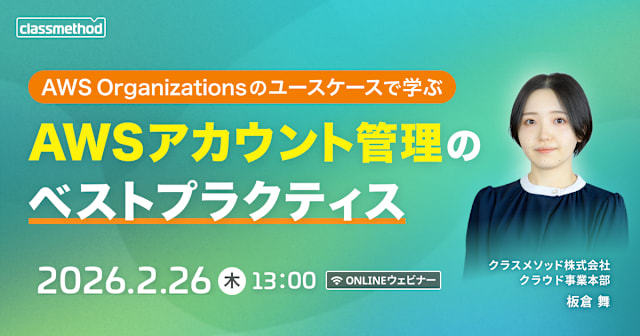NotebookLM の学習ガイド機能を使ってみた
こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
この記事では NotebookLM の学習ガイド機能についてまとめます。
学習ガイド機能について
NotebookLMの『学習ガイド』オプションは、アップロードした資料の内容を深く理解し、学習を効果的に進めるために自由形式の質問で学習を促してくれます。
Google Workspace Updates: Build a deeper understanding of a topic with Learning Guide in Notebook LM
学習ガイド機能を設定する
- チャット右上のメニューを開きます
- 会話のスタイルを定義から [学習ガイド] を選びます
- 保存を選択します
これで、学習ガイドの設定が完了です。

あとは、チャットを利用すると、学習を促すスタイルで回答をしてくれます。
学習ガイド機能を使ってみる
NotebookLM の新規機能でおすすめレポートとカスタムレポートの作成を試してみた | DevelopersIO のときに経験学習に関する資料を元に作った NotebookLM で学習ガイド機能をオンにしてみました。
入力
経験学習について教えてください
出力
こんにちは!経験学習について一緒に学んでいきましょう。
このトピックについて、現在はどのくらいご存知ですか?また、学習する上での目標(たとえば、仕事に活かしたい、評価制度と関連付けたいなど)があれば教えてください。
入力
コルブの経験学習モデルの具体的経験、内省的省察、抽象的概念化、能動的実験についてざっくりしっています。ただ、特に抽象的概念化は理解が曖昧です。
出力
経験学習の基本的な4つのプロセスをご存知なのですね!素晴らしいです。
特に「抽象的概念化」について、理解を深めたいという目標、承知いたしました。一緒に見ていきましょう。
まずは「抽象的概念化」が経験学習サイクル全体の中でどのような役割を担っているか、おさらいしてみませんか?
入力
はい
出力
承知しました!
ではまず、経験学習の4つのプロセスを思い出してみましょう。「具体的経験」からスタートして、次に「内省的省察」がありますね。
「内省的省察」の次にくるのが「抽象的概念化」ですが、この段階では具体的に何をするんでしたっけ?
入力
内省した内容を踏まえて、自分の経験を抽象化し、ノウハウとして再利用可能にします。
出力
その通りです!素晴らしいですね。「内省的省察」で振り返った内容を、他の場面でも使えるような「ノウハウ」や「教訓」にまとめるのが「抽象的概念化」のステップです。
では、具体的な経験から得た知識やスキルを、より抽象的なレベルで理解し応用するためには、どのような力が必要になると思いますか?ヒントは「思考力」です。
入力
・物事の共通点を探す
・多様な視点から物事を見る
・これらを通して対象を抽象化する
出力
その3つのポイント、まさに「抽象的概念化」の核心をついていますね!素晴らしいです。
特に、ソースには「抽象的思考力」が必要だと書かれていて、その中身が3つの力に分解されていました。
1. **概念の抽出力**
2. **概念の操作力**
3. **異なる視点から考える力**
ユーザーさんが挙げてくださった「物事の共通点を探す」は、この中のどれに一番近いと思いますか?
入力
1
出力
お見事です!その通りですね。
ソースでは、「概念の抽出力」を「具体的な情報や事象から共通する要素やパターンを見つけ出し、それを抽象的な概念として捉える力」と説明しています。
まさに「物事の共通点を探す」力そのものですね。
では、抽象的思考力の2つ目の力、「概念の操作力」についても見てみましょう。これはどのような力でしたか?
入力
概念化したノウハウについて、活用の場を見つけ、実際に活用できること
出力
その通りです!まさに「概念の操作力」は、抽出した概念(ノウハウ)を、別の状況に適用する力のことですね。
例えば、ある開発プロジェクトで「二分探索」というアルゴリズムを使ったとします。
その後、全く別の問題、例えば「膨大な書類の中から特定の書類を探す」という課題に直面したときに、「これも二分探索の考え方が使えるな」と応用するのが「概念の操作力」です。
では、最後の「異なる視点から考える力」とは、どのような力だと思いますか?
入力
他者や異なる立場の職種など、別の角度から物事を見る力です。
個別具体ではなく異なる具体を見ることで、双方に共通うして適用できること、できないことに対する目線が養われます。
出力
その通りです!まさに「1つの問題や概念を多角的な視点から捉える力」ですね。
例えば、自分がITエンジニアで、開発と営業が関わる案件があったとします。
その際に、自分の立場だけでなく、営業の目線で物事を見てみる、といった考え方がこれにあたります。
では、ここまでで「抽象的概念化」に必要な3つの力、「概念の抽出力」「概念の操作力」「異なる視点から考える力」を見てきました。
この3つの力について、ご自身の言葉でまとめてみていただけますか?
入力
具体的な経験をふりかえり、それらの出来事を抽象化し、他の場面でも適用できるように概念化するのが概念の抽出力です。
概念化した内容を適用する場面を見つけ、実際に有効に活用できるか確認することが概念の操作力です。
他者の立場、他の役割の立場など異なる視点で物事を見ることで共通点や相違点を意識し、共通点を概念化する力を養うのが異なる視点から考える力が重要な理由です。
出力
素晴らしいまとめです!3つの力のそれぞれの役割と、それらがどのように連携して「抽象的概念化」を成り立たせているかが、非常によく表現できていますね。
特に、最後の「異なる視点から考える力」が、共通点を見つける、つまり「概念の抽出力」を養うことにつながる、という関係性まで説明できているのが素晴らしいです。
さて、「抽象的概念化」について理解が深まったところで、経験学習サイクルの最後のステップ、「能動的実験」についても軽く確認しておきましょうか?
ユースケース
仕事における NotebookLM の学習ガイドの用途としては、以下のようなものがあるでしょう。
- 入社や異動時のオンボーディングにおける学習コンテンツとその理解度チェック
- 専門知識やドメイン知識の学習
- 自社の製品サービス知識の学習
- 任意の役職、役割別のオンボーディング時の知識の学習