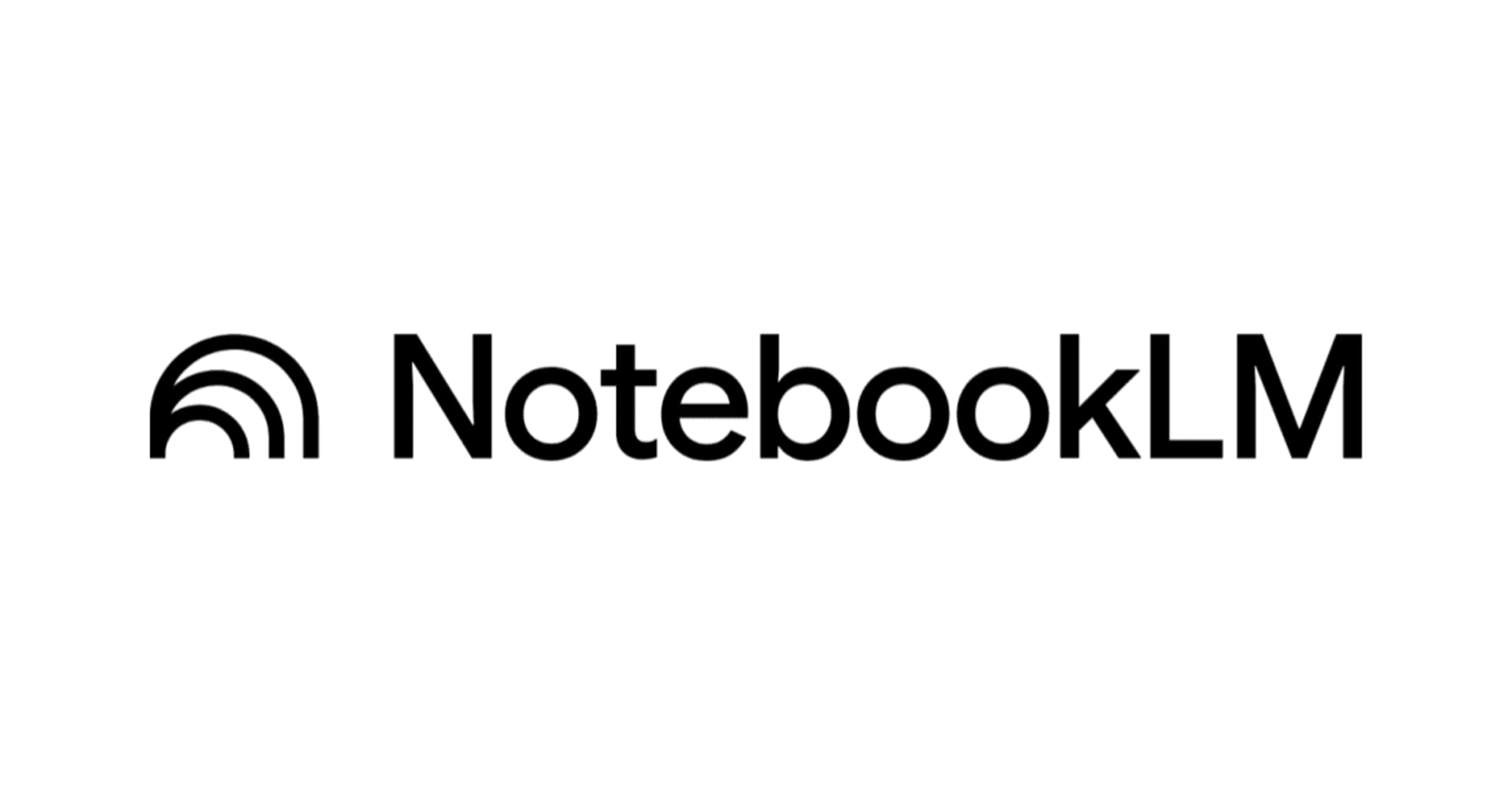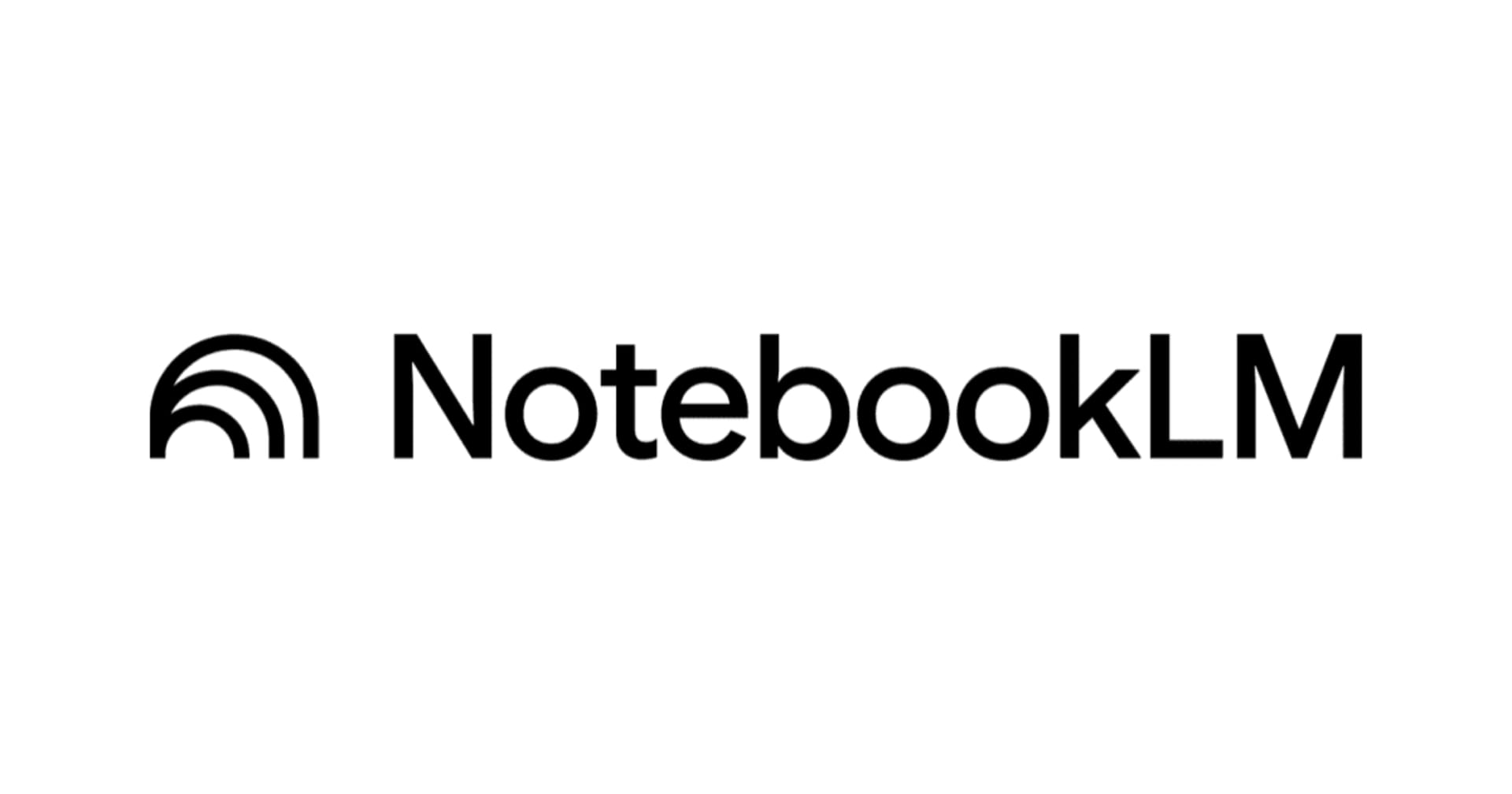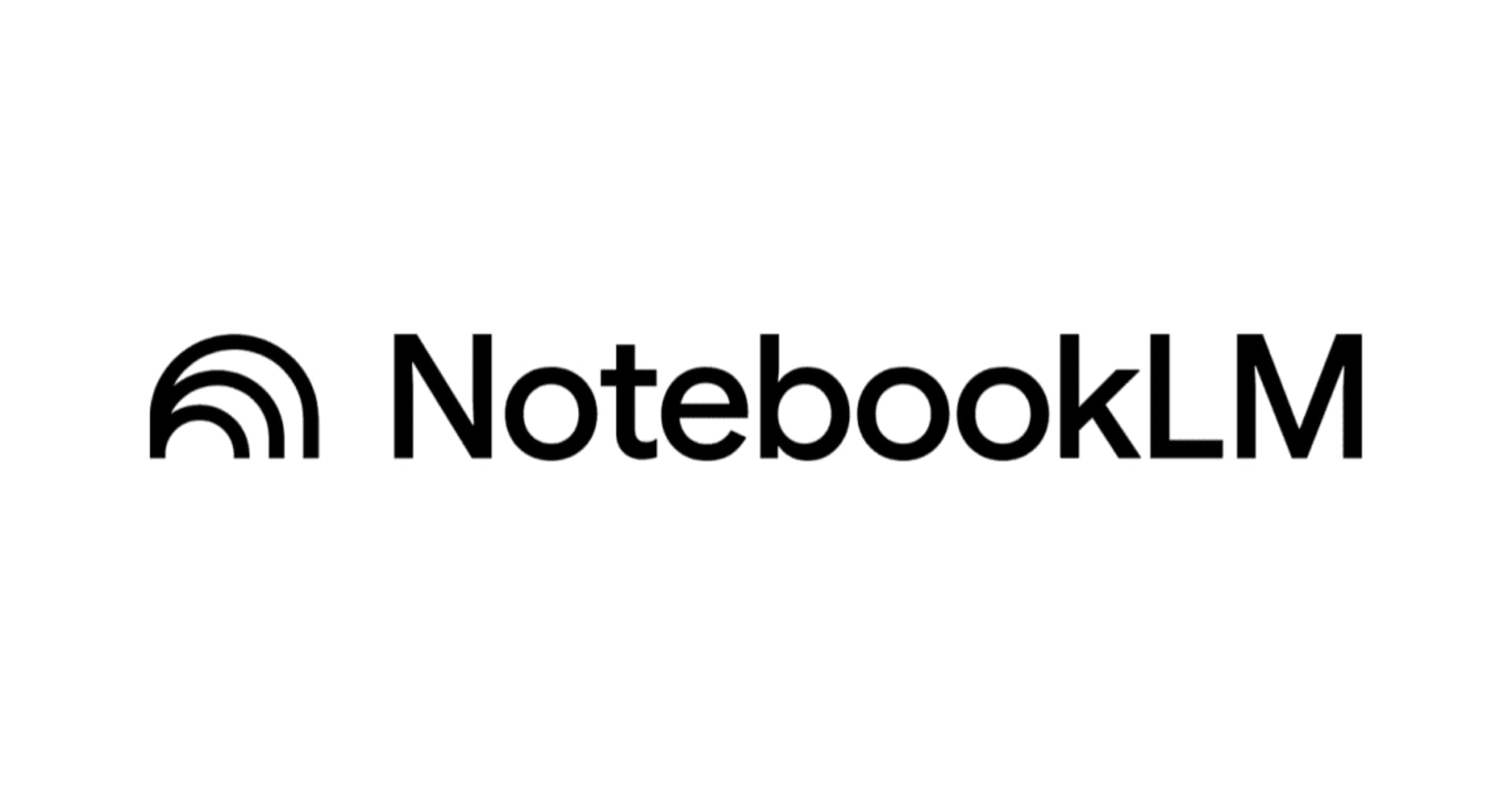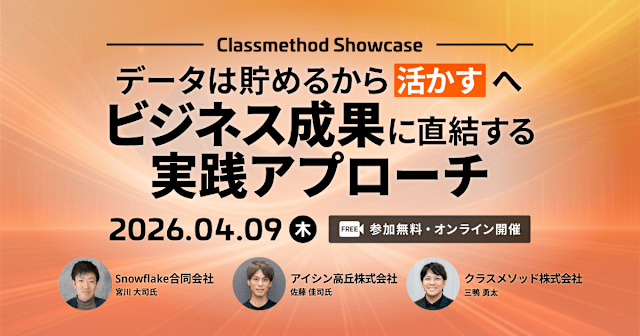待望のリリース!スマートフォンアプリ版NotebookLMを使ってみた
あしざわです。
待望のスマートフォンアプリ版NotebookLMが本日ついに公開されました
(私はXのポストから情報をキャッチしました、ありがとうございます)
このためにGoogle One AI のプレミアムプランを契約していたのは私だけではないはずです。
早速使ってみましたので、その様子を紹介します。
前提
以降の検証の前提となる環境情報はこちらです。
- 検証に利用している端末はAndroid(Google Pixel 9 Pro)です。
- 利用するGoogle アカウントで、Google One AI のプレミアムプランを契約中です。
また、本ブログで紹介するアプリをスマートフォンアプリ版、これまで利用できたブラウザから利用するアプリをWeb版と表現しています。
インストール方法
スマートフォンアプリ版NotebookLMは、Google Play Storeで「NotebookLM」と検索すると出てきます。

Google LLC が提供するアプリであることを確認し、インストールしましょう。
インストールしたアプリを開くとこのような画面になっています。私はGoogle One AI のプレミアムプランを契約しているのでNotebookLM Proが利用できています。

使い方
はじめに、ノートブックを新規作成しましょう。
ソース
ソースとしてPDF/ウェブサイト/YouTube/テキストの4つが利用できるようです。Web版のNotebookLMと比べるとGoogle SlideやGoogle Documentがない点が気になりますね。

ウェブサイトのソースとして、私が以前書いたブログ記事を追加してみました。

ソースを追加すると、このような画面に遷移します。

ソースとして追加したブログは、Web版と同様に文字起こしされて保管されていました(ソースから確認可能)

Web版にあった入力済みのソースを一時的に対象外にする機能は現状利用できないようでした。インポートしているソースすべてが常に利用されるので、対象外にしたい場合はソースを削除する必要がありそうです。

チャット
チャットでこのブログについて聞いてみました。
筆者がコミュニティに関わってよかったと感じていることはなんですか?
Web版と同様な形で入力ソースをベースに返答してくれているようです。

スマートフォン版独自の体験として「いいな」と思った点はソース情報の見やすさです。
Web版だとソースを表す数字をホバーするかクリックするとソースの情報が確認できますが、個人的に読みづらく感じていました。一方、スマートフォン版アプリではソースの数字をタップすると、画面下からソース情報が生えてくるような形です。個人的にはこちらの方が読みやすく感じました。

スタジオ
今回のスマートフォン版アプリ、私の一番の推し機能がこのスタジオです!
スタジオからは、音声概要(Audio Overviews)が生成できます。
ソースに設定しているのは先述したブログの1件のみで、音声生成してみましょう。

生成をクリックしてから、数分(5分程度?)待つと完了しました。この待ち時間はWeb版と同様ですね。なお、NotebookLMアプリをバックグラウンドにしても生成は継続されました。

再生ボタンを押すと、10秒程度のロードの後に音声プレイヤーに遷移し、2名のAIによるポッドキャスト風の音声が日本語で流れ始めました。リリース直後から日本語対応、嬉しいですね。

そして、この音声プレイヤーの体験が素晴らしいです。
シークバー機能、倍速機能(0.5倍/1倍/1.5倍/2倍)、10秒単位の巻き戻し・早送りなど、私が普段動画やラジオを聴く際によく使う機能が充実していて、尚且つUIUXが直感的です。かなり体験が良いなと思いました。
プレーヤーはバックグラウンドでも利用できました。これで通勤中のインプットが捗りそうです。
そして、倍速機能の左側のボタンからは音声概要の共有リンクが生成できます。

リンクをPCに共有して開くと、同じ音声が再生されました。Web版との差分なのかもですが、ロード時間がほぼありませんでした。

三点リーダーボタンから、再生時間の変更や音声ファイル(.wav)のダウンロードもできます。

最後に
この記事では、本日リリースされたスマートフォンアプリ版NotebookLMについて紹介しました。
音声プレーヤーの体験の良さ、音声概要の日本語対応など、リリース直後にも関わらず明日からすぐにでも使いたくなるアプリに仕上がっていると感じました。
明日以降の出勤時間はNotebookLM によるインプットが捗りそうです。
Webアプリ版のソースでは対応していたGoogle SlideとGoogle Documentがスマートフォン版では対応していないところを見ると、ビジネス向けというよりは一般的なユーザーに向けたアプリのように見えます。
今後のアップデート方針も気になりますが、すぐに使えるアプリだと思うので皆で使い倒していきましょう。
以上です。