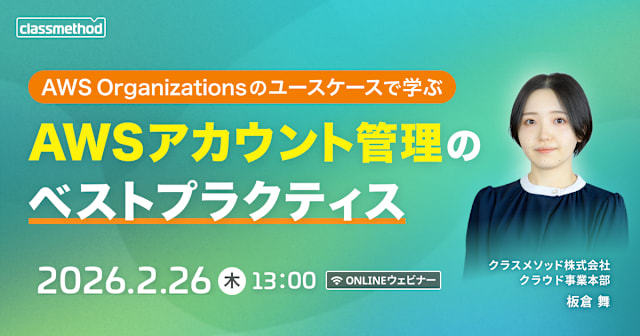![#tableau #data17 [レポート] 地図製作者によるマッピングのヒント – Tableau Conference On Tour 2017 Tokyo](https://devio2023-media.developers.io/wp-content/uploads/2017/04/tc17-tokyo_400x400.png)
#tableau #data17 [レポート] 地図製作者によるマッピングのヒント – Tableau Conference On Tour 2017 Tokyo
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
先日2017/04/18(火)〜2017/04/19(水)の2日間に渡り、ウェスティンホテル東京@恵比寿にて行われたカンファレンスイベント 『Tableau Conference 2017 On Tour Tokyo』。

当エントリでは、イベント1日目(2017/04/18)のテクニカルセッション『地図製作者によるマッピングのヒント』についてその内容をご紹介したいと思います。
目次
セッション情報:概要
事前に公開されていたセッションの概要情報は以下となります。
Speaker: 並木 正之 レベル: 中級者 タイプ: ブレイクアウトセッション 場所: 桜 A
セッション内容レポート

地図作成の基本
- 人間は空間的なパターンを認識する事に慣れている
- 地図のデザインが良ければ空間的なパターンをより速く見つける事が出来る。
- しかし、途中には怪物(落とし穴)が待ち受けている
- 参考資料:元ネタセッション資料作者:Sarah Battersby
- 多くの素材について紹介されており、良いもの/悪いもの/見にくいものなど色々ある。
- Sarah Battersby | Tableau Research
- Sarah Battersby — プロフィール | Tableau Public
-
こんな地図を作らないように...(以下は"悪例")


いつ地図を使用するか
なぜ地図を作成するのか。
- (地図は)見た目が良いから
- 空間データを持っているから
- (地図を)作成出来るから
...間違いです!
答えは...空間的な質問に対する答えを見つける事が出来るから。
例えば、成人肥満率が最も高いのはどの群か?という問。この場合、地図で無くても棒グラフで表現出来てしまえる。

また、既定の設定で最適な地図が出来るとは限らない。少し調整を加えて、関心のあるクラスタをハイライトする。



地図のタイプ
Tableauで、どのタイプの地図を作成するか?→質問とデータによって解答は異なる。地図のタイプを間違うとメッセージが伝わらない事も...
階級区分図(色塗りマップ)

比例記号図
ポイントの位置と属性の意味は慎重に決める。(記号の位置が実際の地表点を表している訳ではないという事に注意)

ポイント分布
ポイントの意味をいつも検討する。

フロー図、パス図

スパイダーマップ
見にくい『クモの巣』を避ける為に、何度も何度もフィルターを適用する

カスタマイズとスタイル作成
直感的な象徴化
- 象徴化は直感的に:
- 手持ちのデータと地図のタイプに合うものは何か?を考えて決める。
- 量的データ(数値):通常、濃色は『より多く』を表すが、ベースマップが暗色の場合は逆にする


- 質的データ(カテゴリ・名前)

- 順序付けされた質的データ(良い/悪い、高/中/低、遅い/速い/より速い):相対的な順序を示す記号を中心に考えて、細かな差異は表さない


- 象徴化で強調する:関連のあるパターンを使うのも面白い

- 象徴化はどの様に役立つか?
- 取水量を示す連続的カラースキーム→わかりやすく分類型カラースキームに変更。


-
カウントには特に注意する:計算フィールドでデータを正規化する
- ちなみにこれは"悪手"。

データ操作
『データの分類』も重要なポイントの1つ。
分類しない
低い値から高い値までの連続的な色の傾斜で表示。見る人は知覚に拠って分類出来る。値間に人為的な『区切り)は無い。

等間隔
データを『ビン』に分類して、視覚的なパターンを簡素化する(n個の明確に異なる色/影)で構成。数値の線の段階は均一であり、分布が途切れている場合は区分を空に出来る。

分類値
各区分に同数の『計算単位)(例:上位20%)。この場合は表計算が必要となる。

分類方法はこんな使い方も出来る。

見やすさに磨きをかける
- 答えを見つけたい質問は何か?
- その地図で答えが見つかるか?
- 他の人も自分と同じように理解出来るか?
- 使いやすいデザインか?飾り付けは最小限に
といった事に気をつけながら、更にVizをブラッシュアップ。
- 背景地図のコンテキストを適切にする
- ベースマップがデータよりも目立たない様に背景のコンテキストを確認。
- マップの外観のカスタマイズ
- データにコンテキストを提供するに足りる最小限のものを表示。
- 強調するのはデータ。ベースマップではない

- 必要なものがない場合、Mapboxタイルを活用する事も出来る。
- Mapbox マップの使用
- Integrate Mapbox with Tableau | Mapbox
- 背景を無くしてみる
- 殆どの人が見慣れている地理の場合、ジオコーディングしたポリゴンだけで表す事を検討
- レイアウトの確認
- 地図を並べて表示する場合、レイアウトが非常に重要。手抜きせず、同じサイズで比較が出来るように調整。

- ツールヒントは役に立ち、使いやすいか?読みやすく、明確な詳細にする
- フィールド名は(他の人にとって)理解しやすいか?
- 含まれるフィールドは理解出来るか?関係の無い情報は一切含めない
- 伝える必要がある情報をどの形式で表示すると良いか?
- 表
- テキスト
- 書式設定で階層を作り、見る人を正確な情報にすばやく導く
-
色には統一感があるか?
- 地図とビューで一貫性のあるサイズと色
- 全てのオブジェクトに統一されたデザイン
- カラーコーディネーションの『失敗例』
- 1つのダッシュボードに2つの地図、同じ色味
- 属性は関連しているが色の傾斜は異なる
- それぞれの地図で色は異なる意味を持つ
- 比較には向いていない!
セッションまとめ
- なぜ地図を作成するのか?空間的な質問に対する答えを見つける事ができるから。
- 既定の地図がいつも最善というわけではない
- 評価し、磨きをかける
- 他の人も自分と同じように理解できるか?
- 使いやすいデザインか
まとめ
という訳で『地図製作者によるマッピングのヒント』に関するセッション内容のご紹介でした。地図で情報を可視化するというのは強力な道具である一方、やり方によっては情報を間違って伝えてしまい兼ねません。当セッションの内容を正しく理解してViz作成に役立てて行きたいところですね。