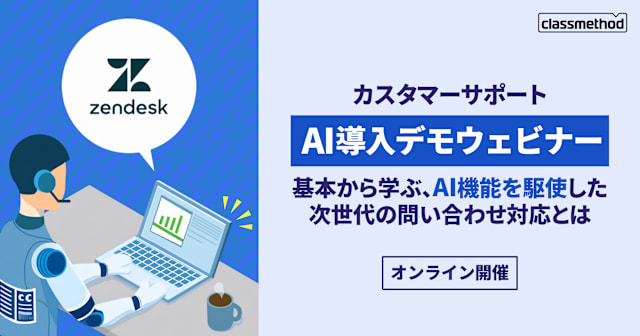社外情報の共有力を高める3つのポイント
こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
社外の情報を共有する方法は人によって様々で、URLだけを渡す場合もあれば、補足コメントを添える場合もあります。この記事では、社外の情報を共有する際に、伝達の質を上げるためのポイントをまとめます。
情報共有の質を上げるポイント
情報共有をする際に、以下のようなポイントを押さえるとより効果的です。
- 共有の意図を添える
- 共有したい部分を明示する
- アクションを明示する
1. 共有の意図を添える
情報を共有する意図を端的に添えます。
共有の目的の典型例として以下の3つがあるでしょう。
- 共有内容を実際の業務に取り入れてもらいたい
- すぐに業務に取り入れる必要はないが、知識として関係者全員に知ってもらいたい
- 業務に取り入れる予定はないし、必読ではないが興味がある人のみ読んでもらいたい
2. 共有したい部分を明示する
共有する情報のボリュームが大きく、全体ではなく一部だけを伝えたい場合は、その部分を明示することが重要です。そうすることで、受け手は最小限の時間で必要な情報を把握できます。
3. アクションを明示する
「この情報を踏まえて〇〇を検討してほしい」など、次にどうしてほしいかを明示すると、共有後のコミュニケーションがスムーズになります。
逆にいうとアクションを明示しない場合、期待するアクションとは異なる行動を生む可能性があります。特に、立場がある人が情報を共有すると事実上の指示とみなされる可能性があります。共有の意図を添えつつ、アクションを求める場合は明示し、特に求めない場合は共有の意図を確認すれば、アクションが不要であることが明確に伝わるようにしましょう。
気をつけるポイント
社外からの情報を共有する上で気をつけるポイントとして以下の3つを紹介します。
- 適切な情報量と頻度にする
- 異論を暗黙的に伝える
- ターゲット外の人を巻き込まない
1. 適切な情報量と頻度にする
情報共有は、業務に役立ってこそ有益で、他の業務と同様にROIがあります。共有した情報は、関係者が内容を確認する時間を必要とします。そして、内容を確認し、実務に活用して生まれるメリットよりもコストが小さくなる必要があります。
そういった点を加味して、重要な情報を理解や活用に必要な最小限の量で共有したり、頻度も他の業務で使う時間を踏まえて消化しきれる程度の量に抑える必要があります。重要度が低めの情報を頻繁に共有しすぎると、周囲が処理しきれず、社外からの情報が共有された際に見過ごされるケースが増えていきます。結果として特に重要な情報もスルーされやすくなってしまいます。
2. 異論を暗黙的に伝える
異論を伝える手段として社外の取り組みの情報を共有する場合に、異論であることや現状の課題については何も触れずに情報のみを共有する場合があります。こういった場合、異論が通るような形で話が進むことは稀で、場合によっては組織批判と受け取られる可能性もあるため、現状の課題を明示し、それに対する解決策として提案しているということを明示的・建設的に伝える必要があります。
3. ターゲット外の人を巻き込まない
情報を読むかどうか取捨選択するのにも多少の時間がかかり、実際に内容を読むのにも時間がかかります。読んだ結果自分の業務にはあまり影響のない内容だった場合、時間を使っただけになります。
そのため、情報を共有する場合、明らかにその情報の活用に関わる範囲に共有することで、他の人達の時間や集中力を奪わないようにするとよいでしょう。