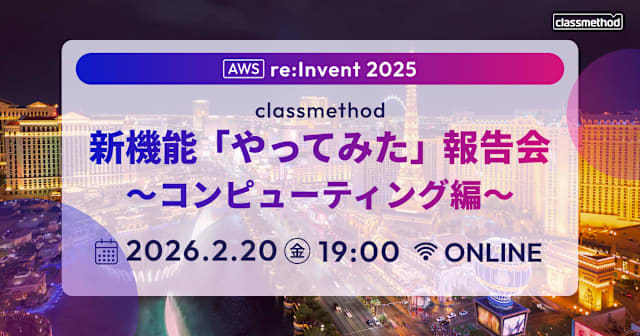生成AIに複雑なタスクに関する指示をするために必要となる問題の構造化
こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
昨今、 Gemini をはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、業務の効率化や新たなアイデア創出に欠かせないツールとなりつつあります。しかし、「思ったような回答が返ってこない」と感じたことはありませんか?
その原因の多くは、AIへの指示の与え方にあります。
この記事では、AIの能力を最大限に引き出すために不可欠なテクニック、プロンプトのための問題の構造化について、まとめます。
問題の構造化の判断
プロンプトを構造化すべきか、それとも簡単な一文の指示で済ませて良いか。この判断は、タスクの性質によって決まります。
シンプルな依頼で十分なケース
以下のような依頼内容の場合、シンプルな指示で十分です。
- タスクのシンプルさ : 一つの動詞で完了する単純なタスク(例:要約、翻訳、一般的なアイデア出し)
- 形式の自由度 : 出力形式に厳密な指定がなく、一般的な文章や箇条書きで問題ない場合
たとえば、以下のような依頼ならシンプルな指示で十分です。
入力
認知バイアスについて、200文字程度で説明してください
出力
認知バイアスとは、過去の経験や先入観、直感などに基づき、物事を非合理的・非客観的に判断してしまう、人間の思考の偏りや歪みのことです。
脳が大量の情報を効率的に処理しようとする過程で生じるもので、誰もが持つ思考の「クセ」といえます。
このバイアスが、誤った意思決定や偏見の原因となることがあります。
* 例: 自分の意見に合う情報ばかりを集める確証バイアスや、特定の良い点から全体を高く評価してしまうハロー効果など、多くの種類があります。
構造化が必要なケース
以下のような依頼内容の場合、後続化が必要です。
- タスクの複雑さ : 複数の手順、論理的な流れ、複数の情報源の考慮が必要な場合
- 出力の厳密さ : 文字数、トーン、特定の構成要素など、細かい制約やルールがある場合
- 役割の指定 : AIに特定領域の専門家・初心といった役割を与えたい場合
問題の構造化
プロンプトを構造化することは、AIにとって必要な情報を整理し、明確なセクションに分けて提示することです。
そして、構造化されたプロンプトを作成するためには、対象の問題を構造化する必要があります。
主な構成要素とその概要は以下の通りです。
プロンプトの基本構成要素
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 指示 | AIに何を実行してほしいかを具体的に示す核となる命令 |
| 役割 | AIがどのような立場や視点でタスクに取り組むかを指定し、出力の質を高める |
| 文脈 | タスクの前提となる状況を提供し、AIの理解を深める |
| 制約 | 出力の形式、長さ、トーン、禁止事項など、満たすべきルールを設定する |
| 入力データ | AIが処理・参照すべき具体的なデータやテキスト |
| 出力形式 | 最終的な回答をどのような形式(箇条書き、表、JSONなど)で返してほしいかを指示する |
プロンプトの基本構成要素の詳細
| 項目 | 詳細な設定・説明 |
|---|---|
| 指示 | 「〇〇をしてください」と明確に動詞で指示し、曖昧な言葉(例:「適当に」「たくさん」)を避ける |
| 役割 | 「あなたは〇〇です」と役割を設定することで、AIの知識や表現力を特定の専門家に寄せることができます |
| 文脈 | 『ターゲット読者は誰か』『なぜこのタスクが必要なのか』など、AIがタスクの意図を理解するための情報を与えます |
| 制約 | プロンプトの品質を担保する最も重要な要素。『300字以内』『ネガティブな表現は禁止』など、具体的なルールを提示します。 |
| 入力データ | 参照データと指示文を混同させないよう、「---入力データ---」などの区切り文字を使って明確に区別することが推奨されます |
| 出力形式 | 「Markdownの表形式で」「導入、本論、結論の構成で」など、受け取り側の使いやすさを考慮した形式を指定することで、納品物のクオリティが統一されます |
サンプル
構造化していないケース
入力
Account Based Recruiting を実現する方法
出力
大雑把な指示の割にはそこそこの回答が得られましたが、ターゲットの設定の段階で、リストアップ対象がズレています。ABMの場合は企業単位でよいですが、ABRの場合は個人単位で考える必要があり、誤った前提のまま後続の分析を続けているため分析結果全体の価値が下がっています。
Account Based Recruiting (アカウントベースド・リクルーティング、ABR) は、Account Based Marketing (アカウントベースド・マーケティング、ABM) の考え方を採用活動に応用した戦略的な手法です。
特定のターゲット企業や人材に焦点を絞り、パーソナライズされたアプローチを行うことで、従来の採用手法よりも効率的かつ効果的に優秀な人材を獲得することを目指します。
ABMの実践ステップを参考にすると、ABRを実現するための主なステップは以下の通りです。
### 🚀 ABR(アカウントベースド・リクルーティング)を実現するステップ
#### 1. 🎯 ターゲットの設定(アカウント選定)
* 事業目標との連携: 採用が事業目標達成に最も貢献する部門や職種を特定します。
* ターゲット企業のリストアップ: 自社にとって重要度が高く、採用難易度が高い、あるいは競合となる企業をターゲットアカウントとしてリストアップします。
* 例: 特定の技術を持つエンジニアが多く在籍する企業、自社のビジネスモデルと類似性の高い企業など。
* ターゲット人材の明確化: ターゲット企業に在籍する求める人材像(ペルソナ)を具体的に定義します。職種、スキル、経験、役職などを明確にします。
#### 2. 🔍 ターゲットの調査・分析
* インサイトの収集: ターゲット企業やターゲット人材に関する詳細な情報(企業文化、組織図、事業の課題、キャリアパス、関心事、転職理由となりうる要素など)を多角的に収集し、分析します。
* 公開情報(Webサイト、ニュース、SNS)、業界レポート、社員からのヒアリングなどを活用します。
* キーパーソンの特定: ターゲット人材に影響を与える意思決定者やインフルエンサーを特定します。
#### 3. 📝 パーソナライズされたメッセージ・コンテンツの作成
* バリュープロポジションの明確化: 自社で働くことの独自の価値(競合他社にはない魅力)を、ターゲット人材のニーズや課題に合わせて明確にします。
* 個別化されたアプローチ戦略: 収集したインサイトに基づき、ターゲット企業・人材一人ひとりに響くパーソナライズされたメッセージやコンテンツを作成します。
* 例: ターゲット企業の事業課題解決に貢献できる具体的なポジションの提示、特定のスキルを活かせるプロジェクトの紹介など。
#### 4. 📢 マルチチャネルでのアプローチ
* チャネルの選定: ターゲット人材が接触しやすい複数のチャネル(ビジネスSNS、ダイレクトリクルーティング、リファラル、イベント、Web広告など)を組み合わせてアプローチを実行します。
* 一貫した体験(Account Based Experience: ABX)の提供: どのチャネルで接触しても、ターゲット人材に対して一貫性のあるメッセージと体験を提供します。
#### 5. 🤝 部門間の連携強化(採用部門と事業部門)
* 採用チームの構築: 人事・採用担当者だけでなく、事業部門のマネージャーや現場社員を巻き込んだABRチームを構築し、目標と戦略を共有します。
* 共同での実行: 特にパーソナライズされたメッセージ作成や、ターゲット人材との初期接触において、事業部門の専門知識やネットワークを最大限に活用します。
#### 6. 📈 効果測定と改善(PDCA)
* KPIの設定と測定: 採用単価や期間だけでなく、ターゲットアカウントとのエンゲージメント度やアプローチの反応率など、ABR特有の指標を設定し、効果を測定します。
* フィードバックと最適化: 実行結果を分析し、ターゲットリスト、メッセージ、アプローチチャネルなどを継続的に改善していきます。
この戦略的なアプローチにより、「誰でもいいから採用する」から「事業成長に不可欠な特定の人材を口説き落とす」という、より質の高い採用活動が可能になります。
---
さらに、ABRを成功させるための具体的なツールや具体的なアプローチ手法について掘り下げますか?**
構造化しているケース
入力
# 役割
あなたは、マーケティング出身の採用人事の専門家です。外資企業で Account Based Marketing を経験し、それを応用して Account Based Recruiting を実践した経験を持っています。
# 文脈
日本のITエンジニア採用市場は売り手市場であり、企業が採用をするためには多数の候補者にアクションをとる必要があります。
また、その影響でそもそも転職顕在層が少なく、優秀な人ほど現職で活躍している転職潜在層です。優秀な人材が必要なら、現職中の段階からアプローチを取ることが必要です。
一方、慣習的に日本の採用市場は母集団形成を元に、大量の候補者を集め、大量にスカウト・応募を集め、その中から厳選していくアプローチが主流です。この手法は、本来採用しない人に多大な時間を割く採用手法で非効率です。
昨今、ITエンジニアにおいては個人の活動や成果を情報発信する人が増えています。また、生成AIの登場で発信する側、発信を見つける側のハードルは更に下がっています。これを踏まえて、 Account Based Recruiting を実現するハードルも下がってきています。
# 指示
Account Based Recruiting(ABR) を用いて採用するために必要な取り組みをステップを分けて説明してください。
# 制約
Account Based Marketing においては、企業を対象にターゲットを定めますが、 Account Based Recruiting においては個人がターゲットが好ましいと考えています。これを踏まえて方法を検討してください。
# 出力フォーマット
{ABR の取組方針の概要}
## ABR の前提
{ABR を実施する企業に必要な前提があれば、それを説明してください。たとえば、競争力のある EVP があること、など}
## ABR の実施ステップ
### ステップ1
{ABR の実施ステップ1の説明}
### ステップ2
{ABR の実施ステップ2の説明}
### ステップn
{ABR の実施ステップnの説明}
## ABR を実施する際のポイント
{ABR を実施する際のポイントを箇条書きで記載する}
出力
今度は、対象を個人に絞った対策方法を出力してくれています。また、前提・ステップ・ポイントを区別してわかりやすく出力してもらいました。
なお、今回はあくまでプロンプトの検証が目的のため省略していますが、個人情報の扱いについて掘り下げて検討する余地があるでしょう。
ご依頼ありがとうございます。マーケティング出身の採用人事の専門家として、Account Based Marketing (ABM) の知見を応用した Account Based Recruiting (ABR) の取り組みについて、ステップ形式でご説明します。
日本のITエンジニア採用市場の現状を踏まえ、「大量の候補者へのアプローチ」から「採用したい個人への精度の高いアプローチ」への転換を目的としたABRのアプローチは極めて有効と考えます。
---
# Account Based Recruiting (ABR) の取組方針の概要
ABRは、従来の「母集団形成型」の採用アプローチと異なり、「ターゲットを絞り込み、個人の特性・ニーズに合わせた最高水準の体験を提供する」ことを目指す戦略的アプローチです。
採用ターゲットとなる個人(Account)を明確に定義し、その個人に対してカスタマイズされたコミュニケーションと価値提供を行うことで、転職潜在層である優秀なエンジニアのエンゲージメントを高め、自社への興味・入社意欲を醸成します。
特にITエンジニアのように情報発信が活発な層に対しては、その発信内容や活動実績を深く分析することで、効果的かつ非線形なアプローチが可能になります。
## ABR の前提
ABRを成功させるためには、以下の競争力の源泉となる前提条件が不可欠です。
* 競争力のあるEVP (Employee Value Proposition) の確立と浸透:
* 自社で働くことの独自の価値、エンジニアのキャリア成長、技術的挑戦の機会、文化などを明確にし、競合他社に勝る「選ばれる理由」を具体的に言語化・社内外に浸透させていること。
* パーソナライズされた体験を提供する体制:
* 採用活動が単なる「選考」ではなく、「個人に合わせた情報提供と対話の機会」となるよう、採用担当者、現場エンジニア、経営層が一貫性のあるパーソナライズされたアプローチを設計・実行できる体制とスキル(特にコミュニケーション、インサイト分析スキル)を有していること。
* 長期的なエンゲージメントを評価する指標設定:
* 短期的な応募数ではなく、「ターゲットリストへのリーチ率」「エンゲージメントレベル(コンタクト頻度、コンテンツ閲覧、イベント参加など)」「関係構築にかかった期間」といった、関係構築の質と長期的な成果を評価するKPIを設定すること。
## ABR の実施ステップ
### ステップ1:💡ハイバリューなターゲット個人の特定と深度あるインサイト分析
1. 採用要件の再定義とターゲットリストの作成:
* 充足したいポジションを明確にし、そのポジションに「最適」な個人(企業ではない)の属性(保有スキル、経験年数、現職企業、活動領域)を定義します。
* この要件に基づき、GitHub、技術ブログ、SNS、カンファレンス登壇、OSS貢献などのオープンな情報源から、具体的な個人名を伴うターゲットリスト(理想的なAccountリスト)を作成します。
2. インサイト(深層的な関心)の徹底的な分析:
* 特定した個人が「今、何に情熱を注いでいるか」「現職で抱えているであろう課題」「どのような技術課題に関心があるか」「キャリアの次に望むこと」といった、表面的なスキル以外の深層的な動機やニーズを、発信情報から徹底的に分析します。
* (例: 特定のOSSへのコントリビュートに熱心であれば、その技術分野の課題解決が動機であり、自社のその分野での挑戦が響く可能性が高い)
### ステップ2:🎯パーソナライズされた価値提供コンテンツの設計
1. ターゲットのインサイトに基づいたメッセージとコンテンツの作成:
* ステップ1で得られたインサイトに基づき、ターゲット個人だけに響く、カスタマイズされた「提供価値(オファー)」を設計します。
* コンテンツ例:
* ターゲットのGitHubでの活動に言及した、個別性の高いスカウトメッセージ。
* ターゲットが関心を持つ技術分野の、自社の具体的な課題や解決事例を紹介する非公開資料への招待。
* ターゲットが使用する技術スタックの自社現場エンジニアとの1on1対話(選考ではないカジュアル面談)の機会。
* ターゲットのブログ記事や登壇内容への具体的なフィードバックや共感を示すコメント。
2. オムニチャネル・デリバリー戦略の策定:
* ターゲットが最も情報を消費しているチャネル(SNS、GitHub、技術コミュニティ、メールなど)を特定し、設計したコンテンツを最も効果的なタイミングと方法で届けるための戦略を策定します。
### ステップ3:🤝関係性の構築とエンゲージメントの深化
1. 非選考ベースの初期アプローチと対話の開始:
* 作成したメッセージを元に、まずは「採用」を全面に出さず、「価値交換」や「技術的な対話」を目的としたアプローチを開始します。
* (例:「あなたの〇〇に関する考えに共感した。当社の〇〇の課題について、ぜひあなたの知見を伺いたい」といったプロフェッショナルな対話の切り口)
2. エンゲージメントレベルに応じた継続的なフォローアップ:
* 対話が始まった後も、一方的な情報提供ではなく、定期的にターゲットの活動をチェックし、関心の変化や新たな発信に合わせて、次に提供する価値やコンテンツを調整し続けます(リターゲティングとナーチャリングの概念)。
* これにより、ターゲット個人にとって、自社が「自分を深く理解し、価値を提供してくれるパートナー」という認知へと昇華させます。
### ステップ4:✅オファーとクロージングのカスタマイズ
1. キャリアパスのカスタマイズ提案:
* 関係構築のプロセスで明らかになった個人の長期的なキャリア目標、希望する技術領域、働き方などを最大限考慮し、単なる既存のポジションへの当てはめではなく、その個人に合わせた独自の挑戦環境や役割を提案します。
2. 意思決定のサポートと懸念点の払拭:
* オファー後の意思決定プロセスにおいても、ターゲット個人の不安や懸念(現職への義理、家族の理解など)に対して、個別のサポートや情報提供を行います。現場エンジニアや経営層が直接、個人に合わせたクロージングを行うことで、入社への意欲を決定づけます。
---
## ABR を実施する際のポイント
* 部門連携の徹底: 採用担当者と現場エンジニア(特にターゲットの専門分野に近いエンジニア)が一体となってアプローチを設計・実行する。これは「営業とマーケティングの連携(Smarketing)」と同じ概念です。
* 定性的な成果を重視: 初期段階では「面接に進んだ人数」よりも、「ターゲット個人との有意義な対話が成立した数」「ターゲットからの具体的なフィードバックが得られた数」といった、関係構築の質を重視する。
* 技術的敬意と誠実性: 候補者個人の発信や活動への言及は、表面的な称賛ではなく、技術的な背景や貢献度への深い理解と誠実な敬意をもって行う。これが欠けると、マーケティング的なアプローチが「浅いスカウト」と見なされ、逆効果となる。
* CRM/ATSの活用: ターゲット個人のインサイト、アプローチ履歴、エンゲージメントレベルを詳細に記録・管理できるシステム(採用CRMや高度なATS)を導入し、パーソナライズの精度と継続性を高める。
* 「選ばれる」姿勢の徹底: 売り手市場において、企業は常に「なぜ貴社で働くべきか」を個人の視点に合わせて説明し続けなければならない。ABRは、その「選ばれる」ための戦略的な努力そのものである。
---
ご興味をお持ちいただけましたら、このステップの具体的な実行計画や、貴社のEVP(社員価値提案)をABRにどう活かすかについて、さらに掘り下げてご提案できます。
まとめ
今回生成AIに指示を出すための構造化を紹介しましたが、実はAIの利用有無にかかわらず仕事をするうえで重要な要素です。
- 難しい業務を人に依頼する際に、取り組む対象を構造化できているか?
- 構造化したうえで、相手が理解できる情報量で伝えることができているか?
- 口頭だけではなく、記録され、見返して確認できる形で伝えているか?
- 他人に業務を依頼されるとき、この構造の要素に不足があれば、質問で引き出すことができているか?