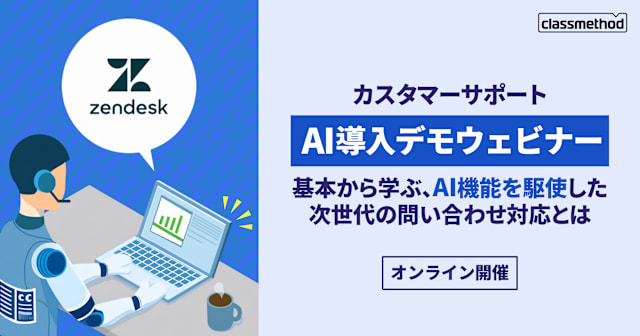評価フィードバックを活用すること
こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
人事評価制度を導入している会社では、多くの場合、評価結果を共有するためのフィードバック面談が行われます。この記事では、評価される側が評価フィードバックを活用する方法についてまとめます。
ターゲット
この記事は、評価フィードバックを受ける本人をターゲットにしています。
評価フィードバックをするマネージャー向けの情報は以下にまとめたので、マネージャーの方は以下の記事を参照ください。
評価フィードバックとは
評価フィードバックとは、評価者が対象者に評価結果を伝えることです。
評価フィードバックは、以下の3つの目的で実施されます。
- 評価の結果を伝えること
- 今後のパフォーマンス向上のために認識を合わせること
- 今後の活躍のためにモチベートすること
評価フィードバックの活用方法
評価フィードバックを受ける側からみた場合の活用方法には以下の3つがあります。
- 評価の理由の確認
- ギャップの把握
- 次の評価期間の準備
1. 評価の理由の確認
評価の結果は、据え置き・一定の昇給・グレードの昇格など、色々な結果がありえます。どの結果であったとしても、その評価になった根拠を確認しましょう。マネージャーが丁寧に説明してくれる場合は、こちらから聞かなくても必要な情報を確認できるかもしれませんが、すべてのマネージャーが十分な情報を伝えてくれるとは限らないため、必要に応じて自分から確認できるよう準備しておきましょう。
昇格や昇給した場合、影響した実績や行動を確認しましょう。また、自分では大きな貢献だと思っていたものが昇格や昇給の理由に含まれていなかった場合、その取り組みの重要性がなぜ大きくないのかを確認しましょう。
2. ギャップの把握
評価の結果が自己評価とギャップがあった場合、ギャップの根拠を確認しましょう。
自己評価が控えめすぎた可能性を認識し、その差分を確認して理解しましょう。逆に、自己評価が高すぎた場合についても、その差分を確認しましょう。特に心情的に受け入れにくいのは後者のケースで、ついつい「自分の評価を正しくできないマネージャーが悪い」という解釈をしがちです。一方で、会社における評価はマネージャーがするものであり、自分自身でするものではないため、あくまでマネージャーの考えを基本として、組織の成果として評価に必要とするものがずれていたのか、不足していたか、成果を出していたがマネージャーに伝わっていなかったと捉え、どの原因だったかによって対策をする方向で検討するのが建設的です。
なお、人の考え方や振る舞いにまつわる評価上の減点要素はマネージャーも率直に伝えにくい部分があり、本当は問題があるにも関わらず伝えられない場合があります。自分から率直に問題点を教えてほしいと伝えることで、マネージャーがフィードバックしやすくなる場合もあります。業務上の成果だけを見ると評価が上がるようにみえるにも関わらず、継続的に評価が上がらない場合、マネージャーから伝えにくい問題点が裏に潜んでいる場合があります。
3. 次の評価期間の準備
評価の根拠を確認し、ギャップも確認できたら、それに加えて来年度に向けた課題や期待を確認することが次の評価期間の活動を始めるためのインプットになります。特に、グレードが上がった場合は求められる責任範囲や期待値が大きく変化するため、これまでと比べて、どのような変化や新たな期待があるのかを確認しておきましょう。