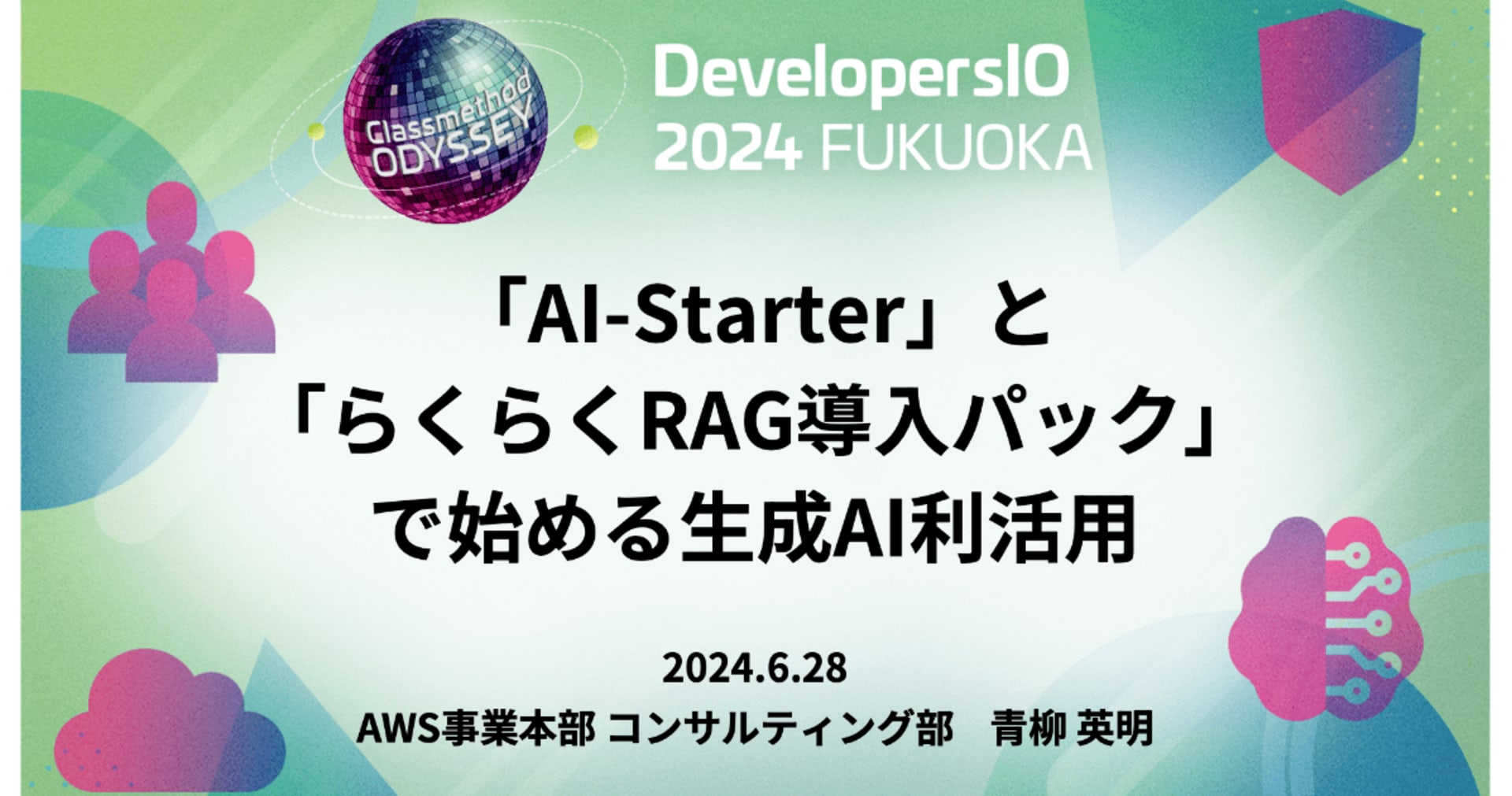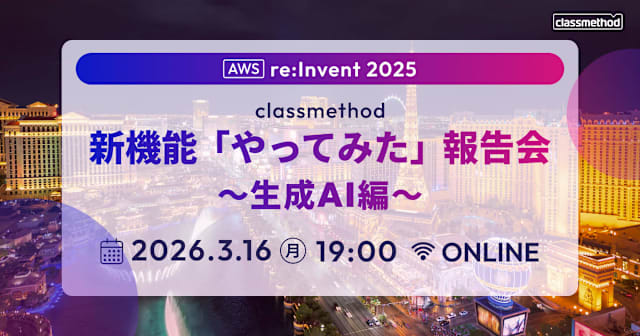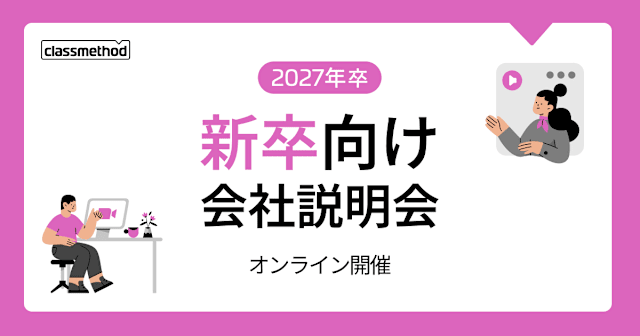生成AI専門の営業が見た「導入が進む企業」の共通点とその理由
こんにちは、洲崎です。
本日、2025年7月7日はクラスメソッドの創立22周年記念日です。
今回は、私自身が日々の業務を通じて肌で感じている「生成AIの現状」について書いてみたいと思います。
この記事では、いわゆる全社導入などにおける、一般ユーザー向けの生成AI活用について取り上げます。
開発者向けの技術的な活用(AI駆動開発)とは異なる視点となりますので、あらかじめご了承ください。
最初に自己紹介
私はもともとAWSの営業職としてクラスメソッドに入社し、その後AWSエンジニアを経て、現在は新規事業統括部で生成AI関連のビジネスを担当しています。
技術とビジネスの両面から、企業の生成AI活用を支援しています。
これまでのキャリアや活動にご興味のある方は、以下の記事もぜひご覧ください。
生成AIの現状
現在、生成AIは一部の企業ではすでに当たり前のように業務で活用され始めています。
一方で、これから導入を検討している企業では、以下のような相談をよくいただきます。
- どこから始めればよいのか
- 導入にかかるコストと効果のバランス(費用対効果)をどう考えるべきか
- セキュリティや情報漏洩のリスク(シャドーITなど)の懸念
生成AIは非常に急速に進化している分野であり、まだ発展途上にあります。
技術やユースケース、ベストプラクティスが日々アップデートされており、良い意味で「カオス」な状況とも言えます。
こうした中で最も重要なことは、情報に振り回されすぎずに、企業ごとに活用方法を模索し、試行錯誤しながら価値を創出していくことが大切です。
導入されている企業の特徴
クラスメソッドでは、これまでに40社以上の生成AI導入プロジェクトを支援してきました。
その中で、導入がうまく進んでいる企業にはいくつかの特徴があると感じたので、事例も踏まえてご紹介します。
1. 経営層が生成AIの価値を理解している
まず大きなポイントは、経営層が生成AIの可能性を正しく理解し推進していることです。
クラスメソッドの支援事例で言えば、コクヨ様の取り組みがこれに該当します。
コクヨ様では、デジタル人材の育成と実践を目的とした「KOKUYO DIGITAL ACADEMY」というプログラムを展開されています。
このアカデミーの体制には、コクヨ様の経営層の方が積極的に関わっています。
その中の取り組みの一つである「GPT-Lab」という取り組みでは、非エンジニアの社員の方々が生成AIを活用した業務アプリを自ら開発し、プロトタイプを完成させたうえで成果発表会まで実施されています。
クラスメソッドは、この取り組みにおいて技術面での伴走支援を行っています。
2. DX推進などの専任チームが存在する
経営層の理解に加えて、DX推進部門などの専任チームが存在することで、生成AIの導入から運用までがスムーズに進みます。
生成AIは「導入して終わり」ではなく、継続的な利用推進や改善が求められます。
たとえば、三井住友トラストクラブ様の事例では、弊社の「AI Starter」の導入に加え、生成AIワークショップの実施までを一貫してご支援させていただきました。
導入後、日常業務への活用を社内に浸透させていくためには、利用促進を担うチームの存在が重要です。
こうした体制があることで、組織全体としての活用がより加速します。
3. 業務上の課題やボトルネックを把握している
生成AIの導入は、特定の業務や部署に絞ってスモールスタートすることも成功の鍵といえます。
たとえば、第一興商様では、コールセンター業務における音声要約の自動化に取り組まれています。
コールセンターの対応後の事務作業の作業負荷や、記録内容の品質のばらつきを生成AIで自動化した事例になります。
事前に業務上の課題やボトルネックが明確になっていると、生成AIの効果を実感しやすく、導入後の成果にもつながりやすくなります。
4. 生成AIの特徴を理解し、段階的な精度向上を前提としている
生成AIは万能ではなく、「ハルシネーション(事実と異なる内容を生成する現象)」が発生することもあります。
そのため、最初から100%の正確性を求めるのではなく、段階的に精度を高めていく前提で取り組むことが重要です。
たとえば、RAGを活用する場合でも、社内データの構造や整備状況によって精度が大きく左右されます。
PSソリューションズ様の事例では、初期段階では40%程度の精度だったものが、改善を重ねることで80〜90%まで向上しました。
今後の展望
現在、生成AIの活用においては、LLMやRAGを活用したチャットボットが、ニーズの明確さや検証のしやすさから多くのプロジェクトで採用されています。
一方で、「生成AIをさらに先進的に活用したい」という要望も増えてきており、今後はより高度なユースケースへの展開が期待されます。
ここでは、そうした次のステップとしての展望をいくつかご紹介します。
AGIについて(個人的所感)
AGIとは、人間のように幅広い知的作業を自律的にこなせるAIを指します。
個人的には、AGIがすぐに人間にとって代わるという考えには少し慎重です。
現状では、生成AIは人間を「置き換える」ものではなく、有能な「アシスタント」や「バディ」として業務をサポートする存在として捉える方が、現状は生成AI活用の道が広がると考えています。
AIエージェント、MCPの活用
AIエージェントやMCPの活用は、RAGよりもさらに難易度が高くなります。
また、生成AIに100%の正確性を求めるのは依然として困難です。
たとえば、コールセンターで宿泊予約をエージェントで実装し自動化したい場合、技術的にはある程度実装することは可能です。
しかし、以下のような観点での検討が必要になります。
- 予約、キャンセル、変更などをどこまで自動化(AIに任せる)するか
- 不正予約や誤キャンセルをどう防ぐか
- どのタイミングで人が介在すべきか
業務プロセスをAIエージェントに任せるには、従来とは異なる視点での設計が求められます。
一方、あまりにもワークフローを作り込みすぎると、それは従来のワークフローシステムと大差がなくなり、生成AIならではの価値を活かしきれない可能性もあります。
こうした高度な取り組みは、生成AIの活用がある程度進み、「もっとできることはないか」と感じ始めたフェーズでチャレンジするのが理想的です。
生成AIの導入がこれからという企業にとっては、いきなりエージェントやMCPに取り組むのは学習コストが高い場合もあります。
期待値が先行しすぎると、思ったような成果が出ずに失望してしまうこともあるため、まずはスモールスタートで段階的に検証を進めることをおすすめします。
マルチモーダルAIの可能性
マルチモーダルAIとは、テキストだけでなく、音声・画像・動画など複数の情報形式を処理できるAIのことです。
これにより、特定の業務を大幅に効率化することが可能になります。
たとえば、以下のような活用が考えられます。
- 動画内の特定のマークやテキストを検出して自動で区切る
- 音声や動画の文字起こしを自動化する
- マーケティング用途での画像・動画生成
- ※著作権や商用利用の可否については事前確認が必要です
これらは、現在手作業で行っている業務がある場合、その一部を自動化することで大きな効果が期待できます。
ただし、最終的には人によるチェックが必要になるケースも多いため、「どこまでAIに任せるか」「どこから人が確認・判断するか」の線引きが重要です。
どこから始めたら良いか?という方に
「どこから始めればいいのか分からない」という企業様に対して、私は以下のようなヒアリングを行っています。
導入を検討する際の参考にしてみてください。
- 現状の業務課題
- 今、社内で困っていることは何ですか?
- 理想のユースケース
- 生成AIで、どんなことを実現したいですか?
- インプットとアウトプット
- AIにどんな情報を与えて(インプット)、どんな結果を得たい(アウトプット)ですか?
- ※想定されるQ&Aリストなどがあると、より具体的な検討が可能です。
- (すでに検証中の場合)現状と理想のギャップ
- 試してみて、理想と比べて何が足りないと感じましたか?
- その原因は何だと思いますか?
まだ具体的に固まっていない段階でも、壁打ちから相談に乗りますので、お気軽にお声がけください。
最後に
私自身、今では生成AIなしでは仕事が回らないほど、日常的に活用しています。
もはや「福利厚生」レベルの存在だと感じています。
今後、生成AIをうまく活用できる企業とそうでない企業の差は、業務効率や競争力の面でますます開いていくと思います。
これから生成AIの導入を考えている方、導入をしたけど悩んでいる方がいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
ではまた!新規事業統括部の洲崎でした。