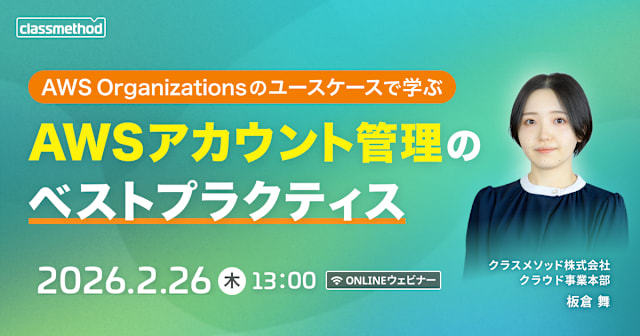内省支援で思考の整理をお手伝いする
こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
私はマネージャーや人事としての業務の中で、また業務外では社外の友人や知人から相談を受ける機会がよくあります。
その際に、相手の思考を整理するお手伝いをすることがあります。
この記事では、相談を受ける立場として、相手の思考を整理することについてまとめます。
相手の思考を整理する
相手が自分自身の思考を整理する支援をすることを内省支援と呼びます。
内省支援の対象
内省支援では、以下のような対象に対して支援をすることができます。
- 思考の整理に協力する
- 気づきを引き出す
- 自己効力感を育む
- 経験学習を促す
1. 思考の整理に協力する
自分ひとりだと思考の掘り下げの粒度が荒くなっている部分や、断片的に理解できていても全体像を整理できていない出来事や、実は複数の問題点が混在するお題を一つの問題として捉えているような状態について質問を通して整理に協力することができます。
対応関係としては以下のようになります。
| 思考の整理対象 | 思考を整理した結果 |
|---|---|
| 思考の粒度が荒い | より具体的に問題を捉えることができる |
| 事実と解釈が混在している | 事実と解釈を区別して扱うことができる |
| 理解が断片的 | 背景、目的、問題、解決策など問題を構造的に理解することができる |
| 複合の問題が混在 | 問題を一つずつ切り分け、区別することができる |
2. 気づきを引き出す
自分だけだと気づいていない部分や思い違いをしていた部分に対する気づきを促すことができます。
対応関係としては以下のようになります。
| 気づきの対象 | 気づきを得た結果 |
|---|---|
| 前提知識の差 | 自分は知らなくて、他者は知っていることを踏まえた情報を得ることができる |
| 他者の目線 | 他者の感じ方や他者から見た問題点に気づくことができる |
| 誤りに気づく | 問題の解釈の誤りや好ましくない選択肢を選んでいたことに気づくことができる |
| 行動の影響 | 自分が行動した結果の影響をより広い範囲で知ることができる |
なお、上記のような個別の対象とは別に、相手の考えを整理し、自ら語るように促すだけでも効果があります。これは、オートクラインと呼ばれるもので、自分の発言を自分で聞くことによって自分の考えや感情に気づきやすくなります。
3. 自己効力感を育む
自分の成果や成長について、客観的な視点で整理を手伝ってもらうことで自己効力感を育みやすくなります。
たとえば、業務で新しく得た知識、新たに習得したスキル、経験済みの業務の習熟度の向上など、実は成長している部分や、自分の関わった業務が最終的な成果にどのように貢献したかを確認できている状態と、整理せず認識しないまま日々を過ごす状態とでは、自己効力感の伸びに差が生じます。
4. 経験学習を促す
内省支援を受けながら、その過程を俯瞰的に捉えられるようになると、どのように内省すればいいかが分かってきます。
結果として、他者の支援を受けたときにできていた内省を少しずつ自分でもできるようになってきます。結果として、自走して成長する力が高まります。
これを促すためには、支援者として考えていることを説明しつつ支援するとよいでしょう。また、第三者の協力が得られるならば、支援者が支援を受ける相手に対して内省支援をしている状況を第三者として同席し、観察させてもらうのも良い方法です。
信頼できる上司やメンターと信頼できる同僚がいれば実現可能です。
内省支援のポイント
内省支援をする際に、以下のようなポイントを注意する必要があります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 信頼構築 | 踏み込んだ内容になるほど、前提として信頼が必要になります。いきなり重い問いかけをしないようにする必要があります |
| 傾聴 | 相手の発言を遮らず、深く理解すること |
| 事実質問 | 5W1Hなど、具体的な事実を引き出す質問をすること |
| 受け入れの自由 | フィードバックした内容を受け入れるかどうかを強制せず、相手が自分の意思で判断できるようにすること |
| 誤認識の可能性 | 意図的に誤った状態になっているわけではなく、誤認識で誤った判断に至ることもあります。それを踏まえて質問をすること |
内省支援をする人は抱えすぎないこと
内省支援が成功につながるかどうかは、支援をする人の腕に依る部分もありますが、支援をされる人に依る部分もあります。
そのため、どれだけ優れた支援者であっても、必ずしも望ましい結果が得られるとは限りません。
常に支援をする人の責任として捉えると支援者としての自信を失うことになりかねません。自分で影響を与えられる範囲に意識を置き、自分では影響を与えられない範囲について責任を感じすぎないようにバランスをとりましょう。