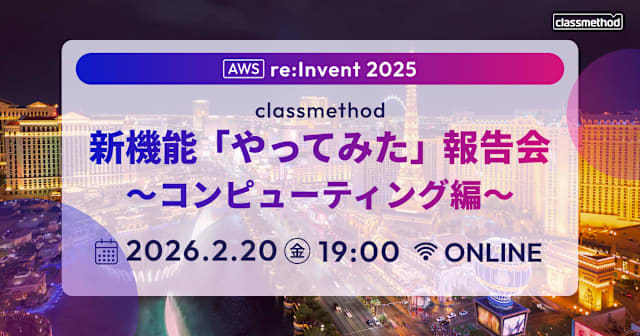社外勉強会で得た情報を社内に共有する際のポイントと生成AIの補助
こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
社外勉強会で得た情報を社内に共有する際のポイントについてまとめます。
情報の推奨度を明確にする
すべての情報を区別なく、丸ごと渡すのではなく、【推奨】【参考】など、推奨度ごとに渡せると相手からみた重要度がわかりやすくなります。たとえば、勉強会で6件の発表があったとき、すべてを同じ重要度で共有したいとは限らないはずです。
なお、私の場合、社外勉強会から得た情報は必読にはしないようにしています。関心がない人からすると急に必須の業務を増やされることになるため、情報共有のありがたさよりも業務負担が上回る可能性があり、せっかくの情報共有がマイナスになりかねないためです。
例
【推奨】推奨のテーマ
推奨のテーマの内容
【参考】参考のテーマ
参考のテーマの内容
【その他】
その他、勉強会で共有されていた資料や関連リンクです。
詳細に興味がある場合、ご覧ください。
* URL1
* URL2
最小の努力で確認できるようにする
推奨度の高い情報は、大きな塊のまま渡さず、必要最小限に絞り、必要な背景情報を補足しつつ連携します。
また、どこが伝えたいポイントなのかを一目でわかるようにすると親切です。
たとえば、発表で引用されていたウェブページの資料が10ページに渡る大量な内容で、伝えたい要点はその中の1ページに限定される場合、対象の1ページだけにフォーカスして共有するような伝え方です。
逆にいうと大雑把に渡すと、相手から見るとどこが伝えたい要点なのか予想する必要が出てきます。
そして、予想をするためには基本的には共有された情報を網羅的に確認することになります。
もし、その情報が膨大な量の場合、本来知ってほしい情報を理解するために、余分な時間が必要になります。
要点が伝わればまだしも、趣旨そのものが伝わらない可能性もあります。
伝えることに効果を想定する
知識を増やしてほしいのか、それを元に課題を理解できるようになってもらいたいのか、具体的にアクションにつなげてほしいのかなど、共有したあとにどのような状態になってもらいたいのかを踏まえて共有方法を検討する必要があります。
共有の注意点
上司と部下、先輩と後輩など職務上の権威差がある場合、共有する側が気軽な共有として伝えたとしても受け取る側が必読として認識してしまい、情報の共有が過負荷になってしまう可能性があります。
たとえば「もしよければご覧ください」「興味があればご覧ください」など、読むことはあくまで本人の意志に任せられていることを明示することが大切です。また、普段からの関わりを通じて、忖度なく言葉通りに受け取ってもらえるような関係を築くことが必要です。
生成AIのアシスト
情報を最小にするうえで、生成AIによる要約は手間を減らす良い手段です。
入力
https://speakerdeck.com/tbpgr/1-on-1-sessions-to-foster-self-reflection
このスライドの内容を読み込み、経験学習とはどんなもので、どのように重要かについて要約してください
出力
経験学習とは、経験を通じて学ぶプロセスであり、個々人が自身の行動や結果から学びを得るためのサイクルとして、特にプロフェッショナルな能力開発において非常に重要です。
## 経験学習のプロセス
経験学習は単に「やってみる」ことではありません。以下の4つの段階からなる継続的かつ循環的なプロセスです。
1. 具体的経験(Concrete Experience): これは「やる」の部分です。例えば、開発者が新しいプログラミング言語でバグを修正するタスクを任されるといった、具体的な出来事や状況を直接経験することです。
2. 省察的観察(Reflective Observation): 経験した後、何が起こったのかを振り返ります。自分の考えや感情、行動の結果はどうだったか、なぜ成功したのか、あるいは失敗したのかを考察します。このスライドの1on1ミーティングは、まさにこの重要なステップを促進するために設計されており、従業員が自身の仕事について深く考えることを促します。
3. 抽象的概念化(Abstract Conceptualization): 振り返りから、自分なりの結論を導き出し、一般的な原則や理論を形成します。「あの新しい言語で苦労したのは、構文を完全に理解していなかったからだ。次は、まずドキュメントをしっかり読むべきだ」といった学びを得る段階です。
4. 能動的実験(Active Experimentation): 新しい理解を別の状況で応用します。新しい「理論」を指針として行動することで、新たな具体的経験が生まれ、再び学習サイクルが始まります。
このサイクルは、行動し、内省し、適応するという継続的な学習プロセスを示しています。
## 経験学習が重要である理由
経験学習は、単に情報を受け取るだけでなく、意味のある個人的な理解を生み出すことに焦点を当てているため、非常に重要です。スライドでも、その重要性が以下の点で強調されています。
* 自己内省を促進する: スライドで説明されている1on1ミーティングは、マネージャーが指示を与える場ではなく、従業員自身が内省を促すような質問を投げかける場です。この焦点の転換により、従業員は自身の成長に主体的に取り組むようになります。
* より深い学習を育む: 自分の経験に積極的に向き合い、内省することで、従業員は単に解決策を覚えるのではなく、「なぜ」そうなるのかを深く理解するようになります。これにより、表面的な知識ではなく、より確固とした問題解決能力と本物の成長につながります。
* 自律性を育む: 自分で答えを見つけるように導かれると、人々はより自立し、自分の能力に自信を持つようになります。これは、単に「何をすべきか」を教えられるよりもはるかに価値のある「学び方」を身につけることにつながります。マネージャーは指示者ではなくファシリテーターとして機能することで、信頼関係を築き、より成熟したプロフェッショナルな関係を育みます。