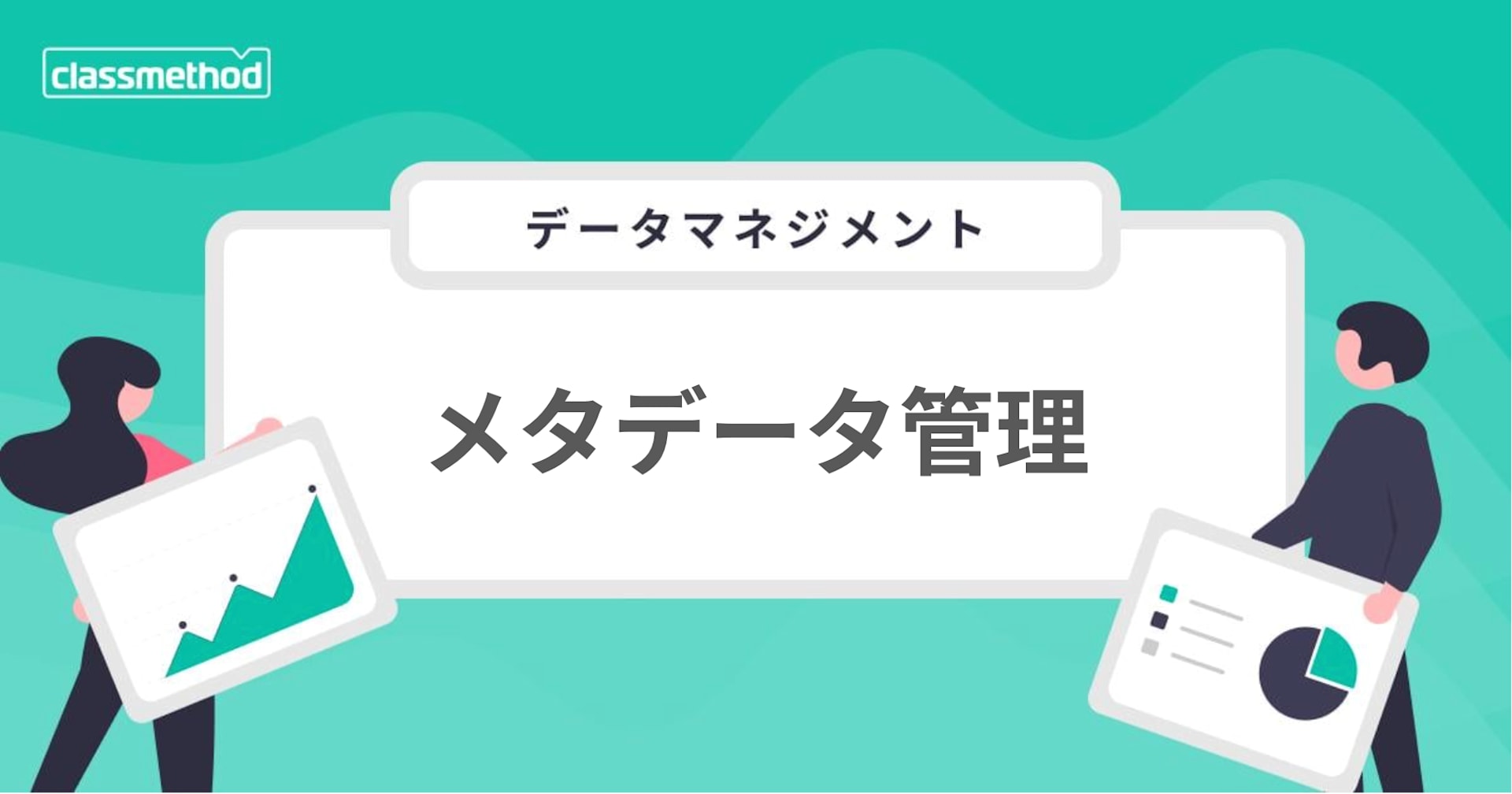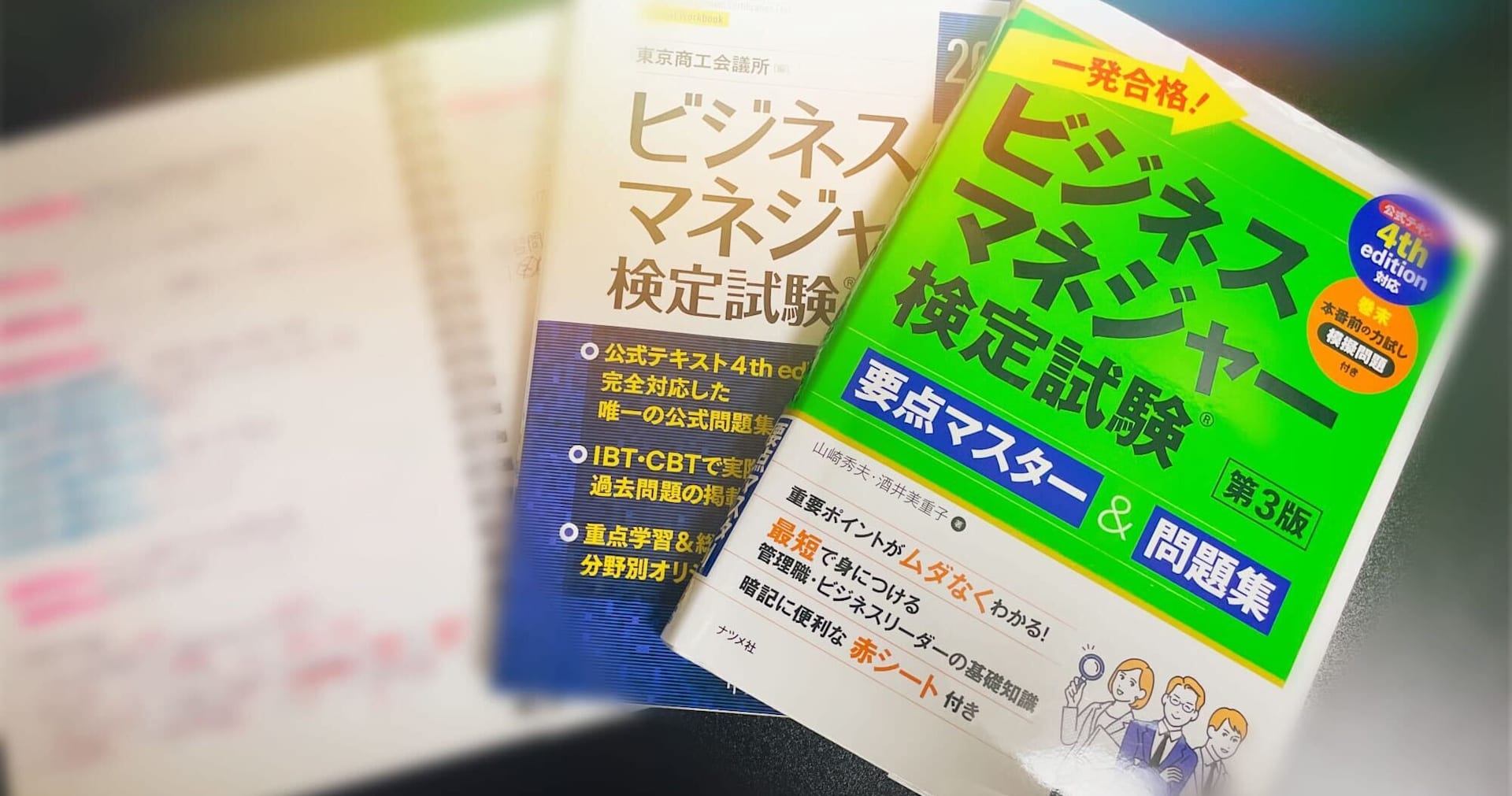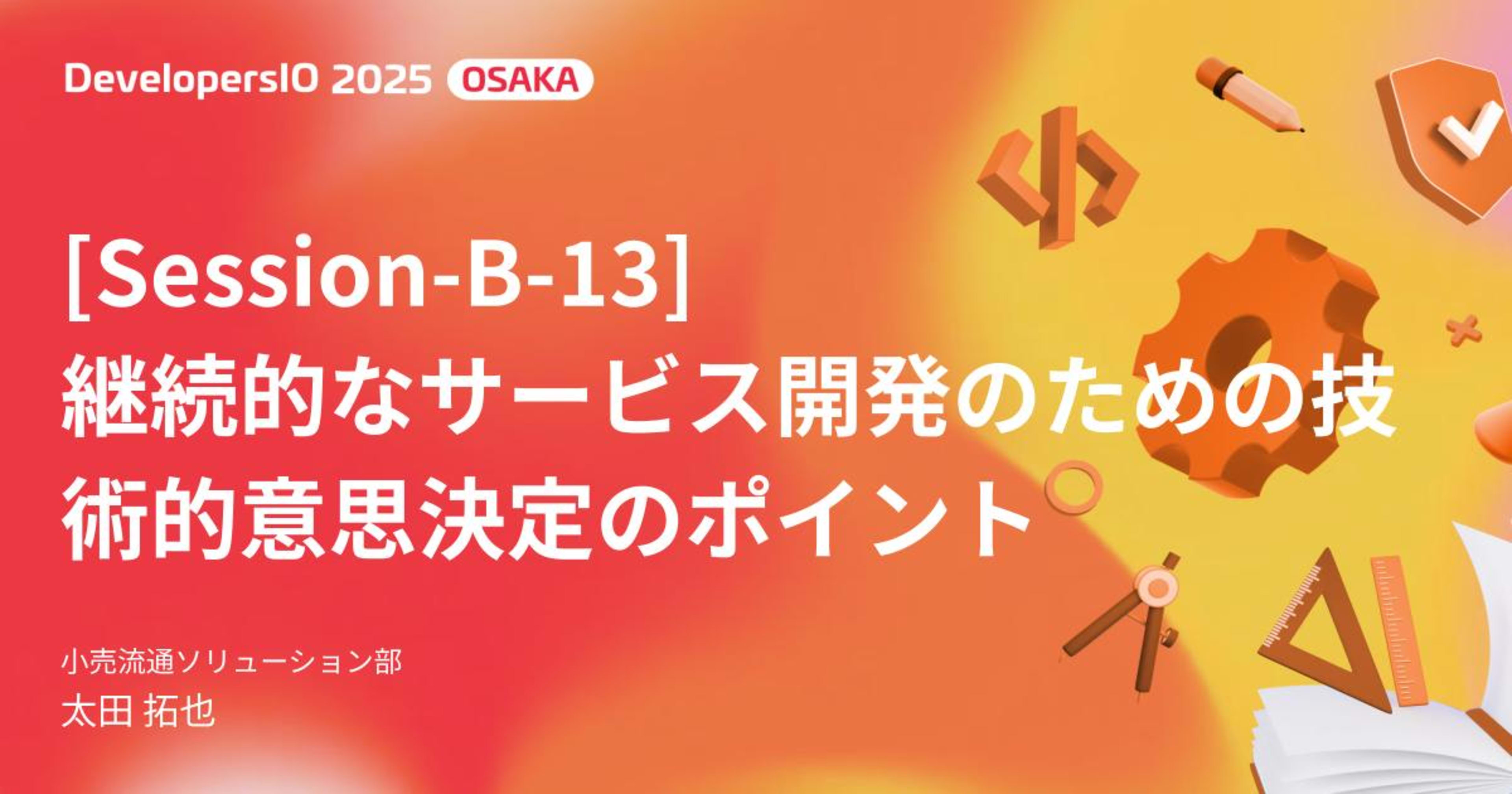
【登壇資料】 「継続的なサービス開発のための技術的意思決定のポイント」 というタイトルで DevelopersIO 2025 Osaka で登壇しました #devio2025
小売流通ソリューション部の太田です。
2025年9月3日(水)に開催されたDevelopersIO 2025 Osakaに「継続的なサービス開発のための技術的意思決定のポイント」というタイトルで登壇しました。
具体的な技術のトピックからは少し離れた抽象的なテーマということもあり、ちゃんと集客できるか本番まで不安でしたが、いざ蓋を開けてみると立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。
ご参加いただいた方には改めて感謝申し上げます。
それだけ注目を集めたテーマということで、この記事では発表では話しきれなかった前提となる課題感について少し補足させていただきます。
登壇資料
前提となる課題感
普段はみなさんの現場で個別具体の意志決定に翻弄されていることかと思います。
そんなそれぞれの意志決定について、実際の現場のコンテキスト抜きにその評価を行うことは難しいと考えています。
全く同じ選択肢が並んでいた場合においても、現場によってその選択が意味するものは大きく異なります。
こうした性質から「個別の意志決定について毎日振り回されながら孤独に戦っておられる方が一定数いるのではないか」という課題感がありました。
そこで、個別の意志決定ではなく、一連の意志決定フローとしての性質に着目し、より良い意志決定ができるようになるために自分たちの現場で改善を行うにはどういった方法があるのか、ということに焦点を当てて発表することにしました。
アプローチ
クネビンフレームワークにおける複雑系のシステムに対するアプローチ(探索、把握、対応)に着目しました。
そもそも失敗が当たり前というマインドセットを持つことでプレッシャーから脱却することができます。
そして、うまく探索、把握を行うためのプラクティスとして、以下を紹介しました。
- ADR
- One-Way-Door, Two-Way-Door
- 視野の狭窄に陥りやすい問いの形式
これらを組み合わせることで、安全に実験を繰り返し、意志決定を上達させることができると考えています。
おわりに
今回ご紹介した考え方が皆様のお役に立てれば幸いです。