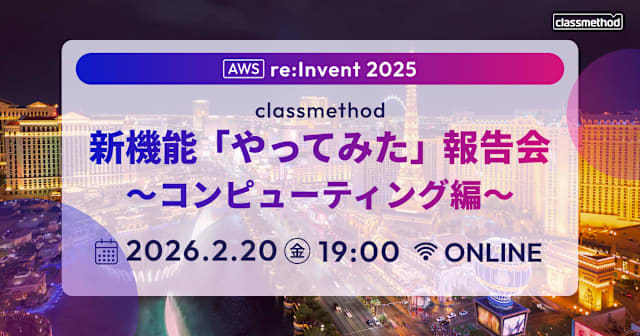フィードバックを求めてから改善につながるまでの全体像
この記事は公開されてから1年以上経過しています。情報が古い可能性がありますので、ご注意ください。
上司や同僚にフィードバックを求め、フィードバックを受け取っただけでは自己の改善につながるとは限りません。そこで、フィードバックが改善につながるまでの全体についてまとめます。
フィードバックを求めてから改善につなげるまでの全体像
フィードバックを求めてから、改善につながるまでは以下のような過程があります。
- フィードバック探索行動
- フィードバック提供
- フィードバック受容性
- フィードバック行動の実施
1 フィードバック探索行動
例えば、ミーティングのファシリテーションがうまくいなかったと感じたとき、同席していたファシリテーションに長けた同僚のAさんに「今のミーティングで自分のファシリテーションがうまくいっていないように感じました。ただ、自分ではどこに問題があるのか分からないのです。Aさんからみて改善する余地がありそうな部分があれば教えて欲しいです」とフィードバックを求めるようなケースです。
フィードバック探索行動について詳しくは以下の記事を参照ください。
2 フィードバック提供
例えば、先程の例の続きとしてAさんから「議論の進行をするとき、他者の意見を遮っている場面が複数回ありました。最後まで意見を聞き終えない場合、相手が本当に伝えたかった内容を聞き逃すリスクがあります。また、仮にすべて聞かずとも相手の言いたいことを把握できていたとしても、人の話を最後まで聞いてくれない人と認識されて相手の心象を損ねてしまうリスクがあります。」とフィードバックをするようなケースです。
フィードバックについて詳しくは以下の記事を参照ください。
3 フィードバック受容性
フィードバックを受け入れるにはいくつかの要素が必要になります。
1つ目にオープンマインドです。オープンマインドとは、新しい考えや意見に対して受け入れやすく、柔軟性や寛容性を持つことができる状態を指します。
2つ目に内容の理解です。フィードバックとして伝えられた内容に不明点があれば質問したり、具体例を元に説明を補足してもらうなどして理解に努めます。
3つ目に有効性の見極めです。フィードバックは改善に伝わる的を射た有用なものもあれば、全く的はずれなものもあります。相手から受け取ったフィードバックを元に自分の行動を変えたほうがいいか、そのままでいいか見極める必要があります。
4つ目に感情のコントロールです。改善に必要なフィードバックは受け止め方次第で自分の未熟さと捉えて落ち込んでしまったり、他者からの攻撃とみなして防衛的になってしまいがちです。受け取った情報からフィードバックとして活用できる事実に着目すること。相手の発言の裏にある感情を読みすぎないこと。仮にフィードバックに攻撃的な感情が含まれていそうなときも、フィードバック内容の事実のみに着目することなど、感情をコントロールすることが必要です。
例えば、先程の例の続きとして、「相手の話を遮っている」というメッセージに対して自分への否定や攻撃として捉えるのではなく、「話を遮っている場合、相手の言う通りの悪影響があるのかどうか?」「遮らないように改善することでよりよい結果を生み出すことができるかどうか?」などに着目し、自分にとっては改善の好機を得た、と捉え直すようなケースです。
4 フィードバック行動の実施
改善が必要な自分の振る舞いを理解し、新たな行動に変えることで改善につながることになります。フィードバックを活用する道のりはここまでの全てに成功してようやく自己の成長につながることになります。
例えば、先程の例の続きとして、次にファシリテーションをする機会があったときに相手の発言を遮らないように最後まで聞き取ってから次の議論に進行させるようなファシリテーションをすること。また、それによって実際に議論の質が向上したことを確認するようなケースです。
まとめ
フィードバックの話題になるとき、フィードバックそのものについて語られがちですが、実際にはここで挙げたようにフィードバック探索行動から始まり、フィードバック行動の実施までの全体を経てようやく実際に改善につながります。自分はどの部分でつまずいているのか、すべてうまくいっているのか、過去の経験をふりかえってみるとよいでしょう。