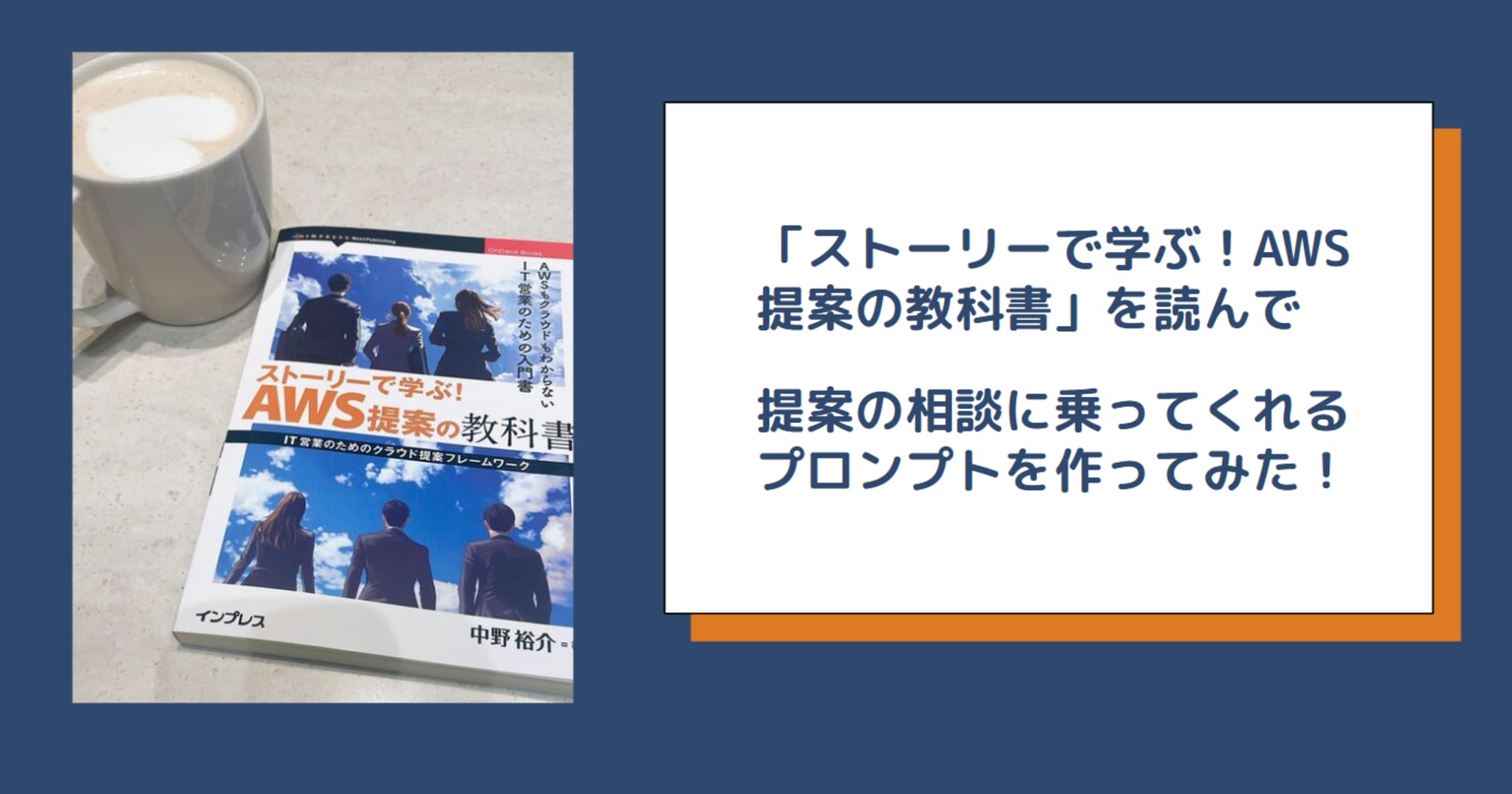思考フレームワークの助けを借りてプロンプトを作成する
こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
生成AIを活用する際に、お題にあった思考フレームワークを活用すると、掘り下げが捗ります。
この記事では、生成AIのプロンプトに思考フレームワークを活用する事例と、思考フレームワークをプロンプトで探すことについてまとめます。
思考フレームワークをプロンプトで活用する例
4つの例を紹介します。
- STAR面接法
- PREP法
- SMARTな目標
- 推論のはしご
STAR面接法
入力
STAR面接法について説明してください
出力
STAR面接法は、応募者の**過去の具体的な行動**を通して、その人の能力や行動特性、思考パターンを深く把握するための面接手法です。
「**行動面接**」の一種であり、質問項目や評価基準を統一しやすい「構造化面接」として、多くの企業(AmazonやGoogleなど)で採用されています。
「STAR」は、応募者に話してもらうべき具体的な経験を構成する4つの要素の頭文字です。面接官は、この順番に質問を掘り下げていきます。
| 頭文字 | 要素 | 意味と質問の目的 |
| :--- | :--- | :--- |
| **S** | **Situation (状況)** | **どのような状況・環境だったか**。いつ、どこで、誰と、どのような目標や背景があったかを明確にし、話の前提を理解する。 |
| **T** | **Task (課題)** | その状況の中で、**応募者自身が直面した課題や、達成すべき任務**は何だったか。自身の役割や責任範囲を把握する。 |
| **A** | **Action (行動)** | その課題に対し、**応募者自身が具体的にどのような行動をとったか**、その行動の理由や思考プロセスを掘り下げる。ここが最も重要で、応募者の資質が表れる。 |
| **R** | **Result (結果)** | その行動の結果、**どのような成果(定量的・定性的)が得られたか**。また、その経験から何を学び、次にどう活かそうと考えているか。 |
### STAR面接法のメリット
1. **客観的な評価:** 抽象的な回答ではなく、過去の事実に基づいた行動を深掘りするため、面接官の主観に頼らず、客観的で公平な評価がしやすくなります。
2. **再現性の判断:** 過去の行動パターンや思考プロセスを知ることで、「この応募者が自社で同様の状況に直面した際に、同じように成果を再現できるか」を予測する精度が高まります。
3. **ミスマッチの防止:** 求める人物像やコンピテンシー(資質)に基づいた質問を設計できるため、入社後のミスマッチを減らす効果が期待できます。
入力
STAR面接法で主体性を問う面接をしたいです。
質問の流れを作成してください。
出力
STAR面接法を用いて**主体性(イニシアティブ)**を問う質問の流れを作成します。
主体性は、「指示待ちではなく、自ら課題を見つけ、解決に向けて行動する力」として定義し、その行動の**動機**、**自律性**、**困難への対応**を中心に掘り下げます。
## STAR面接法:主体性を問う質問の流れ
### 1. Situation (状況) の質問:背景と目標の把握
応募者が自ら課題解決に取り組む必要があった**状況**を特定します。
| 質問 | 意図 |
| :--- | :--- |
| **S-1.** 過去の業務経験で、**誰からの指示でもなく、あなた自身が「これはやるべきだ」と感じて始めたプロジェクトや業務改善の事例**について教えてください。 | 🙋 応募者が**自律的**に動いた経験を引き出す。 |
| **S-2.** その時のチーム体制や、あなたがその中でどのような立場だったか(チームリーダー、担当者など)、**当時の目標**は何だったかを詳しく教えてください。 | 🎯 行動の背景にある組織構造と、応募者の公式・非公式な役割を把握する。 |
***
### 2. Task (課題) の質問:課題設定能力の深掘り
応募者が設定した**課題**の難易度や、その課題を**自ら定義したプロセス**を明確にします。
| 質問 | 意図 |
| :--- | :--- |
| **T-1.** なぜ、その課題を**あなたが**解決しなければならないと考えたのですか? 放置された場合、どのような影響があったと予測されますか? | 🤔 課題に対する**当事者意識**と**危機察知能力**を問う。 |
| **T-2.** その課題を解決するための**難しさ**はどこにありましたか? 障害は技術的なものですか、それとも人間関係やリソースの問題ですか? | 🚧 応募者が**設定した課題の現実的な複雑さ**を評価する。 |
***
### 3. Action (行動) の質問:具体的な自律的行動の確認
課題解決のためにとった**行動**、特に**自発性**と**工夫**があった部分に焦点を当てます。
| 質問 | 意図 |
| :--- | :--- |
| **A-1.** 課題解決のために、**具体的に最初の一歩として何から始めましたか?** その行動は、**既存のマニュアルや前例のないもの**でしたか? | 🚀 自主性、**行動の起点**、および前例のない状況への対応力を評価する。 |
| **A-2.** 課題解決を進める中で、上司や周囲の人はどのような反応でしたか? **反対や抵抗があった場合**、それを乗り越えるために**あなた自身でどのような工夫**をしましたか? | 🤝 困難な状況における**巻き込み力**と**推進力**、**粘り強さ**を評価する。 |
| **A-3.** その行動をとる上で、**最も重視した判断基準や価値観**は何でしたか? | ✨ 行動の裏にある**判断軸**や**動機(主体性の根源)**を掘り下げる。 |
***
### 4. Result (結果) の質問:成果と反省、学びの確認
**結果**が目標達成にどう貢献したか、また経験から何を学んだかを確認します。
| 質問 | 意図 |
| :--- | :--- |
| **R-1.** あなたの行動の結果、**最終的にどのような成果**が得られましたか?(できる限り定量的な数値で教えてください。) | 📈 行動の**有効性**と、結果に対する**貢献度**を評価する。 |
| **R-2.** この一連の取り組みを振り返って、**「もっとこうすれば良かった」と思う点**はありますか? 次に同様の状況に直面したら、何を改善しますか? | 🔄 **自己批判能力**と**学習意欲**を評価する。 |
| **R-3.** この経験を通して、あなたの**「主体性」**に関して最も学んだことは何ですか? | 🧠 **経験を抽象化し、自己成長に繋げられるか**を確認する。 |
PREP法
入力
PREP法について説明してください
出力
PREP法は、ビジネスシーンで**論理的かつ説得力のあるコミュニケーション**を行うためのフレームワークです。特に、会議での発言、報告書、プレゼンテーション、メールなど、結論を最初に伝える必要がある場面で非常に有効です。
PREPは、以下の4つの要素の頭文字を取っています。
| 頭文字 | 要素 | 意味 | 役割(話の構成) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **P** | **Point (結論)** | **最も伝えたい主張や結論**。 | 最初に結論を述べ、聞き手の注意を引きつける。 |
| **R** | **Reason (理由)** | その結論に至った**根拠や理由**。 | 結論が正しいことを示すための理由を提示する。 |
| **E** | **Example (具体例・事例)** | 理由を裏付けるための**具体的なデータや事実**。 | 理由を裏付ける証拠や具体的なイメージを提供し、説得力を高める。 |
| **P** | **Point (結論)** | 最初に述べた結論を**再度強調**。 | 最後に改めて結論を繰り返し、最も伝えたいことを印象づける。 |
### PREP法の構成と効果
1. **P (結論):** まず結論から入ることで、「何の話をしているのか」がすぐに伝わり、聞き手の理解を助けます。
2. **R (理由):** 結論の直後に「なぜなら」という形で理由を述べることで、論理的な筋道が明確になります。
3. **E (具体例):** 理由だけでは抽象的になりがちなため、具体的な事例や数値を入れることで、聞き手に納得感を与えます。
4. **P (再結論):** 最後に同じ結論を繰り返すことで、伝えたいメッセージが記憶に残りやすくなります。
この構造を使うことで、話が**論理的**になり、**結論が明確**なため、聞き手にとって理解しやすく、**説得力の高い**伝え方が可能になります。
入力
上司に担当しているタスクフォースの現状を伝えようと思っています。
部内でのAI活用に関して、以下の手順で浸透を促す予定です。
1. 基礎知識のインプット
2. 仮想の業務でのお試し利用
3. 手元の業務での利用
4. チームの業務での利用
このアプローチについて、PREP法を踏まえて報告したいです。
報告の流れについて素案を作成してください。
出力
PREP法を活用し、上司へのタスクフォースの現状報告の流れを作成します。この流れでは、まず結論として「順調に進んでいること」を伝え、その理由として「段階的なアプローチ」を提示し、具体例として「4つのステップ」を詳細に説明し、最後に改めて今後の見通しを再結論として伝えます。
## PREP法に基づく報告の流れ(素案)
| 構成要素 | ポイント(内容と報告の意図) | 報告の切り出し方(例文) |
| :--- | :--- | :--- |
| **P (Point: 結論)** | **AI活用浸透のためのアプローチは順調**に進んでおり、計画どおりに部内展開を進行中であること。 | 「タスクフォースが推進している部内AI活用浸透施策についてご報告します。結論から申し上げますと、**導入アプローチは計画通りに進捗しており、手応えを感じています。**」 |
| **R (Reason: 理由)** | 段階的かつ心理的障壁の低い**4ステップのフェーズ**を踏むことで、参加者の**学習意欲と利用定着率の向上**を図っているため。 | 「その理由として、私たちは『**基礎→個人→チーム**』という段階を踏むことで、AI利用に対する心理的な障壁を下げ、学習定着率を高めるアプローチを採用しているからです。」 |
| **E (Example: 具体例)** | 理由を裏付ける**4つの具体的な手順(ステップ)と、それぞれの目標を説明する。 | 「具体的には、以下の4つのステップで浸透を促しています。」<br>1. 基礎知識のインプット: AIの仕組みやリスクを理解させる。<br>2. 仮想の業務でのお試し利用: 失敗しても良い環境で操作に慣れてもらう**。<br>3. **手元の業務での利用:** 自分の業務への**具体的な応用イメージを持たせる**。<br>4. **チームの業務での利用:** チーム全体の効率化を図り、**定着を促進する**。 |
| **P (Point: 再結論)** | このアプローチにより、年内には**部内全体の業務効率化に貢献**できる見込みであること。 | 「以上の段階的なアプローチにより、当初の計画どおり**年内の本格的な業務活用、および部内全体の業務効率化に繋がる**と見込んでおります。引き続き進捗を注視し、次のフェーズへ移行します。」 |
### 報告のヒント
* \*\*P(結論)\*\*は簡潔に、\*\*R(理由)\*\*は論理的に、\*\*E(具体例)\*\*は具体的かつ説得力を持たせるよう意識してください。
* 上司からは、特に「手元の業務での利用(ステップ3)」や「チームの業務での利用(ステップ4)」の**具体的な事例**や**利用率の数値**について質問される可能性が高いです。可能であれば、これらの具体的な成果(例:ステップ2終了者が○名、ステップ3で○時間の削減効果)を補足データとして用意しておくと、さらに説得力が増します。
SMARTな目標
SMARTは、個人や組織の目標設定において、目標を明確にし、達成可能性を高めるために広く使われているフレームワークです。
目標が単なる願望や抽象的なものに終わるのを防ぎ、具体的で実行可能な計画に落とし込むことを目的としています。
SMARTは、効果的な目標が満たすべき5つの要素の頭文字を取っています。
| 頭文字 | 要素 | 意味 | 質問の例 |
|---|---|---|---|
| S | Specific (具体的) | 目標が曖昧ではなく、誰が、何を、どのように達成するのかが明確であること。 | 「何を」「なぜ」「どのように」達成するのか? |
| M | Measurable (測定可能) | 目標の達成度合いを数値や指標で客観的に測定できること。進捗の確認や評価が可能であること。 | 「いつまでに」「どれくらいの量・数」を達成するのか? |
| A | Achievable (達成可能) | 目標が現実的に達成可能であり、非現実的でないこと。ただし、適度な挑戦を含むこと。 | 自分の能力やリソースで「本当に達成できる」のか? |
| R | Relevant (関連性) | その目標が、上位の目標や組織の戦略・ビジョンと関連していること。なぜその目標を達成する必要があるのか、意味があること。 | その目標は「全体戦略」や「自分のミッション」と結びついているか? |
| T | Time-bound (期限がある) | 目標の達成期限が明確に設定されていること。 | 「いつまでに」完了させるのか? マイルストーン(中間目標)はいつか? |
SMARTな目標をプロンプトで確認するケースについては、以前以下の記事にまとめました。
ChatGPTで目標がSMARTかどうかをチェックする | DevelopersIO
推論のはしご
「推論のはしご (The Ladder of Inference)」は、組織心理学者クリス・アージリスによって提唱されたフレームワークです。人が目の前の「事実」から「行動」に至るまでの無意識的で急速な思考プロセスを、はしごの段に見立てて図式化したものです。
このモデルを理解することで、人はなぜ誤った結論に至るのか、また、他者との間にコミュニケーション上の誤解が生じるのかを分析し、建設的な議論やより良い意思決定を行うために役立ちます。
推論のはしごのステップ
はしごは下から上へと登るように進み、ステップが上がるほど主観的で抽象的な要素が強くなります。
| ステップ | 要素 | 意味とプロセス |
|---|---|---|
| 7. 行動 (Action) | 信念に基づき、具体的な行動を起こす。 | 自身の信念が行動を導き、その行動が次の観察(ステップ1)に影響を与える。 |
| 6. 信念を持つ (Beliefs) | 結論や仮定が繰り返され、強固な信念や世界観を形成する。 | 「物事はこうあるべきだ」という確信が生まれ、自己強化される(確証バイアス)。 |
| 5. 結論を出す (Conclusions) | 立てた仮定に基づき、最終的な判断や結論を導き出す。 | ほとんどの場合、結論は「真実」として受け止められる。 |
| 4. 仮定を立てる (Assumptions) | 解釈に、過去の経験や個人的な前提を加えて意味を補強する。 | 「あの人はいつもそうだ」「うちの会社ではこうだ」といった思い込みを形成する。 |
| 3. 意味付け・解釈 (Meaning/Interpret) | 選択したデータに対して、個人的な意味を与える。 | データが自分にとって「良い」「悪い」「問題だ」といった主観的な評価が加わる。 |
| 2. データの選択 (Select Data) | 目の前の現実(ステップ1)から、特定のデータや事実だけを無意識に選択し、意識的に認識する。 | 膨大な情報の中から、自分の興味や関心、過去の経験に合うものだけを選び取る。 |
| 1. 現実・事実 (Observable Data/Reality) | 客観的に観察可能な出来事やデータ。 | 議論の土台となる、誰の目にも明らかな**「真実」**。 |
推論のはしごをプロンプトで確認するケースについては、以前以下の記事にまとめました。
AI壁打ちシリーズ : 思考の流れを推測する | DevelopersIO
思考フレームワークの存在を確認する
自分が思考フレームワークに詳しくない場合、フレームワークを質問するところから始める方法もあります。
入力
新規事業の市場環境を整理し、自社の取るべき戦略を立案するために適した思考フレームワークがあれば教えてください。
出力
新規事業の市場環境の整理と戦略立案に適した思考フレームワークは多数あり、それらを**複数組み合わせて段階的に活用する**ことが一般的かつ効果的です。
特に新規事業の企画段階で、市場環境を整理し、自社の取るべき戦略を立案するために有用な代表的なフレームワークを以下にご紹介します。
### 1. 市場環境の整理・分析に有用なフレームワーク
新規事業の外部環境(市場・競合)と内部環境(自社)を多角的に分析し、現状を把握するために使います。
| フェーズ | フレームワーク | 概要と目的 |
| :--- | :--- | :--- |
| **外部環境分析** | **PEST分析** | **P**olitics(政治)、**E**conomy(経済)、**S**ociety(社会)、**T**echnology(技術)の4つの視点から、自社を取り巻くマクロな外部環境が事業に与える影響を整理します。将来の機会や脅威を予測するのに役立ちます。 |
| **外部・内部環境分析** | **3C分析** | **C**ustomer(市場・顧客)、**C**ompetitor(競合)、**C**ompany(自社)の3つの視点から、事業成功の要因(KFS: Key Success Factor)を見つけ出すために使われます。 |
| **業界構造分析** | **5フォース分析** | 業界の収益性を決定する5つの競争要因(新規参入の脅威、代替品の脅威、売り手の交渉力、買い手の交渉力、既存競合間の敵対関係)を分析し、業界の魅力度や参入障壁などを把握します。 |
| **総合分析** | **SWOT分析** | **S**trengths(強み)、**W**eaknesses(弱み)、**O**pportunities(機会)、**T**hreats(脅威)の4つの要素に、自社を取り巻く内部環境(S, W)と外部環境(O, T)を整理します。 |
### 2. 戦略立案に有用なフレームワーク
上記で整理した環境分析の結果を活用し、具体的な戦略の方向性を決定するために使われます。
| フェーズ | フレームワーク | 概要と目的 |
| :--- | :--- | :--- |
| **戦略策定** | **クロスSWOT分析 (TOWSマトリクス)** | SWOT分析で洗い出した4つの要素を組み合わせて(例:強み $\times$ 機会、弱み $\times$ 脅威)、具体的な戦略オプション(攻め、守りなど)を導き出します。 |
| **ターゲット設定** | **STP分析** | **S**egmentation(市場の細分化)、**T**argeting(狙う市場の決定)、**P**ositioning(自社の立ち位置の明確化)を行い、競合と差別化できる独自のポジションを確立します。 |
| **事業モデル設計** | **ビジネスモデルキャンバス / リーンキャンバス** | 事業に必要な要素(顧客セグメント、提供価値、チャネル、収益の流れ、コスト構造など)を1枚の図に整理し、事業全体の構造を可視化し、関係者間で共有しやすくします。新規事業やベンチャーでは「リーンキャンバス」がより簡潔で好まれることもあります。 |
| **マーケティング戦略** | **4P分析 (マーケティングミックス)** | **P**roduct(製品・サービス)、**P**rice(価格)、**P**lace(流通・販売)、**P**romotion(販促・広告)の4つの要素から具体的な施策を検討します。 |
### 活用する際のステップ例
新規事業の戦略立案では、上記のフレームワークを以下のような流れで活用すると体系的に進められます。
1. **マクロ環境把握:** **PEST分析**で社会全体の大きな変化を捉える。
2. **業界構造理解:** **5フォース分析**で業界の収益構造と競争の厳しさを把握する。
3. **ミクロ環境把握:** **3C分析**で市場の成功要因、競合の動向、自社の強み・弱みを深掘りする。
4. **現状の総括:** **SWOT分析**で内部環境と外部環境を整理し、現状を客観的に評価する。
5. **戦略オプションの導出:** **クロスSWOT分析**で具体的な戦略の方向性(例:強みを活かして機会を捉える)を複数立案する。
6. **ポジショニング決定:** **STP分析**でターゲット顧客と提供価値を明確にし、市場における自社の優位なポジションを定める。
7. **事業モデルの設計:** **ビジネスモデルキャンバス / リーンキャンバス**で、事業の構造全体を具体化・検証し、実行可能な計画に落とし込む。
これらのフレームワークは**組み合わせて使用することで、多角的な分析が可能になり、より精度の高い戦略立案につながります。**また、分析に時間をかけすぎず、仮説と検証を繰り返す「リーンスタートアップ」の考え方も新規事業では重要です。