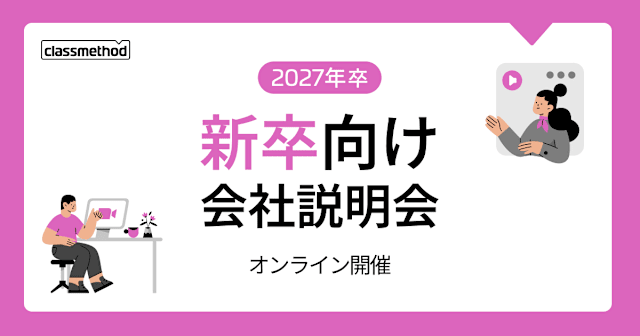AI壁打ちシリーズ : 思考の流れを推測する
こんにちは。組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
仕事におけるやりとりにおいて、相手の発言がすべてとは限りません。実際には発言に至る思考の流れがあり、それを丁寧に伝える人もいれば結論だけを伝える人もいます。
そこで、 Gemini を利用して思考の流れを推測する方法を紹介します。
推論のはしご
思考の流れを理解する前提として、推論のはしごを紹介します。
推論のはしご ( The Ladder of Inference )とは、私たちが観察した事実からどうやって結論や行動へと至るかを7つの段階でモデル化したものです。
推論のはしごを一段ずつ上っていくことで、客観的な事実から、主観的な行動へとつながる思考プロセスを辿ることができます。このモデルを理解することで、「 なぜ自分はそのように考え、行動したのか? 」を客観的に見つめ直し、より健全な判断を下すことができるようになります。これは、自分だけではなく、他者の思考についても同様です。
以下に、それぞれの段階を例を交えて説明します。
1. 事実の観察
これは、最も客観的なデータや出来事です。
例: Aさんは会議で何も発言しなかった。
2. 事実の選択
私たちは膨大な情報の中から、特定の情報だけを無意識に選び取ります。
例: Aさんが発言しなかったという事実に焦点を当てる。
3. 意味づけ
選択した事実に対して、独自の解釈や意味を加えます。
例: Aさんは「この会議に興味がない」と解釈する。
4. 仮定の構築
意味づけに基づいて、さらに先の仮定を立てます。
例: Aさんは会議の準備をしていなかったのだろうと推測する。
5. 結論を導き出す
仮定を事実とみなし、最終的な結論を導きます。
例: Aさんは「仕事に対するモチベーションが低い」と結論づける。
6. 信念の採用
導き出された結論が、その人や状況に対する信念として定着します。
例: Aさんはやる気がない人だという信念を持つ。
7. 行動
確立された信念に基づいて、具体的な行動を起こします。
例: 今後Aさんには重要な仕事を任せないという行動に出る。
これはかなり偏った好ましくない解釈の例ですが、同じ出来事があっても人によって思考のプロセスは多様です。
思考プロセスを伴わない Gemini の出力
思考プロセスを明らかにする例との対比のため、プロセスを明示しないプロンプトの例を先に確認します。
入力
本日、チームの課題について話し合うミーティングがありました。
Aさんは会議で何も発言しなかったのですが、その行動に至る過程についてありえそうな理由を3例説明してください。
出力
ミーティングでAさんが発言しなかった理由として、考えられる3つの例を以下に説明します。
---
### 1. 準備不足または情報不足
Aさんは、議題について十分に理解していなかったり、必要な情報を持ち合わせていなかったりした可能性があります。
会議中に何か発言したくても、内容を把握できていなければ、的外れな意見を述べることを避けるために沈黙を選んだのかもしれません。
また、その場で新しい情報が出てきて、それを整理するのに集中していたという状況も考えられます。
---
### 2. 性格的な要因または心理的な障壁
Aさんは元々、人前で話すのが得意ではなかったり、内向的な性格だったりするかもしれません。
特に、議論が活発に行われている場合、発言するタイミングを見つけられず、話に入り込むのをためらうことがあります。
また、自分の意見が間違っていたらどうしよう、という不安や、他のメンバーの意見に圧倒されてしまい、発言を控えてしまった可能性もあります。
---
### 3. 戦略的な理由またはチーム内での役割
Aさんは、あえて発言しなかったのかもしれません。
たとえば、他のメンバーの意見を注意深く聞き、全体像を把握することに徹していた可能性があります。
チーム内での役割として、進行役や書記、あるいはまとめ役を担っており、発言者としてではなく、議論の監視や記録に集中していたということも考えられます。
この場合、Aさんの沈黙は、チームの生産性を高めるための戦略的な行動といえます。
方法1 - Zero-shot Prompting + Chain-of-Thought Prompting による Gemini の出力
Zero-shot Prompting とは、例を提供せずに指示するプロンプトの記述法です。
シンプルな指示でも意図した動作をしやすいようなお題に対しては、 Zero-shot Prompting でも十分です。逆に、ある程度例示してチューニングする必要がある場合、後続で紹介する Few-shot Prompting が必要になります。
Chain-of-Thought Prompting は LLM が複雑な問題を解く際に、最終的な答えだけでなく、その答えに至るまでの思考の過程や中間ステップを段階的に出力させるためのプロンプト手法です
これらを元に思考のプロセスを掘り下げてみます。
入力
本日、チームの課題について話し合うミーティングがありました。
Aさんは会議で何も発言しなかったのですが、その行動に至る過程についてありえそうな理由について、3例説明してください。
また、その際に思考プロセスを含めてステップバイステップで説明してください。
出力
今日のミーティングでAさんが発言しなかったことには、いくつかの理由が考えられます。
ここでは、その思考プロセスを含めて3つの例を説明します。
---
### 1. 緊張や不安
この場合、Aさんは**発言すること自体に強いプレッシャー**を感じています。
**思考プロセス:**
1. **会議前:** 「今日、何か意見を言わなきゃいけないかな…」と考え、発言内容を事前に準備しようとします。
2. **会議中(初期):** チームメイトが次々と発言し始め、自分の意見が場違いではないか、あるいは十分に良い意見ではないのではないかと不安になります。
3. **会議中(中期):** 「今、発言しようかな。でも、もっと良いタイミングがあるかも」「もし間違っていたらどうしよう」と自問自答を繰り返します。この段階で、緊張がピークに達し、発言する勇気が出なくなります。
4. **会議中(後期):** 結局、何も言えないまま時間が過ぎ、発言の機会を逃してしまいます。「今日はもう無理だ。次の機会にしよう」と心の中で諦めます。
---
### 2. 状況の観察と情報収集
このケースでは、Aさんは**発言よりも、まず状況全体を把握すること**を優先しています。
**思考プロセス:**
1. **会議前:** 事前に議題の概要は把握していますが、詳細な情報は不足していると感じています。「まずは、みんなの意見をしっかり聞いて、全体像を把握しよう」と決意します。
2. **会議中(初期):** チームメイトの意見や議論の流れに注意深く耳を傾けます。誰がどんな情報を持ち、どう考えているのかを分析します。
3. **会議中(中期):** 議論が深まるにつれて、自分の考えが定まってきます。しかし、まだ発言する段階ではないと判断します。「この問題は、もっとデータが必要だな」「この点は、後で個別にBさんと話すべきかもしれない」などと、次のアクションを考えています。
4. **会議終了後:** 会議で得た情報を元に、個人的に課題の解決策を練ったり、必要な人に個別に話しかけたりします。
---
### 3. 発言の必要性を感じていない
この場合、Aさんは**議論の方向性に納得しており、自分が付け加えるべき意見はない**と考えています。
**思考プロセス:**
1. **会議前:** 議題に対して自分の考えは持っていますが、特に斬新な意見ではありません。
2. **会議中(初期):** チームメイトの意見を聞き、自分の考えとほとんど同じであることに気づきます。「Cさんの言っていることが、まさに自分が考えていたことだ」と納得します。
3. **会議中(中期):** 議論が進むにつれ、課題解決に向けて良い方向に向かっていると感じます。「このまま進めば、うまくいくはずだ。わざわざ発言して議論を中断させる必要はないな」と判断します。
4. **会議終了後:** 会議の決定事項に異論はなく、次の行動にスムーズに移ります。発言はしなかったものの、チームの結論には十分に貢献していると考えています。
このように、発言しないことの背後には、**さまざまな思考や意図**が存在する可能性があります。
単純に無関心なわけではないかもしれません。
方法2 - Few-shot Prompting + Chain-of-Thought Prompting による Gemini の出力
Few-shot Prompting とは、例を提供して回答の質を高める手法です。
今回は Chain-of-Thought Prompting を利用する際に Zero-shot Prompting ではなく、 Few-shot Prompting として推論のはしごに相当する例を提供してみます。
入力
本日、チームの課題について話し合うミーティングがありました。
Aさんは会議で何も発言しなかったのですが、その行動に至る過程についてありえそうな思考プロセスを3例説明してください。
各例は推論のはしごを元に以下にようなプロセスを含めて解説してください。
[推論のはしごの例]
### 1. 事実の観察
これは、最も客観的なデータや出来事です。
例: Aさんは会議で何も発言しなかった。
### 2. 事実の選択
私たちは膨大な情報の中から、特定の情報だけを無意識に選び取ります。
例: Aさんが発言しなかったという事実に焦点を当てる。
### 3. 意味づけ
選択した事実に対して、独自の解釈や意味を加えます。
例: Aさんは「この会議に興味がない」と解釈する。
### 4. 仮定の構築
意味づけに基づいて、さらに先の仮定を立てます。
例: Aさんは会議の準備をしていなかったのだろうと推測する。
### 5. 結論を導き出す
仮定を事実とみなし、最終的な結論を導きます。
例: Aさんは「仕事に対するモチベーションが低い」と結論づける。
### 6. 信念の採用
導き出された結論が、その人や状況に対する信念として定着します。
例: Aさんはやる気がない人だという信念を持つ。
### 7. 行動
確立された信念に基づいて、具体的な行動を起こします。
例: 今後Aさんには重要な仕事を任せないという行動に出る。
出力
ミーティングで発言しなかったAさんの行動について、ありそうな思考プロセスを推論のはしごを元に3つ説明します。
---
### 例1:発言の機会をうかがっていたケース
このケースでは、Aさんは会議の進行状況を慎重に観察し、発言すべきタイミングを見極めようとしています。
1. **事実の観察:** Aさんは会議で何も発言しなかった。
2. **事実の選択:** 参加メンバーの顔ぶれ、議題の複雑さ、議論のペースに焦点を当てる。
3. **意味づけ:** 「この議題はまだ議論が収束していない」「自分の意見をここで言っても、かえって議論を混乱させるかもしれない」と解釈する。
4. **仮定の構築:** 議論の全体像を理解し、より建設的な提案ができるタイミングを待つのが最善だと仮定する。
5. **結論を導き出す:** 「現時点で発言しないことが、チームにとって最も良い選択だ」と結論づける。
6. **信念の採用:** チーム全体の利益を最優先に行動すべきだという信念を持つ。
7. **行動:** 発言の機会をうかがい、最終的に発言せずに会議を終える。
---
### 例2:発言することに不安を感じていたケース
このケースでは、Aさんは過去の経験から発言することに自信がなく、緊張しています。
1. **事実の観察:** Aさんは会議で何も発言しなかった。
2. **事実の選択:** 過去に会議で発言した際に、意見が否定されたり、うまく説明できなかったりした経験に焦点を当てる。
3. **意味づけ:** 「自分の意見は間違っているかもしれない」「うまく伝えられず、恥をかくかもしれない」と解釈する。
4. **仮定の構築:** 発言することで、再び失敗するリスクがあると考え、発言しない方が安全だと仮定する。
5. **結論を導き出す:** 「発言しない方が、自分にとって精神的な負担が少ない」と結論づける。
6. **信念の採用:** 会議での発言は、自分にとってリスクが高い行動だという信念を持つ。
7. **行動:** 会議中、発言を控え、他の人の意見を聞くことに徹する。
---
### 例3:すでに解決策を持っている、あるいは賛成していたケース
このケースでは、Aさんはすでに議題に対して自分なりの答えを持っており、他の人の意見を聞いて確認しようとしています。
1. **事実の観察:** Aさんは会議で何も発言しなかった。
2. **事実の選択:** 議題に対する事前知識や、すでに自分の中で持っている解決策に焦点を当てる。
3. **意味づけ:** 「この議題については、すでに自分の中で結論が出ている」「他のメンバーの意見も自分の考えと似ている」と解釈する。
4. **仮定の構築:** 自分の意見をわざわざ述べなくても、議論は正しい方向に進むだろうと仮定する。
5. **結論を導き出す:** 「自分の意見を述べる必要はない」と結論づける。
6. **信念の採用:** チームの議論を信じ、不必要な発言は控えるべきだという信念を持つ。
7. **行動:** 会議中、他のメンバーの意見を聞き、自分の考えと一致していることを確認し、発言せずに会議を終える。
他者の思考を整理する場面
他者の思考を推測する必要があるような場面について、本来であれば話題が出たときに質問して不明点を明確にしたり、相手の言動の意図を決めつけず、意図を確認するのがベストですが、毎回そのようにできるとは限りません。
詳細を確認できず、今更あとから質問しにくいような場面で改めて整理してみるとよいでしょう。
補足
推論のはしごを用いた思考プロセスの整理は、他者の考えを推測するケースだけではなく、内省にも役立ちます。
瞬間的に行った判断が妥当だったのか、バイアスがあったのか、誤った解釈があったのかなどを確認しやすくなります。
また、他者の思考のプロセス・自己の思考のプロセスのどちらについても繰り返し整理する経験を繰り返すことで、思考プロセスに対する理解が高まります。
結果として、自分の思考の詳細について自覚的になり、バイアスに囚われにくくなったり、他者の思考の詳細を思い描き、確認するための質問がうまくなるなどの効果があるでしょう。