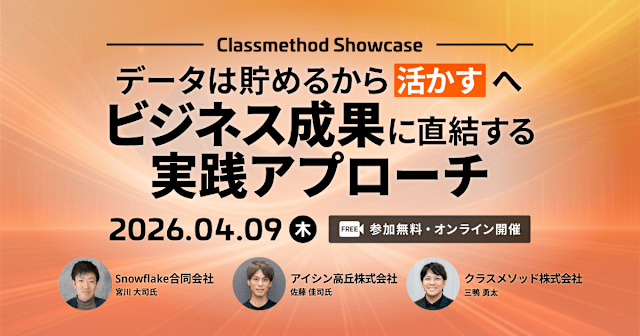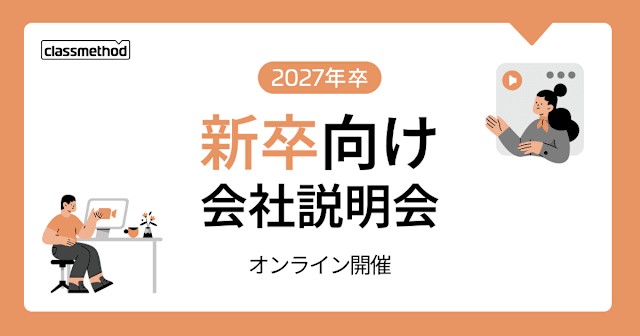専門スキル以外の成長について目を向ける
こんにちは。人事グループ・組織開発室に所属し、組織開発を担当しているてぃーびーです。
仕事において成長について考える場合、要素は一つではありません。
一方で、専門職の場合、専門知識・専門スキルなどが成長対象として注目されがちです。専門スキルはもちろん重要ですが、それだけでは十分ではありません。仕事の成長にはその他の要素も不可欠です。
※専門スキルはハードスキルとも呼ばれます。
この記事では、専門スキル以外の成長についてまとめます。
専門スキル以外の成長の要素
専門スキル以外の成長要素は、以下のとおり分類できます。
| カテゴリ | サブカテゴリ | 内容 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 知識 | ドメイン知識 | 業界や事業領域に関する知識 | ユーザーやビジネスの理解に直結し、実務の精度と説得力を高める |
| 知識 | 社内知識 | 社内制度、文化、業務プロセス、関係者などの理解 | 業務をスムーズに遂行したり、円滑に連携するために必要 |
| ソフトスキル | 対人スキル | コミュニケーション、ファシリテーション、チームワークなど | 他者との協働を通じて成果を発揮するソフトスキル |
| ソフトスキル | 認知スキル | 論理的思考、問題解決、タスク分解、自己管理、批判的思考など | 主に個人の思考や作業遂行で発揮されるソフトスキル |
| その他 | マインド | 責任感、柔軟性、誠実さなど | 行動の根本となり、信頼や成長スピードに影響 |
| その他 | 経験 | 実際に行動し、成果や失敗を通じて得た蓄積 | 暗黙知や状況判断力の源泉となる |
| その他 | ノウハウ | 効率的な進め方、トラブル回避策などの具体的手段 | 再現性のある成果やチーム貢献につながる |
各要素のポータビリティ
仕事で身につける知識やスキルは他の環境や他の職種でも通用するかどうかに関わるポータビリティの特性があります。
各要素のポータビリティは以下のようになっています。
| 要素 | ポータビリティ | 補足 |
|---|---|---|
| ソフトスキル | 高 | 認知スキルや対人スキルはどの職種でも必要とされ、業界・職種に依存せず活用できます |
| マインド | 高 | 誠実さ、柔軟性、責任感などは、どの環境でも信頼や成果につながります |
| ノウハウ | 中〜高 | 再現性のあるノウハウは他の環境でも役立ちます |
| 専門スキル | 低〜中 | 特定の職種・技術領域に依存し、転職先・異動先・職種変更時に使えないこともあります |
| ドメイン知識 | 低〜中 | 特定業界・分野に限定される知識であり、汎用性は限定的です |
| 社内知識 | 低 | 特定組織に閉じた知識で、転職先では無効になることが多い |
このように整理すると、職種や会社に依存しない成長資産として、ソフトスキル・マインド・ノウハウの重要性が際立ちます。
その中でもソフトスキルやマインドには多くの環境で必要となるいくつかの共有の要素があります。
仮にキャリアステージに応じて3段階に分類してみます。
| 段階 | 役割 | 必要なソフトスキル・マインドの例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1. 担当者レベル | 周囲と協力し、業務をやり遂げる | 誠実さ、責任感、報連相、タスク管理、協調性 | 周囲と協力しつつ自分の役割を果たすための基礎的な力 |
| 2. 小規模リーダーレベル | 周囲をまとめながら、チームで成果を出す | 巻き込み力、調整力、状況把握力、フィードバック、柔軟性、視点の切り替え | 自分+他者の成果を最大化する力が求められる |
| 3. 戦略・ビジョンレベル | 組織全体の方向性を示し、仕組みによって組織を動かす | 長期志向、メタ認知、戦略的思考、関係性の構築と維持、信頼の蓄積 | 大局を見て、仕組みや文化で動かす力が問われる |
育成者として気をつけること
部門内にある主要な業務のうち、役割ごとにどんな要素が必要か把握することが必要です。
その際に専門知識や専門スキルだけではなく、ここまで紹介したソフトスキルやマインドなどの要素にも着目します。
一人で整理するのが難しい場合、他のマネージャー・シニアな専門家・人事等と相談しつつ整理するとよいでしょう。
AIも良い相談相手になり得ます。
業務に必要な要素を役割ごとに整理する場合、キャリアラダーと併せて整理するとまとめやすくなります。
キャリアラダーで特定の職種グループにおけるステップアップのはしごを明示する | DevelopersIO
逆にいうと部門やチームに存在する仕事を区別せずにひとまとめに扱っていると整理や理解の難度が高まります。
必要な要素が整理できたら、今度は育成対象のメンバーの現在地の把握です。
現在地を踏まえ、メンバーが今の役割で習熟する段階なのか、次の役割を目指す段階なのかを把握することで成長に向けてどの要素を伸ばす必要があるかを伝え、習得の支援をしやすくなります。
ここで紹介した要素を元にメンバー育成をするなら継続的パフォーマンスマネジメントのアプローチを利用するのが最適です。
継続的パフォーマンスマネジメントに取り組みはじめた | DevelopersIO
本人が気をつけること
常に理想的な環境が揃っているとは限りません。十分な支援を得られない場合、『育成者として必要なこと』に相当する内容を自分で整理したり、周囲を巻き込んで整理する必要があります。自分の人生のハンドルを握るのは自分です。仮に不十分な環境だった場合、改善されるのを待っていては結果は変わりません。できる範囲で自ら動けると少しでも変化を生むことができます。
この際に、もし部門やチーム内に頼れる相手がいない場合は注意が必要です。チームメイトと一緒に整理するのも難しい場合は、他の部門や社外で同様の職務に就いている上級者に相談するとよいでしょう。
以上のような内容を自分の手で意図的に、着実に進めていく鍵はふりかえりです。定期的にふりかえりをすることで着実に前に進んでいくことができます。